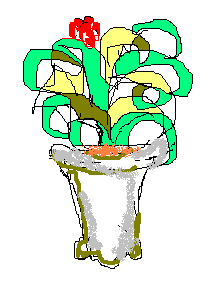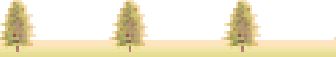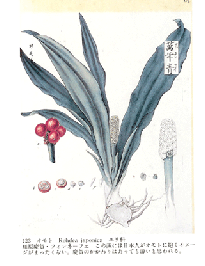万年青と書いて、”おもと”と読みます。
日本原産の植物で、古典的な(最近では伝統園芸とも
言われています)園芸の一つです。
今から400年前に、徳川家康が駿河から江戸に入る時に、
3本の万年青を大切に持って来た故事があって、一年中かわらぬ
緑の葉を愛でて瑞草として庶民にも広く流行し、昔から転居の際に
は、引越しおもとと言って、おもとを持って、家内安全を祈った風習が
あります。
明治に入ってからも、おもと人気が何度かあり、昭和の始め頃、
そして、戦後になってからも、大流行の時代が来る。
株式や土地のような投機のシステムが完備されなかったころは、
一部の人達の投機の対象にされたのでしょう。
万年青には、現在約500ほどの命名された種類があって、
小葉、中葉、大葉に分類されていて、それぞれの固体の特徴を
もっています。
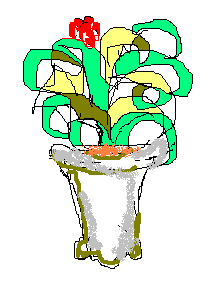
万年青のどこがよいのか・・・・・とよく聞かれますが、
小葉は約10cm、中葉は15cmの鉢で栽培するので、
場所をあまり取らない。
多年草で一年目から親木になる4〜5年の成長するに
従って面白いほど変化する。
本来、半日陰の植物だから、それほど日当たりの少ない
場所でもつくることが出来る。
実生と言って、万年青の種を蒔いて、新種のおもとを作り
出す方法があって、万年青は遺伝的に大変変化しやすい
植物であって、この新種で高級な品種ができれば、高価な
値打ちになることがある。
同好の趣味者との交友が殖え、おもとが取り持つ縁で
おもとを楽しむことが出来る。
万年青には、葉の厚いもの、薄いもの、葉がクルクルと
パーマのように巻くものなど色々な形があります。
また、緑の葉のなかに、曙といって黄色く色の変化する
ものや、白や黄色の斑柄のきれいなものもあります。
まず、一鉢の万年青を入手して、水をやってみて下さい。
そして、万年青趣味の世界に入ってみませんか。
西洋の花と違った世界
日本おもと協会顧問 塚本 洋太郎
京大名誉教授 (中日新聞より)
◆赤い実
正月に赤い実をつけたオモトを用いることは、華道の
一部で習慣になっている。赤い実をつけたオモトの
鑑賞は、古くからのことであろう。
延徳二年(1490年)ごろに描かれた雪舟の
「四季花鳥図」の中に、実をつけたオモトが出ているし、
雪舟の弟子が描いたという「花鳥図」の中にもオモトが
見られる。それ以後、オモトの図は日本の絵画の中にいくつも出て
くる。
このように、オモトの絵は多いので、オモト鑑賞は日本の室町時代に
始まったと考えられるかもしれないが、そうだと決めることはできない。
中国の絵画を見ると、岩についたオモトの図がいくつも出てくる。
古いものでは宋時代のものがあり明、清時代も出てくる。中国に絵の修行
に行っていた雪舟は、当然オモトの絵を見ていたであろうし、中国での
オモト鑑賞を知ったことであろう。宋時代の画家の描いたものの一つには、
はち植えの図があるから、栽培していたことは間違いない。
したがって、オモトの園芸は中国から始まったと考えた方がよいが、
オモトそのものは日本の西部林間に広く自生が見られるから、
あるいは中国と平行して、独自の発展をしたのかも知れない。
江戸末期以後、今日の状況を見ると、非常に高いレベルに
なっていて、中国のオモトとは比較にならない日本独自の園芸植物
になっている。中国のオモトは薬草として用いられてきたが、
園芸植物としては、未発達に終わったといってよいだろう。
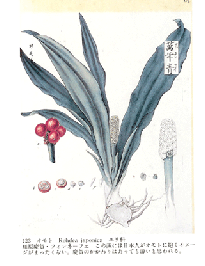
◆大流行
日本でオモトが園芸植物として認められるようになったのは、
元禄時代からのことであるが、はっきりした品種名が出てくるのは、
文化文政年間になってからである。文政十年(1827年)に出た
金太「草木奇品家雅見」の中に図とともに七十品種近くが加わって
いる。
その後、天保年間にオモトは全国的に流行するようになり、
法外な金銭で取引されるようになった。幕府も嘉永五年(1852年)
にオモトを高価に売買することを禁止するようになった。
この大流行と平行して、三河国の長島長兵衛が家康の
江戸城本丸完成の記念にオモトを献上したという伝説も
つくられている。
その後、安政六年(1859年)にオモトの書物に百四十四品種が
あげられているし、慶応、明治までも流行は続いた。そして、
銘鑑や図譜が続いて出された。明治時代にも大きな流行の
ピークが現れ、その後下火のなることなく今日まできている。
以上に見たように、おそらく中国のオモトになって、実のついたものを
主に鑑賞した室町時代から、江戸初期までと、江戸後期以後の
品種分化の時代とを区別することができるが、オモトは日本独自の
園芸植物といえるだろう。日本の文化がなかなか西洋世界に
理解されないのに似て、西洋へのオモトの紹介は皆無である。

◆特異性
オモトの園芸は、まったく日本独自のもので、西洋にはない特異性を
もっている。第一は、葉の芸である。こんなに葉が変化して珍しい
形を示すものは、西洋で発達した園芸植物では見られない。
第二は、そのさびのある葉色である。西洋でもパステルカラーは
好まれるが、オモトの葉の変化はパステルカラーといったものではなく、
日本独自のさびの色というべきであろう。
バラやチューリップなどの西洋の花とは全く異なった世界といわなければ
ならない。もっとも、鹿児島地方に多いサツマオモトは雄大で、観葉
植物として見ても立派である。この系統あたりから、もっと世界に
紹介し、売り出したいものである。
豊明園発行 万年青の歴史 より


|