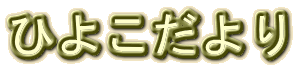��8�����i2024�N8��1���j
�@�@�u���M�I�v�u���S�I�v�u���R�I�v�B�����炮�݂̎q�ǂ������̐��������܂��B7�����{�ɂb�`�o�i�G���p�������g���Ȃ���j�ɂ��肢���Ď��{�������[�N�V���b�v�Ŋw���t�ł��B�q�ǂ������ɐ�삯�ĕی�҂̕��̃��[�N�V���b�v���J�Â��܂����B���N�����{����\��ł��̂ŎQ�����Ă������������ł��B
�@�@�q�ǂ������͂R���ԘA���Ŏw�����̕��̂��b��l�`���g���������ɂ��u�����鐫�\�͂�U���Ȃǂ��玩������邱�Ɓv�A�u�����͂��������̂Ȃ���Ȑl�v�Ƃ������Ƃ��w�т܂����B
�@�@���{�l�͌����u�ς��邱�Ɓv��u�䖝���邱�Ɓv�ɔ����������₷���ł����A���̊w�тł͎q�ǂ��������ۈ牀�ł������Ă���ԁA�ЂƁi�F�B�j���猙�Ȃ��Ƃ����ꂽ�Ƃ��ɂ́u���₾�v�ƌ����Ă����B�ق��̐l�i�ۈ�m�j�ɘb���Ă����B�ǂ�Ȃɏ������q�ǂ��ł��A�݂�ȓ��������i��{�I�l���j������Ƃ������Ƃ��A�����������Ă��̂����w�т܂����B
�@�@�s�u�j���[�X�Ŏq�ǂ��ɑ��鐫�\�͂��悭�ڂɂ��܂��B�C�M���X�ł͂P�O�N���O����c�a�r�i�O���J���y�ёO���ҏA�Ɛ����@�\�j�Ƃ����d�g�݂�����A�q�ǂ�����������Ă��܂����A���{�ł����E��ۈ�W�҂ɂ�鐫�ƍ߂��������Ă��邱�Ƃ��ē��{��DBS�i���ǂ����\�͖h�~�@�j���U���P�X���������܂����B�����ʂ���̋^�`�͂���Ȃ�����{�s�͂Q�O�Q�U�N�ł��B
�@�@�Ђ悱�ۈ牀�ł͎q�ǂ������������鐫��Q�����錈�ӂ���A���ɓ��O�ʼn������ނ�݂ɎB�e���Ȃ��A���ɓ��ɂ����Ă͕ی�ҏ��g�т���A�Ђ悱����蓙�Ɍl��ƂȂ�t���l�[���͋L�ڂ��Ȃ��A�ȂǕی�҂̊F����ɂ��肢���Ă��鎟��ł��B
��7�����i2024�N7��1���j
�@�@�T���̍��J�����]���āA���悢��ҏ�������Ă��܂����B�����̓v�[���J���̗\��ł������A���J�E�����E�g�Q���ӕo�Ă����̂ʼn������܂����B�q�ǂ������͂�������ł����y���݂͐�ɐL�����Ƃɂ��āA�v���ʂ�ɂȂ�Ȃ����Ƃ����邱�Ƃ��w�т܂����B����Q�����̊ԁA���̐_�l���q�ǂ��������v��������v�[���␅�V�т��y���߂�悤�ɁA�ƌ�����Ă���邱�Ƃł��傤�B
�@�@�Ђ悱�ۈ牀�ł́A���ɂ��`���Ƃ��Ďq�ǂ�������������Ă���鑶�݂����o�������̖ݐ[���ɉB��Z��ł���ƌ����Ă��܂��B�Ȃ����A��������ĂɂȂ�Ǝq�ǂ������̎����C�ɂȂ��āA���A���炻���Ƃ̂����Č�����A�莆�����ꂽ�肷�邻���ł��B���N���A�l�q�����ɗ��邩������܂���ˁB
�@�@�ۈ牀�ł̐����͈��S�ł��邶������Ƃ������Ԃ̗���̒��ŁA�g�߂Ȋ��Ɏ����I�ɓ��������Ȃ���A�v���������͂̐��E�ɑ��Ă̍D��S��T���S����������A�F�B�Ɗւ��Ȃ���l�Ƃ̊W���w�ђz���Ă������߂ɂƂĂ��厖�Ȏ����ł��B�c������Ɏ����̊������������܂��ċ����Ȃ��߂������Ƃ��A���̌�̐l���̂���l�����߂邱�ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B���������Ӗ��ł��A�����̕ۈ�ɂ����āA�q�ǂ�������l��l����ɂ���A�F�߂���悤�ɂ��čs�������ł��B
�@�@���Ă��ҏ��̓��X�ƂȂ�܂����A���s���̂��Ƃ��ɕۈ�Q���Ȃǂŕۈ�̗l�q����������Ƃ���������ĕی�҂݂̂Ȃ���Ƃ̘A�g��z���Ă��������Ɗ���Ă��܂��B
�@�@�܂��A�q�ǂ����ۈ�m�ɂ��s�҂�\�͂̔�Q�ɑ����������������Ă��܂��B���������ɂ͊W���Ȃ��Ǝv�����܂��A�ی�҂̊F����͂��߁A�n���q�ǂ��Ɋւ��w�Z�A�ۈ珊���̐E�����q�ǂ��������Q�ɑ��킹�Ȃ����߂̗\�h��ɂ��Ċw�сA�b�������@����v�悵�܂����B���Z�����Ƃ͎v���܂����A���Q�����������܂��悤���肢�������܂��B�@
��6�����i2024�N6��1���j
�@�@�U���ƌ����u�~�J�v���v�������ׂ܂��ˁB���N�̔~�J����͗�N���x�����{���̗\�z�ł����A������W���W�����V���V�̎����͓�������̂ŁA�q�ǂ����������K�ɉ߂�����悤�ɁA�v�������ۈ牀�Ŋy�����߂�����悤�ɂ������ł��B����ł͑����J���~���Ă��A�ǂ�����т��o����̂ł��Ƃł͐���ςł��ˁB�D���݂͂����ɂ����̂ŁA����Ă��悢����p�ӂ��Ă���������K���ł��B�@
�@�@�q�ǂ��������D������ɓy�Ɛ����g���ėV���́A�ۈ牀�ł͔r���a�̂܂�ƌ����^���ɒ������Ă��āA������d�����Ȃ����Ƃ�����߂�C���������ɁA�ǂ�ŗV��n�����q�ǂ������Ɗy���߂�ۈ���ǂ��n�邩�Ɩ͍����ł��B
�@�@����͍�N�ȗ��A�����Ȃ�������낢��ȑ̌����ł���悤�ɏ������������Ă��āA���N��̗F�B��A�Z�펙���܂߂��ٔN��ł̗V�т��L�����Ă��܂��B�܂��A������Ă̐��V�шȊO�ɂ��q�ǂ��������̂т̂їV�ׂ��Ԃɂ���p���v���߂��点�Ă��܂��B
�@�@�ȑO�s�u�ԑg�œs�}���1�Ԃ̕]���́u�Γ��v�ƕ�������Ă��܂����B�L���ň��S�Ȗؗ���������Ƃ���ɑ����Ă���̂ŁA������Ƃ������Ԃɂ����Ƒ��ł̎U�����y���߂܂��ˁB�Ђ悱�ۈ牀�����b���Ď��R�����Ȃ���ۈ�����邱�Ƃ��ł��邱�ƂɊ��ӂł��B���Ƒ�����݂̗��s��L�����v�ȂǑ傫�Ȍv��łȂ��Ă�����I�ȏ����ȑ̌����q�ǂ������ɂ͐g�߂Ȏ��R�Ƃ̐G�ꍇ���ƂȂ�A�q�ǂ����m�̏�������T���S�̈炿�Ɍq�����Ă��܂��B
��5�����i2024�N5��1���j
�@�@�҂�҂�P�O���A�͂Ƃۂ��ۂP�P���A�������R���A�����Q���̐V���������}���ē��₩�ȐV�N�x�S�����߂��A�S�[���f���E�B�[�N�ɓ���܂����B��������]���������T���͂������A�����A���邩������ɂP������������̂ō��킹�ĂP�O�X���̉������ɂȂ�܂��B
�@�@���ŏ��q���������ċv�����ł����A�s�}������l�s�̒��Ő��єN��ł��Ⴂ�ƌ����Ȃ�����A�w�O�������͌������Ă��܂��B�Ђ悱�ۈ牀�ł͓��X�p���t���Ȏq�ǂ��������吨�ʂ��ė���̂Ŋ��C�����茳�C�����ς��ł����A����ŊJ����������w�߂Ă���ۈ�҂̍���������ł��B
�@�@�ۈ�m�{���Z�o�g�ŕۈ珊�ɋΖ����Ă��Ȃ��吨�̕ۈ�m���i�ۗL�҂ɍēx�A�ۈ�̖ʔ�����m���Ă�����ĕۈ�m�Ƃ��ē����Ăق����Ɗ���Ă��܂��B
�@�@�q�ǂ������ɂƂ��ĕۈ牀�͂܂��Ɂu��Q�̂������v�ł��B�F�B�Ɩ����ɂȂ��ėV�сA�q�ǂ�������l��l�������ł���悤�ɁA���낢��Ȍ��̕ۈ�m�����ƍא�łȂ����Ԃ���������ւ��A����̐S�̂����������H�₨���H�ׁA�������Ă������薰��B����ȉ��ł��Ȃ����ʂ̕�炵���߂܂��邵���ς����X��������ɂ����āA���ƂȂ̉��l�ςɐU����q�ǂ������ɂ܂��ۏႳ���ׂ����Ƃ��Ǝv���Ă��܂��B
��4�����i2024�N4��1���j
�@�@���̊J�Ԃ��y���݂ɂ��Ȃ�����A�ˑR�̖\���J�Ɍ�����ꂽ�N�x���ł����B���Z�������A�ۈ�ŏI���̒Z�k�ۈ�ɂ����������͂��肪�Ƃ��������܂����B�ۈ牀�͊w�Z��c�t���ƈ���ďt�x�݂��Ȃ��̂ŁA�ۈ�ŏI���̗[�����烍�b�J�[��C���̖��O��t���ւ�����A������e�[�u���̃T�C�Y���m�F���ĂS���P������V�����S�C�ł̕ۈ炪�n�܂�܂��B���N�x�͂Q�S�l�̓��������������̂ł��炭�͌��C�ȋ��������ۈ牀���ɋ����n�邱�Ƃł��傤�B�R���i���g�債�Ă�����Ԃ͓����N���X�ł̐e�q�ʉ��͊����h�~�̊ϓ_��蒆�~���Ă��܂������A���̍s���ȂǂƓ��l�ɏ��X�ɖ߂��Ă������ƍl���Ă��܂��B
�@�@�q�ǂ����������ꂼ��̔��B�̎d���ň��S���Ă������ƈ���Ă�����悤�ɁA�܂��ی�҂̊F����̂��q����ɑ���z�����~�߂Ȃ��炲�ꏏ�ɐV�����P�N�A�ۈ��i�߂Ă܂���܂��B
�@�@���N�x���q�ǂ�������^�ɁA���ׂĂ̐E��̐E�����b�������ďd��Ȏ��̂�h���A�Ђ悱�ۈ牀�̕ۈ�����߂Ă��������Ɗ���Ă��܂��B���N�x�������������͂��肢�������܂��B
�@�@
��3�����i2024�N3��1���j
�Q�����͊��މē��ƍ~��̓~�������荬�������H�L�ȓ��X���߂����܂����B���ƂȂ́u�̂ɏ��I�v�ȂǂƂڂ₫�܂����A�q�ǂ������̓^���N�g�b�v�Ŋ��������Ȃ��牀��𑖂�������A�t���[�X���H�D������Ɩڂ܂��邵���C�ۂ̕ω��ɂ��߂������C�����ς��ł��B����A�C���t���G���U��R���i�ɜ늳����q�ǂ����������āA�ی�҂̕��͂قڂP�T�ԋx�ނ��ƂɂȂ�̂ő�ςł��ˁB
�@�@���ėߘa�T�N�x���I���ɋ߂Â��A�q�ǂ��������N�x���߂Ƃ͑S���Ⴄ�p�������Ă���Ă��܂��B�������Ń~���N������ł����҂�҂�̎q�ǂ������͎��R�ɕ������ۈ牀�ł̐�����搉̂��Ă��܂��B�����炮�݂̎q�ǂ������͎v���������R�ɁA��_�ɉ߂������Ђ悱�ł̓��X�𖼎c�ɂ��������Ă���̂ł��傤�B���X�A�s���ȕ\�����������A�t�ɂ͂��Ⴌ���������Ȃ����肵�Ă��܂��B������ӂ��ʼn��x�������肵�Ă��������ς�������ق���q�ǂ������ɁA�u���w�Z�ɍs�����炨��͏o�Ȃ����ǁA���Ȃ����������낤�ȁv�ȂǂƂ��������̋C�����ɂȂ��Ă��܂��B�Ƃ�����A�c��̓��X���ꂼ��̃N���X�ł�������V��ŁA�V�����N�x���}���Ăق����ł��B
�@�@���N�x�́A���E���Ő푈���������Ȃ��Ђ�����s����X�ő����̍Г�Ɍ������܂����B�܂��A�n�k��R�Ύ��Ȃǂ̎��R�ЊQ��������Ƃ���Ŗu�����܂����B�����ł��\�o�����ł̑�n�k�ɂ�葽���̋]���҂��o�����Ƃ͋L���ɐV�������Ƃł��B�ǂ�Ȃɕ������i�����Ă��厩�R�̋��Ђɂ͋t�炦�Ȃ��ƁA���炽�߂Ċ����܂����B���ꂩ���A�������Ԃ����ł����q�ǂ������ɂ́A���낢��ȑ̌���ʂ��Ď��R�̈̑傳�ƕ|�������X�ɒm���Ă��炢�����Ɗ肢�܂��B
�@�@���N�x���l�X�ȏo�����ɑΛ������Ă��������܂����B�����M�d�Ȍo���Ƃ��ĐE���ꓯ�Ƌ��ɕۈ�̎��̌���Ɋ������ĎQ��܂��B������q�ǂ������̍K���ɂȂ���ׂ��A�����Ȃ��ӌ��������������܂��悤���肢�������܂��B�����͂��肪�Ƃ��������܂����B
�@�@
��2�����i2024�N2��1���j
���N�x���c��Q�����ƂȂ�A�P�����ɗ��N�x�̕ۈ珊���p�������ʂ��ʒm���ꂽ�̂ŁA�N�x���ƐV�N�x�̕ۈ�̌v�����s���čl���鎞���ƂȂ�A��N�̂��ƂȂ���Q���������Ȃ��Ă��܂����B
�@�@���ǂ������ɂ��ƂȂ̃o�^�o�^���`���Ȃ��悤�ɂ��Ă��܂����A�����炮�݂̂��ǂ������͑����Ə��w�Z���w�ƌ�����厖���܂����Ɋ����ė������Ȃ��C�����ɂȂ��Ă���悤�ł��B�قƂ�ǂ̎q�ǂ����U�N���̔N�����߂����ė����̂ł�����₵���C�����ɂȂ��ē��R�A�l���̋@���̃g���l���̓�����Ȃ̂ł��ˁB�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�ۈ珊�������Ă͍�N�P�Q���Ɋt�c���肳�ꂽ�u���ǂ������헪�v�ɂ����ĕۈ珊�E���z�u��ɂ��ĉ������s���Ƃ��Ă��܂��B�܂��A�u���ǂ��N�ł��ʉ����x�v��n�݂��ďA�J�̔@�����킸�A���ǂ����ۈ珊�ʼn߂������Ԃ�ۏႷ��Ƃ����Ă��܂��B�ݑ�ō��������Ă���e�q���ۈ牀�ɗV�тɗ�����A�a�����鐧�x�͂��ǂ����̎���ɂ����ė��z�I�Ƃ͎v���܂����A���݂̈ꎞ�ۈ��q��Ďx�����_�Ƃǂ��Ⴄ�̂��A���ł����A���t�ȕۈ�m�z�u�ł͊댯�������̂ł͂Ȃ����A�Ȃǂ킩��Ȃ����Ƃ��炯�ł��B
�@�@���ׂĂ̂��ǂ��������~�����ĐÂ܂�Ԃ������ɂŁA����傫�Ȏ��̂₯�����Ȃ��߂��������ƂɊ��ӂ��閈���ł����A���������A�C���t���G���U��R���i�̗��s�����܂�Ȃ����ő̒��Ǘ��ɋC��t���܂��傤�B
�@
��1�����i2024�N1��4���j
�@�@�\��x�̒��ŗB����݂��Ȃ������ł���C�N�̏��߂ł��B�N���N�n�ɂ����ē~�Ƃ͎v���Ȃ��قǒg�����S�n�悢���X�ł������A���U�ɂ͐ΐ쌧�ő�n�k�ƒÔg�̑�ЊQ�A�Q���ɂ͉H�c��`�Ŕ�s�@���̂��N�������̋]���҂��o�Ă������C�������@���ꂽ�悤�ł��B
�@�@��N���ɂ̓C���t���G���U��V�^�R���i���ēx�͂��n�߂āA�x���f�Â𗘗p���ꂽ���ƒ낪���������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����Ȃ��ǂ������邲�ƒ�͂Ȃ��Ȃ��v���ʂ�ɂȂ�Ȃ��̂���Ԃł��ˁB�R���i���T�ނɂȂ��Ďv���Ƃǂ܂��Ă�����l���ł̈��H�̋@����������Ƃ������̈�A�Ƃ������Ă��܂����A���̗ǂ��l�X�ƏW�܂肽���C�����͂悭�킩��܂��B�ۈ牀�̍s���̎����F����y�������ł��ˁB
�@�@���N�x�͂S���ȗ��c���N���X�ł̈ٔN��̊ւ�𑝂₻���ƁA����̎��Ԃɂ�����ۈ玺���u������ӂ��v�Ɩ��ł��Ă����E���邩�E������̂��ǂ��������ߐ���ɂ��ꂼ��u�����Ō��߂ė�������ĐH�ׂ�v�Ƃ������������݂܂����B�͂��߂͑��N���X�̎q������Ȃ�Ȃ����i�ɂ����낢�ő��������Ȃ�������A�܂�������q�����܂������A����Ɋ���ď��q�g�[�N������ȗl�q�������܂��B���ʁA�j�q�ł͏��X�����̉߂����ʂ���������ƁA�������꒩��[�ɂ͂����Ȃ����̂��Ȃ��Ɗ����Ă��܂����A�ٔN��̂��ǂ��̊ւ肪�[�܂��Ă���ʂ�����A����ǂ����Ă������������ǂ������ɕ����Ă݂悤�Ǝv���܂��B�Ђ悱�ۈ牀�͌Z�펙�������ʂ��Ă��Ă���̂ŁA�w�Z�ł̓��N��̊ւ�łȂ��ƒ�̉����̂悤�Ȃ̂т̂т������͋C�������o����Ă���̂��A�ǂ��ɂ��������ɂ��Ђ悱�ۈ牀�̓����Ǝv���܂��B���ꂼ��ʌ̉ƒ�Ő��܂����Ă��邱�ǂ����������ꂩ��̒����N���������ɂ��āA�S�n�悭�������Ă����̂��ۈ牀�̉e���͑傫���Ǝv���܂��B�����͍�N�P�P���ɕی�҂̊F����ɃA���P�[�g�̂����͂�������������R�ҕ]������R����̂ŁA��������p�x����ۈ��U��Ԃ邱�Ƃ��ł���Ɗ��҂��Ă��܂��B
�@�@���N�x�͂��ƂR�����ł����A�V�N���X�V���̓��j���ɂ͐E���S���̎Q���Ŏ��{����u�S�̐E����c�v�̏�ł��ꂼ��̃N���X�̕ۈ瑍�����s���A�ӌ��������Ȃ��瑼�̃N���X�Ƃ̘A�g�����Ɍ����Ă����܂��B�ۈ�m�Ԃ̃R�~���j�P�[�V�����̗ǂ��͕ۈ�̎��Ɋւ�邱�Ƃł�����[��������c�ɂ������ł����A�ۈ���e�ɂ��ĕی�҂̕��X�̌��ݓI�Ȃ��ӌ����f�������Ɗ���Ă��܂��B
��12�����i2023�N12��1���j
�@�@�P�Q���́u�t���v�ƌ����A�́A�N���ɖ@�����s���Ƃ������đm�����Z����������l�q��\�킵�����̂Ƃ��B����ł��N�̐��͑�|���₨�����̐H��̏����ȂǂŖZ�����C���[�W�͂���܂����A���ǂ��̂���ƒ�ł̓N���X�}�X�C�x���g�Ȃǂłɂ��키���Ƃ������ł��傤�B�����͕ۈ牀�̓���̒��ł����ǂ������͒����̋x�݂��Ђ����Ă������������C���ɂȂ�܂��B�C���t���G���U��A�f�m�E�B���X�����ǂ��͂���Ă���܂ł����A���N�ɉ߂����ĉƑ��Ŋy�����N���N�n���}�������ł��ˁB
�@�@�N���ς��ƊԂ��Ȃ��ߘa�U�N�x�ۈ珊�^�c�Ɍ����ėl�X�ȓ���������܂��B�ی�҂̕��̍ő�̊S�͐V�N�x�̕ۈ�̐�������̉ۂł��傤���B�����ɂ������̌��w�҂���������܂������A��������ɂ��Ă͌ʂ̕ۈ牀�ł͂Ȃ����l�s���s���̂ŕۈ牀�Ƃ��Ă͔Y�܂��ɍς݂܂��B����ŕۈ���e�ɖ��S�Ȃ���A�Ƃ肠�����\������œ������肵�����X�Ƃ̓�����̃~�X�}�b�`���뜜������Ȃ��ʂ�����A������͐[���ł��B
�@�@�s�}�Ђ悱�ۈ牀�͖��ԕۈ牀�Ȃ̂Ō����ۈ牀�̕ۈ痝�O�Ƃ͈قȂ�A�ۈ���j�ɂ͐ݗ��҂̋����v�����ꂪ����܂��B�قȂ�ƒ���̒��Ő��܂�炿�A���܂��܂Ȍ�������ǂ������B�ǂ̎q�ɂƂ��Ă������̕ۈ牀�ł̂����тƐ������y�����Ɠ����ɁA�F�B�Ƃ̂������̒��Ől�Ƃ��đ�Ȃ��Ƃ̊�{���w�тȂ��炽���܂�������Ăق����ƁA�E�������Ƙb�������Ȃ���^�c���Ă��܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@���ǂ��̐l�������Ȃ��鎖�Ă������N���Ă�������̏ɁA���ł͎q��Ďx�����������N�ł��ۈ珊�ۈ������悤�ɁA�Ɛ��i��ł��܂��B���ۓI�Ƀg�b�v�N���X�Œ�����E���q���̐i�ޓ��{���A�����A����w�����l�����S�Ɉ琬���Ă����ӔC�̈�[��ۈ牀�A�c�t���A�w�Z���������Ă��܂����A�����I�ɂ͂ǂ����ڂ����ς��A���t�ł���̂������ȂƂ���ł��B�傫�����Ƃɂ͂��荞�݂������ł����A�ی�҂�n��̕��Ƌ������邱�ƂŐg�߂ȂƂ��납��A���ǂ������̕��a�Ȑ�����n�����邱�Ƃ̈�[��S�����Ƃŋ��e���Ă��炦��Ƃ������ȁA�Ǝv���܂��B
�@���ǂ����������₩�Ɉ���߂ɂ́A���ƂȂ����̗͂��s���ł��邱�Ƃ���̂��ǂ��������i���Ă��܂��B
�@�@���N�͊����ǂ̗��s����������ۈ�^�c�ɂ��Ă����낢��Ɩ���N�̔N�ł������A�ۈ�Q�����|���̋��͂Ȃǂ��肪�Ƃ��������܂����B�R���i�����������Ă���悤�ł����܂��܂��y�ςł��܂���ˁB�S�z�̎�͐s���܂��A�悸�͌��N�ŘN�炩�ɉ߂������Ƃ�ڕW�ɁA���N����낵�����肢�������܂��B
��11�����i2023�N11��1���j
�@�@�e�q�ŗV�ԉ�A���ق�ƓV�C�Ɍb�܂�Ċy�����ЂƎ����߂������P�O���ł����B���Z�������Q�����Ă����������肪�Ƃ��������܂����B���̎����͋ߗ��w�Z�̉^����Əd�Ȃ邱�Ƃ����������������ۑ�ƂȂ��Ă��܂��B���N�x�͊J�Ó�������ɂ��Č������K�v�Ɗ����Ă��܂��B�Ƃ�����A���ǂ������ɂƂ��Ă͂����̂��F�B��Ƒ��ƈꏏ�ɗV�ԋ@��͊y�����悤�ŁA�c���ł͊y����������ʂ����G�`���ɂ��ĂQ�x�ڂ̂��y���݂ɂ��Ă��܂��B
�@�@�R���i���T�ނɂȂ����̂ŕۈ�Q�����ĊJ���Ă��܂��B���i�A�ǂ�Ȃ��Ƃ����ĉ߂����Ă��邩�A���F�B�Ƃǂ̂悤�Ɋւ���Ă��邩�ȂǕۈ牀�ł̂��q����̗l�q����������Ƃ�������������@��Ƃ��Ď����Ă��������B
�@�@����������A���Ƃ����ۈ牀�ł��ǂ�������ۈ�҂Ɗy������b������A�V�肵�Ă���l�q�����邱�Ƃ��A���ǂ������ɂƂ��ĕۈ牀�ł̎��Ԃ����S�ŁA��������邱�ƂɌq����Ǝv���܂��B�܂��A�ی�҂̊F�������s���̉����ɂ��Ȃ�Ǝv���܂��B���Ѓ`�������W���Ă݂Ă��������B
�@�@�E�N���C�i�ƃ��V�A�A�C�X���G���ƃp���X�`�i�ł͖ڂ��S�����ƂȂ��Ă��܂��B���{�ł͍l�����Ȃ���Ђ�����ƂȂ��Ă��鎞�ԁE��ԂŁA���ǂ������̋��|�Ɛ�]�͂ǂ�قǂ̎����B���X�͐l�X���K���ɂ��邱�Ƃ��ړ��Ă̏@���ɗR������푈�ł���̂ɁA����l���̂��ǂ����E�C����Ă��錻��͋�����܂���B
�@�@�ۈ牀�ł͑S�g�Ŋ�{���y��\�����Ă��邱�ǂ������A����̂܂܂ɂԂ��荇�����ǂ�������ڂ̓�����ɂ��Ȃ����n�ɂ��邱�ǂ������̕��a��]�ނ���ł��B���{�ɂ��ďo���邱�Ƃ�����A�Ђ悱�ۈ牀�S�̂Ŏ��g�݂����Ǝv���܂��B�������Ă�����������͕���Ȃǂ��߂�ۂɂ����͂����肢���܂��B
��10�����i2023�N10��1���j
�@�@�M���ǎw�����^���Ԃȁu�댯�v��I�����W�́u���d�x���Ɂv�h��Ԃ��ꂽ�X���B�v���悤�ɊO�V�т�v�[���V�т͏o���܂���ł������A���ǂ��������M���ǂǂ��Ȃ��悤�ɂƔz�����Ȃ���̖����ł����B���ƒ�ł��l�X�ȍH�v�����ꂽ���ƂƎv���܂��B�X�����Ɏ��X�y�����������������Ă��A���ǂ��Ƃ��ƂȁA�ǂ�������̂Ƃ����ꂪ�o�Ă��Ă���悤�Ɋ����܂��B��f���Ă��f�f���̂͂�������Ȃ����M�₹�����݂̂��ǂ��������Ă��܂����BTV�̃j���[�X�ł́D�R���i���͂��߁A�C���t���G���U�ARS�E�B���X�����ǁA�q�g���^�j���[���E�B���X�����ǂȂǗl�X�Ȋ����ǂ����s���Ă��Ċw�������Ă��鏬���w�Z�������悤�ł��B�Ђ悱�ۈ牀�ł��X���ȗ��A�a�������������đ����̂��ǂ������M���o����A��M���Ă����肫�炸�ɒ������Ă��܂��B���ǂ��͂��݂��ɋ�����u�����ɐڐG����̂Ŋ������g�債�₷���̂ł��B�Ζ��̎��������Ƃ͎v���܂����A�����ǜ늳��͑̒������Ă���o�����Ă���������Ί����̊g�傪�ɘa�����̂ł͂Ǝv���܂��B
�@�@�P�O���͏��w�Z��ۈ牀�A�c�t���ʼn^�����Ղ�Ȃǂ̍s���������J�Â���܂����A��̑O��U��Ԃ��Ă݂�ƁA��l�ɋK�͂��k������Ă���悤�ł��B�R���i�Ђ�E���̕s���A���̊m�ہA�ߗב�ȂǗl�X�Ȏ�����钆�ł̊J�ÂƂȂ炴��Ȃ��̂ł����A����̑������ł��ǂ������₲�Ƒ����y���߂�悤�ɍl���Ď��{���Ă��܂��B�Ђ悱�ۈ牀�ł́u�e�q�ŗV�ԉ�v��\�肵�Ă��܂����A�S�n�悭�y���ލs���Ƃ��Ă����܂��傤�B
��9�����i2023�N9��1���j
�@�@�ҏ��̉ċx�݂��I���A�w�Z���n�܂�܂����B���N�̂��~�͊e�n����^�䕗�⍂�C���ȂLjُ�C�ۂɌ������ė��s��A�Ȃ��o���Ȃ��������ƒ낪���������̂ł͂Ǝv���܂��B����ł��������Ƃ������Ƒ��ł̎��Ԃ��߂����Ďq�ǂ������͈���傫���Ȃ����悤�ł��B���Ă͏������ĔM���ǎw�����T���������������A�v�[�������т��ł��Ȃ�������������܂����B���̒��ł��������������A�C�Â��Ȃ����ɔM���ǂɂȂ�̂������ł��B�Ђ悱�ۈ牀�ł͖����A�C�ۏ������m�F���Ă��犈�����n�߂Ă��܂��B�u���S�ۈ�ł��̑���Ȃ��v�Ǝv����������ł��傤���A�ЂƂ��ё傫�Ȏ��̂��N�����Ƃ��ɂ́A�܂��Đ�������������邱�Ƃ������Ă͎��Ԃ������Ȃ��̂ł��B
�@�@���܂��܂ȏ�����z�����Ȃ���A�\�Ȍ���̑̌���ۏႵ�����Ɗ���ĕۈ��i�߂Ă��܂����A�����Ő����̑����ۈ�ł���Ȃ�����A�v�������芈���I�Ō��C�����ς��Ȏq�ǂ������̋����Ȃ��\��Ɉ��g���Ă��܂��B
�@�@�ۈ牀�͗l�X�Ȑ��i����̎q�ǂ��������吨�A�������Ԃ�F�B�ƈꏏ�ɉ߂����Ă��܂����A���ꂼ��̉ƒ�ł̈玙���j�≿�l�ρA�q�ǂ��ɑ���z���͗l�X�Ȃ̂ŁA�q�ǂ������̂��������Ă���ƗF�B�Ƃ̊W���ɂ��ƒ�̉e�����傫���Ɗ����܂��B����ǁA���ɉ߂����q�ǂ��������m�̊ւ�̒��ŏ��������݂��̈Ⴂ�ɋC�Â��ĔF�߂���悤�ɂȂ��Ă��܂��B���ƂȂ��Œ�I�ȉ��l�ς����ςŌ��߂����ڂ��邱�Ƃ��ł���A�����ƐL�ѐL�тƈ炿�������Ƃ��ł��邩������܂���ˁB���}�ȓ��X���ɂ��Ȃ���ۈ���������܂��B
�@�@����A�C�O�ł̓E�N���C�i�ƃ��V�A�Ԃ̐푈���甭����s���ȏ��≯������ь����A�k���N�̕p�ɂȃ~�T�C�����ˁA�������������������̊C�m���o�������Ē��������{�Y���Y����S�ʓI�ɗA���֎~����ȂǁA�����O�ł��ĂȂ��������ȑ������u�����Ă��܂��B�܂��ATV��X�}�z�ɂ��̂悤�ȃj���[�X���������A�R���i�����ǂ��T�ނɂȂ������Ƃɂ���Ď������̐����ɓ��킢���߂����l�q�������ɂ��A���Â̍��݂��邱�̎��オ�ǂ�Ȃӂ��ɗ��j�̒��ňʒu�Â�����̂��ȁA���a�ɕ�炵�Ă���q�ǂ������ɂǂ̂悤�ɉe������̂��ȁA�Ȃǂƍ������Ă��܂��܂��B�����q�ǂ������ɂ͕��a�Ȑ�����ۏႵ�����ł��B
��8�����i2023�N8��1���j
�@�@�u�����ł��ˁv�����̈��A�ɂȂ��Ă��邱�̍��A���E�����ҏ��Ɍ������Ă��܂��B���E�C�ۋ@�ցiWMO�j�͂V���̐��E�̕��ϋC�����ϑ��j��ō��Ƃ��Ă��܂��B�u�n�������̎��オ�����v�Ƃ��Đ��E�e���ɋ�̓I�ȍs�������߂Ă��邻���ł��B���������g�̉��̏������Ƃ��납��S�������Ă��������Ƃ���ł��ˁB���ُ̈�C�ۂ͊C�O�ł͑䕗�̑�^�����J�A�^���A�R�щЂȂǑ����̎��R�ЊQ�������N�����A�����ł���J�ɂ��͐�̔×��A�y���ЊQ���e�n�ŕp�����đ吨�̕�����Ђ��Ă��܂��B����҂������n��ł͌�n������ςȂ��Ƃł��傤�B
�@�@�ۈ牀�ł́A�R���i���T�ނƂȂ��ĕۈ�̗l�q���ς���Ă������Ǝv������A�͂��ځA�w���p���M�[�i�A�v�[���M�Ȃǎ��X�Ɋ����ǂ����s������A�����̎w�W�Ƃ���M���ǎw�����u�댯�v�ƂȂ��Ďv���悤�ɕۈ炪�i�߂��Ȃ����X�������Ă��܂��B����A���q����̕a�C�ʼn�������������Ȃ��ی�҂̕��́A��ς��낤�Ƃ��@�����Ă��܂��B�������a�C���������܂��ċ����Ȃ��ۈ牀�ł̎��Ԃ��y����ł������������Ɗ���Ă��܂��B
�@�@��N���̎����ɂ́A�C���A�v�[���ł̎��̂̕������Ȃ�܂��B���N�����łɐ����̎��̂�����܂������q�ǂ������łȂ����ƂȂ��]���ƂȂ�̂����̎��̂ł��ˁB�u�q�ǂ��͐Â��ɓM���v�ƌ����܂��B5�����̐��ł��M��鎖�͂���̂ł�����A�v�[���ۈ�̎��{�ɓ������Ă͏\���ɒ��ӂ��܂��B�ċx�ݒ��̂��o�����ɂ͎Ԃ␅�̎��̂Ȃǂ��ꂮ������p�S���������B
�S������c���N���X�ł͈ٔN��̎��Ԃ��w����J�t�F�x�Ə̂��Ă�����ۈ玺�Ŏ��R�ɂ�����y���ނ悤�ɂ��Ă��܂��B���߂͑��̃N���X�̎q�ǂ������邱�ƂŋC��ꂷ��q�ǂ����������܂������A�S�����o�߂������A����Ă��đ��̃N���X�̎q�ǂ������Ɍ������ĐH�ׂ�p������܂��B�Q�����ɂȂ�ƌߐ����Ȃ��q�ǂ�����������݂ɋN�����ɍs���Ă���Ă��܂��B�˂ڂ��܂Ȃ��ł���������ƐH�ׂ�q������A���ɂ́u�����i�����j�����v�ƌ����q�����܂����A�S������Ȃ����R�ȋC���Ȃ̂ŁA�H����ɂ͑S�����H�ׂ���悤�ɂȂ�܂��B
�@�@���̖ҏ��̒��ŐH�~���Ȃ�������A��������イ���M�≺�����J��Ԃ����肵�Ă��S�z�ɂȂ��Ă���ی�҂̕����������Ƃł��傤�B�ۈ牀�ɒʂ��Ă���N��̎q�ǂ������͂܂��܂��炿�ł͏��S�҃}�[�N�ł�����A���낢��ȏ�ʂŐe�̑z���Ƃ͈Ⴄ�����ɂȂ�����A�t�߂肵����ƁA�D�ɗ����Ȃ����Ƃ����X����Ƃ͎v���܂��B����ǒ����ڂŌ��鎞�ɂ͒����Ɉ���Ă��邱�Ƃ������ł��܂��̂ŁA�������ƍ\���Ă��Ă������������ł��B�@�@�@�@
��7�����i2023�N7��1���j
�@�@�~�J�����錾���o�Ă��Ȃ��̂ɁA�A���̖ҏ��Ɋ������̖����ł��B�M���ǂł̋~�}������H���ł��������Ă���̂ŏ\�����ӂ������ł��ˁB�Ђ悱�ۈ牀�ł͂U�����߂��u���s���p�������i�͂��ځj�v��A�f�m�E�B���X�����ǂɜ늳���鉀����ی�ҁA�E�����}�����Ă���A�P�`�Q�T�ԁA�Ђǂ��ꍇ�͂���ȏ㌇�Ȃ��Ă��������Ă���A�\����Ȃ��v���Ă���܂��B�R���i�����g��ȗ��A�����Ƃ≀���ł͂��܂߂Ƀs���[���b�N�X��߉t���g�p���Đ@���|�����s���Ă��܂����A�ڂɌ����Ȃ��E�B���X���͂т����Ă���悤�ŁA������p�����Ď�E���ł��s���܂��B���ڂ��Ԃ��悤�ł�����A��ȂŎ�f���Ă��������悤���肢���܂��B�����Ȃœo��OK�Ƃ̐f�f�̌�A��Ȃ̌����ł͂��ڂƐf�f�����P�[�X������A�������L�����Ă���C�z������܂��B
�@�@�s�}�敟���ی��Z���^�[�ɂU���P�S���i���j�Ɋ����ǔ��������o���Ĉȗ��A�Q�T�Ԉȏ�o�ߕ��X�V���Ă��܂����܂��A�����҂��O�l�ɂȂ��Ă��Ȃ��̂ŁA�v�[���V�т��n�߂��Ȃ��ł��܂��B�ی��ۂ̎w���ɂ�芴���҂��O�ɂȂ��Ă���V���Ԍo�ߌ�ɏ��߂ĊJ�n�ł��邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B
�@�@���}�ɏI�������āA�q�ǂ��������y���݂ɂ��Ă���v�[���V�т��J�n�������̂ł����������͂�낵�����肢�������܂��B
�@�@�܂��A���l�s���ǂ����N�Ǖۈ�E����^�c�ے����A�v�[���ۈ�����Ă����ʂ̎ʐ^�̎�舵���ɂ��āA���̕ۈ牀�Ńz�[���y�[�W�Ɍf�ڂ��ꂽ�ʐ^���ʂ̃T�C�g��ň��p�i�����j����Ă����Ƃ��������܂����B�f�ڂ��ꂽ�ʐ^�̏��l�����肳��ƍ߂̊댯�ɂ��炳��鋰������邱�Ƃ���A���Ղȓ]�ڂ��s��Ȃ����ƂȂǒ��ӊ��N������܂����B�ċG�x�ɂȂNJO�o����@�������Ǝv���܂����A�q�ǂ������̈��S����Ƃ��ĉ߂����Ă܂���܂��傤�B
��6�����i2023�N6��1���j
�@�@�X�̂����炱����ɃA�W�T�C�����ꂢ�ɍ炢�Ă��܂��B�Ђ悱�ۈ牀�̒��ԏ�e�ɂ��傫�Ȋ����炫�ւ��Ă��܂��B���N�O�A�䂪�Ƃ̔��A�����͂ꂩ�����Ă����̂ňڂ��ւ����̂ł����A�P�N���Ƃɑ傫������Ă��ꂢ�ȉԂ��y���܂��Ă���Ă��܂��B�G���g�����X�ɂ��O�̂���炢����������Ԃ��F�N�₩�ʼn����������u�����ȐF������ˁv�ƌ����Ă��܂��B���|�X�ōw�������ԕc�͂��ꂢ�͂��̎�����Ŗ��c�Ɍ͂�Ă��܂����Ƃ������̂ɁA�A�W�T�C�⓹�[�ɂ����G���͂ǂ�ȂɎ�r�������Ă����N�͂��ԂƂ��炢�Ă����̂ɂ͋��Q���܂��B
�@�@�u�G���̂悤�ɂ����܂�����v�Ƃ́A�_�ߌ��t�Ƃ��Ă悭����܂����A�ǂ̂悤�ɂ�����G���̂悤�ɂ����܂����A����ǐl�̐S���ق��Ƃ�����D�����〉���������˓Y�����l�Ɉ�̂��A�ۈ�̋��ɂł���Ǝv�����ۈ珊�̐E���Ƃ��Ă̏d�ӂ������Ă��܂��B�����A�吨�̎q�ǂ������Ɛڂ��钆�ŗl�X�Ȍ��̎q�ǂ��������ǂ�Ȃ��ƂȂɂȂ�̂��ȁA�Ǝv����y���邱�Ƃ������ł����A���ƒ�ł����܂��܂ɂ��q����Ƃ̏�����v����Ă��邱�Ƃł��傤�B
�@�@�ŋ߁A����AI�i�l�H�m�\�j�����E���Řb��ɂȂ��Ă��܂����A���������x�Ő��E��Ȋ��ł��镶���̐i���ɋ����������ŁA���̐�l�Ԃ̐��E���ǂ�Ȃӂ��ɂȂ邩�ƁA�܂��S�e�f��̐��E�ɓ������܂ꂽ���̂悤�ȋC�����܂��B�ۈ���H�̒��ō���Ȃ��Ƃɏ��荇�����Ƃ��ɁA�u���܁A�Z�Z�ō����Ă��܂��v�ƁA�₢��������u����ł́Z�Z�����炢���ł��傤�v�Ȃ�Ċ����ȉ��Ԃ��ꂽ�肵����ǂ��Ȃ邩�ȁE�E�E�Ȃ�ău���b�N�W���[�N�ł��B�ۈ�̒��ł́A�R���s���[�^�[�̂悤�Ȋ����͋��߂��Ȃ��ł��B
�@�@���E���Ő헐���u�����đ吨�̎q�ǂ��������]���ɂȂ鍬�Ƃ�Ƃ�������w�i�ɁA�����̐l�X���S���I�ɈÂ��s����ɂȂ��Ă��܂��B�ŋ߁A�����ł͔ƍ߂⎖�̂��������������A���Ȃ��炸����̕��͋C�Ɋ������܂�Ă���C�����Ă��܂��B�@
�@�@����Ȏ��ł������l�ЂƂ�قȂ�l�i�̐l�Ԃ����Y���A�v������āA�o�������̍őP��T�荇�����Ƃ��ۈ�ł͋��߂��Ă��邩�Ǝv���܂��B
��5�����i2023�N5��1���j
�V�N�x�ɂȂ��āA���炭�͐Ԃ����̋��������G���g�����X�ɋ����n���Ă��܂������A�ŋ߂͂߂�����ƌ���A�����̎�ނ��ς���Ă��܂����B�q�ǂ������̏������͑f���炵���A�S�[���f���E�B�[�N�œo�����Ȃ����������Ă��S���̐U�o���ɖ߂��Ă��܂��悤�Ȃ��Ƃ͂���܂���̂ŁA���ɓ�������͂��S�z���Ǝv���܂������S���Ă��߂������������B
�@�@�R���i���T�ނɂȂ��čs���̎��R���������A�O������̃C���o�E���h�������Ċό��n���ɂ�����Ă�����i������Ă��܂����A����͂ǂ��Ȃ邩�ȂƊ뜜���܂��B�g�߂Ɋ����҂��o�Ȃ��悤�Ɋ����������Ă����܂��傤�B�Ђ悱�ۈ牀�ł́A�v���Ԃ�ɂЂ悱�܂���v�悵�܂����B�q�ǂ������̕ۈ牀�ł̓���̉����ŁA�q�ǂ������������ʂ�Ɋy����ł����悤�Ɋ���Ă��܂��B�ی�҂̊F���������Ȃ��q����̗l�q�����āA���S���Ă���������Ƃ������ȂƎv���܂��B
��4�����i2023�N4��1���j
�n���Q�P�N�ځA�S���̕ۈ炪�n�܂�܂����B�V�����O�Ύ��P�O���A�P�Ύ��V���A�R�Ύ��P��������đ����P�P�O���ł̃X�^�[�g�ł��B���̂R�N�Ԃ̓R���i�E�B���X�̃p���f�~�b�N�Ő��E�����傫�ȕω��Ɍ������܂����B�Ђ悱�ۈ牀�ł��ۈ��s��������܂ł̂悤�ɂ͂ł����A�H�v���Ȃ���̎��H�ł������A���ʓI�Ɏq�ǂ������̊y���ގp������ꂽ�Ǝv���܂��B���͊������������Ƃ��ĘA�x�����̂T���W�����犴���ǖ@��ł̂T�ށA�G�ߐ��C���t���G���U�Ɠ����̑Ή��ɕς��܂��B�ڍs����ɂ������Đ��Ƃ̊Ԃł̈ӌ��͂���悤�ł����A�ۈ牀�Ƃ��Ă͈����������܂Œʂ�̊����\�h����̂邱�ƂŒ��Â���܂ł̎��Ԃ����̂������ł��B
�@�@��N�x�͂Q�O�N�Ԃ̕ۈ���H�̐U��Ԃ肩��A����̑�^�V������A�z�R�͏C�U���ĂЂ悱�ӂ��ɕϐg��������A���߂����̉���f�r���[��߂����̒��ԓ���Ȃlj��날���т��g���鎎�݂����܂����B�͂Ƃۂ��ۂ��݂̎q�ǂ������₤�������݂̎q�ǂ��������̂т̂їV�Ԃ悤�ɂȂ�ٔN��̊ւ肪�����Ă��܂��B���N�x�͗c���N���X�̎q�ǂ��������ٔN��ʼn߂������Ԃ݂̍�����H�v���Ȃ���A�q�ǂ����m�A�܂��q�ǂ��ƕۈ�m�Ƃ̊W��������Ɍ��シ��悤�Ɏq�ǂ������Ƒ��k���Ȃ���A�Ђ悱�ۈ牀�Ȃ�ł͂̐�����g�ݗ��ĂĂ����܂��B
�@�@�R���i�ŎЉ�̗l�����傫���ς������A�E�N���C�i�̐�Ђ�V���A�E�g���R�ł̑�n�k�Ȃǂɂ���Đ��E�K�͂Ōo�ρE�Y�ƊE�����I�ɕϊv���Ă��܂��B�߂܂��邵���ϓ��̔g�͏����̐����ɂ����M���H���i�A���p�i�Ȃǂ̒l�オ��ȂǑ傫�ȑŌ��ƂȂ��ĉ����Ă��܂��B�ۈ牀�ł��d�C��⋋�H�ޗ���Ȃǂ��啝�ɏオ���Ă���̂ł��܂߂ɓd���������Ȃǔ��X������̂ł����Ή����Ă��܂��B
�@�@�Â��j���[�X���������AWBC���Č�����̕��ϐ��ю��������֓��n��ł͂S�Q�D�S%�����������ŁA�ǂꂾ�����������邢�j���[�X�����]���Ă���������Ă��܂��B���i�͖싅�ɋ������Ȃ��̂ɂ��ꂵ���Ȃ��ăj���[�X�����܂����B�劈���I�肪�������u�`�[�����[�N�v�ƌ���Ă��܂������A��l�̓ˏo�������[�_�[�̑��݂����邱�ƂȂ���A��̖ڕW�Ɍ������Ă݂�ȂŒS�����Ƃ̏d�v�����A�s�[������Ă���Ɗ����܂����B
�@�@�Q�P�N�ڂƂ����ߖڂ̔N�x���߂ɓ�����A���܂ŗl�X�ȏo����������Ȃ�����A�ی�҂̊F����̂������ƐE���̎q�ǂ��ɑ���z���ƃ`�[�����[�N�ɂ���ďd��Ȏ��̂Ȃ��^�c�𑱂���ꂽ���ƂɊ��ӂ��Ă��܂��B
�@�@���q�����̏d�v�{��ƂȂ��č����A���ǂ��ƒ뒡���������܂����A�ۈ牀�͂����Ɓu�q�ǂ���^�Ɂv�ƌ��������Ă��܂����B���̏����̂��߂̏��q����Ƃ������ƂƓ����ɁA�q�ǂ��͎q�ǂ��ł��邱�Ǝ��̂��̎^�ɒl����̂��Ǝv���܂��B���ƂȂ̗l�X�Ȏv�f����łȂ��A�q�ǂ��������q�ǂ��Ƃ��Ď��ꑸ�d����ĉ߂�����ۈ牀�Â���Ɍ����āA�Ђ悱�ۈ牀�̐E���̓`�[�����[�N�Ŋ撣��܂��B������q�ǂ����������S���Ĉ��S�ɉ߂������߂̌��ݓI�Ȃ��ӌ�������������Ǝv���܂��B
��3�����i2023�N3��1���j
�ߘa�S�N�x�ŏI���ɂȂ�܂����B�����P�T�i�Q�O�O�R�j�N�ɑn�݁E�J�����Ĉȗ��A�Q�O�N�̔N�����߂��ĉ��l�s�Ƃ̎s�L�n�ݎ،_�X�V���ꂽ���̎��Ƃ��Ȃ�܂��B�J����������Ζ����Ă���E���⒆�r�œ��E�����E�����ɁA�ۈ璆�̎q�ǂ��̎p��l�X�ȏo�������v���N�����A�U��Ԃ��Ă��܂��B���̂Q�O�N�Ԃɂ͂��ꂵ�����ƁA�h�����ƂȂǂ��낢��Ȃ��Ƃ�����܂������A�܂��A�ۈ�ɂ܂���̋}���ȕω��̗]�g���Ȃ���A�S������͐S�@��]���ĐV���ȂЂ悱�ۈ牀�̕ۈ�̊J�n�ƂȂ�܂��B
�@�@�u�ی�҂Ƙb�������Ȃ����l��l���������̂Ȃ��q�ǂ��Ƃ��Č����A�Љ�̈���Ƃ��Ď�̐��d���Ĉ�݂܂��v�Ƃ͓s�}�Ђ悱�ۈ牀�̕ۈ痝�O�ł��B�F�ۈ珊�n�݂ɓ������ĕۈ�ɑ���z���̏��\��������ł��܂������A�ʂ����Ď��H���Ă��邩�H�ی�҂ɏ\���������Ă��Ă��邩�H�R���i�Ђɂ���Đ��E�������Ƃ�Ƃ��Ă��钆�ŁA�q�ǂ������̌��₩�Ȑ������B�ƕۈ�j�[�Y�̕ω��Ƃ��ǂ̂悤�ɒ������Ă������H
�@�@�R���i�E�B���X�ւ̑Ή������⎩���̂ł܂��܂��ł��钆�ŁA����̕ۈ�̐i�ߕ��͗��z���ł͂Ȃ��A�����̎q�ǂ��̎p����������ƌ��Ȃ���A�ǂ̎q�ǂ��ɂƂ��Ă����S���ĉ߂������Ƃ��ċ@�\����悤�ɂ��Ă����܂��B���݁A�S������̐V�̐��ɂ��ĕۈ�ҊԂł͘b���������d�˂Ȃ���v�悵�Ă��܂��B
�@�@���N�x���ۈ�^�c�ɂ����͂����������肪�Ƃ��������܂����B�V�N�x�����ǂ��ۈ牀�Â���Ɍ����Ă�낵�����肢�������܂��B
��2�����i2023�N2��1���j
�Q���͔@���i�����炬�j�ƌ����܂��B�܂��܂������A�ߗނ��d�˂Ē���i�ߍX���j���Ƃ��痈���Ƃ����̂�����������ł��B��T���͑劦�g���P�����ē��{�C���͑��Ɍ������A������Ƃ��늲�����H�ő�^�A���g���b�N�������������Ă���f����TV�ɉf���o����Ă��܂����B�ቺ�낵�Ŏ��̂ɑ�������҂��吨���炵�āA��҂����Ȃ��n���̕�炵�̌������ɁA�Ƃ����l�C�̂Ȃ��c�ɂŕ�炵�����Ȃ�Ȃ̐g���肳��l���̊Â���m�炳��Ă��܂��B
�@�@�Q���́A���������Ȃ����Ƃɉ����ĐV�N�x�̓������������肷��̂ŁA�S�C�z�u�ȂǕۈ�^�c�ł̏d�v�Ȍ��ߎ����R�ς����A�N�x���̎����������d�Ȃ��čQ�������������Ƃ����Ԃɉ߂�����܂��B�R���͔N�x���̓��ʊ����鐶�����߂����āA�������j����ł͂����炮�݂̎q�ǂ������͂Ђ悱�ۈ牀���珬�w�Z�Ƃ����V�����Љ�Ɍ������Ĕ�ї����Ă����܂��B���ǂ������ƒS�C�͂��̂P�N��U��Ԃ�A�c���ꂽ���X���[�����ĉ߂������Ƃ��Ă��܂��B�����炮�݂̎q�ǂ������͂Ђ悱�ۈ牀�ł̂��C�ɓ���̋��H���j���[�����N�G�X�g���ĐH�ה[�߂悤�Ƃ��Ă��܂��B���������v���o�Â���̂��߂ɂ������������鋋�H���̐搶�����B�Ȃ�Ƃ��ق̂ڂ̂Ƃ����ۈ牀�̓���̕��i�Ǝv���܂��B
�@�@�C���������߂̔h��ȍs��������狗����u���Ђ悱�ۈ牀�̕ۈ�ł́A�����̉��C�Ȃ����Ƃ��q�ǂ������̐[���ɂ����₩�Ȏv���o�ƂȂ��ďZ�ݒ����Ă����Ǝv���Ă��܂��B�����̉ߒ��Ōo������l�X�Ȏ����̎��ɁA�ӂ��Ǝv���o���Ă���邮�炢���������ȁA�Ɗ����Ă��܂��B�@
��1�����i2023�N1��4���j
�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�N�����琳���R�����̊ԁA���l�͓V�C�Ɍb�܂�ĉ��₩�ȗz�C�ł����B�s�������̂Ȃ��x���ɋv���Ԃ�ɋA�Ȃ������������������Ƃł��傤�B���̊Ԃ������Ă��Ă�����������ÐE����E�̕��X�ɂ͊��ӂł��B
�@�@���ɑ������ƗV���n�ɍs���܂����B���\�N�Ԃ�ł������A�����Ă����V���n�̃C���[�W�Ƃ͑傫���l�ς�肵�đ�l���y���߂�悤�ɂȂ��Ă��Ď���̈ڂ낢�������܂����B�Ƒ��A��̐e���q������̂킸��킵�����痣��ĐS���������Ă���̂ł��傤�A��l�ɂ������Ƃ����\������Ă��܂����B���i�͗l�X�Ȃ��Ƃɒǂ��Ă��ĐS���̂��]�T�������Ă���̂�������܂���ˁB
�@�@�s�}�Ђ悱�ۈ牀���J�����ĂQ�O�N���߂��A�S������͂Q�P�N�ڂɂȂ�܂��B�O�g�̓����ۈ玺����͒ʎZ�R�W�N�̔N�����o���A�����̉��������̑����͉ƒ��z���Ċ��Ă��܂��B����ŕۈ���n�߂�������U��Ԃ�Ɩ������ƂĂ��̂ǂ��������C�����܂����A�q�ǂ������̎p�͍����ς��Ȃ��悤�Ɏv���܂��B
�@�@�l�X�ȗ̈�ő��l�������d����A�����̋��X�܂Ńf�W�^�����AICT�����Z�������錻��Љ�ł͍D�ނƍD�܂���ɂ�����炸��炵�Ԃ肪�ω����ē��R�Ȃ���A�q�ǂ������̉߂������͂��ƂȊ��ɂȂ��Ă��܂��B���ʓI�ɁA�l�̎��R�d����ƌ����Ȃ�����A��������SNS�ɂ܂��ƍ߂⎖�̂���q�ǂ������ׂ��w�Z��ƒ�ł͊Ǘ��D��ɂȂ��āA�������Ďq�ǂ������𑧋ꂵ�������Ă���̂�������܂���B
�@�@�S���Ɂu�q�ǂ��ƒ뒡�v���n�݂���A�u���ǂ��܂�Ȃ��v�ւƎЉ�S�̂�ς���d�g�݂����Ƃ���Ă��܂��B���܂ł��ƂȒ��S�̖ڐ��Ŏ{����E�^�p���ꑱ���Ă������Ƃւ̕]���A�����āA�q�ǂ������ɍL�������s���肳��ƒ���̋s�ҁA���q���Ȃnj���̗l�X�Ȗ�蔭�����Ă̑傫�ȕ����]���Ƃ������ƂȂ̂ł��傤���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�q�ǂ������ɂ͎q�ǂ������̐��E������A���ƂȂ͕s�p�ӂɉ�����Ȃ��悤�ɐS���Ă��������B������Љ�A�����q���Љ�̂ǐ^�̓��{�ł����A������l��l����ɂ���鍑�ɂȂ��Ăق����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�R���i�������I���������������ƌ������ł����A�ی�҂̊F����̂������ƕۈ�ґS���̋��͂łЂ悱�ۈ牀���ǂ̎q���̂т̂тƎ�����\�����Ĉ���Ă����ɂӂ��킵����ɂ��Ă��������Ɗ���Ă��܂��B
��12�����i2022�N12��1���j
�@�@���N���삯���ʼn߂��Ă͂�P�Q���ɂȂ�܂����B����͑�|���̂����͂��肪�Ƃ��������܂����B�����猩������ꂢ�ł��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@���A�E�N���C�i�ƃ��V�A�̐푈�A�����Ƒ�p�A�k���N�̋��ЂȂǒn����̂�����Ƃ��낪�s���ŔߎS�ȏɂȂ��Ă��܂��B���{�����ł̓R���i������W�g�ƃC���t���G���U�̓������s���뜜����Ă��܂����A�\���Ƃ͌����Ȃ��ɂ��듊����Â̑Ή����\�ł����炵�͌b�܂�Ă��܂��B���E�œ�̋~�ϊ����������Ȃ��Ă���NPO���c�̂�TV�j���[�X�ł̓E�N���C�i��A�t�K�j�X�^���A�V���A�A�C���h�l�V�A�ȂǑ����̍��̐l�X���d��ȍ����ɂ��邱�Ƃ�����Ă��܂��B���V�V�N���o�Đ푈�̌��҂�����������҂̎����ł���������A�푈�̔ߎS���������ł��Ă��Ȃ����A���N�푈�������������Ă������{���h�q��\�Z����������ȂǍ���ǂ�ȕ����ɐi�ނ̂��뜜���܂��B
�@�@������V�����A����̎��X���g�t�Ɨ��t�̐^���������Ŏq�ǂ������̗V�т��Ă�H�Ƃ͂܂������ω����Ă��܂��B�l�G�̈ڂ낢��S�g�Ŋ�������ĊG�ɂ�������A�}�ӂŒ��ׂ���A���ɂ͂��U���}�b�v���쐬���Ď��X�̗l�q������̖��O�̗R�����l����ȂǁA���ƂȂ��U�����Ȃ��Ă����������ōl���o���������ł�������w��ł���l�q������A�Ђ悱�ۈ牀�Ŏ��R�C�܂܂ɉ߂����Ă���ԂɈ�����u��L�т���́v�������܂��B�@�@�@�@�@
�@�@�����̑啔����ۈ牀�ʼn߂����ėF�B�Ƃ͎��̌Z������G�ꍇ�����Ԃ��������A�C�S�m�ꂽ���ŗe�͂Ȃ����Ԃ�������肪�o�錖�܂ɔ��W���邱�Ƃ�����܂����A���������܂�Ɖ������Ȃ��������̂悤�ɗV�юn�߂܂��B����Ȏ��ɕۈ�҂͐R���҂ɂȂ�̂ł͂Ȃ��A�o���̌����������ē`����悤�ɂ��Ă��܂��B�q�ǂ������̒�����ӂӂƕ����Ă���U���I�ȑz���⌾�t�̗��ɉ������̑̌�������̂��A�Ȃ��̂���F������������𐮂��āA�q�ǂ��������F�B�ƈꏏ�Ɋy�����������ꂽ���Ԃ�L���ɂ��Ă��������ł��B
�@�@���̒��A�f�W�^�������}���ɐi��Ŏq�ǂ������̐����ɂ��傫�ȉe�����y�ڂ��Ă��܂��B����ɍR����킯�ł͂Ȃ�����ǁA���������吨�̗F�B�Ɛ��������ɂ��Ȃ���A�q�ǂ��������L���L�������\��Ō����̐��E�ŗV��ł���l�q�Ɂu���̂܂q�ǂ��̐��E��S�g�Ŋ����Ċy����ň���Ăق����v�Ɗ肢�܂��B
�@�@���N���c�菭�Ȃ��Ȃ�܂����B�����̑��}�ȂǁA�����͂��肪�Ƃ��������܂����B�Ђ����Ԃ�̍s�������̂Ȃ��N���N�n�ł����R���i�����g�傪�\�z����Ă��܂��B�ǂ������N�ɗ��ӂ��Ă��߂������������B
��11�����i2022�N11��1���j
�@�@�����͒g�����������ŐS�n�悭�߂����Ă��܂����A�S���߂��ɂȂ�Ƌ�C���₽���A�㒅�𒅂��ނ悤�ł��B
�@�@�C���̕ϓ��ɓ�������͕q���ŁA�����̎q�ǂ������M���o������A��������ƕ��Ǐ�𗈂��Ă��܂��B�R���i�������܂����X�ɑ����Ă��Ă��܂����A�C���t���G���U��RS�E�B���X�̏d���������뜜����Ă��܂��B�\�h�ڎ��o���邾���̊����\�h����Ƃ��āA���N�̓~���}���������̂ł��B
�@�@�X���ɂ͐e�q�U�������[�A�P�O���ɂ͐e�q�ŗV�ԉ�����{���܂����B���Q�����肪�Ƃ��������܂��B�R�N���̃R���i�E�B���X�����g����Ԃ͍P�Ⴞ�������s�����قƂ�ǒ��~�ƂȂ�A�v���Ԃ�̍s���̎��g�݂ł����B���S���S���P�Ƃ��Ă̎��{�ł������A���s�O����ݐЂ��Ă��������ɂƂ��Ă͕ύX�_�������A���s��ɓ������Ă��������ɂ͏��߂Ă̌o���ŁA�ǂ���ɂƂ��Ă��l�X�Ȋ��z��^�₪���������Ƃ��A����Ɏ��{�����A���P�[�g�̉��ʂ���ǂݎ��܂����B�i�s���A���P�[�g�W�v���ʂ����ǂ݂��������j
�@�@�R���i�����\�h��O��ɁA�q�ǂ������̕��i�̕ۈ炩��h���������e�\���ł��邱�ƁA�q�ǂ������ƕی�҂��y���߂邱�ƁA�ꏊ�̊m�ۂ����S�ł��邱�ƁA���O����̏�����ЂÂ�������ς����Ȃ����ƂȂǁA�����I�ɍl�����Ă̎��{�ł����B���N�x�͕ی�҂̋��͂̉��A���ꏏ�ɍl�����킹�Ď��s�ł���Ƃ����ł��ˁB�@
�@�@����̐��������X�Ɛi��ł��܂��B�傫�ȃA�X���`�b�N�����A���̔�Q�ɑ����A�C�U����ł̔�p�������ނ��Ƃ���v�����ēP�����܂����B�Ւn�͒z�R�ɃS���`�b�v�����Ԃ����u�Ђ悱�ӂ��v�A����������ɒn�ʂ��@���Ă��炢�A�^�C���߂Ă����������u�ǂ�ʂ܁v�i�����ƒf�̖����ł����j�A�������̂Ȃ邽��炮�݁A�䂷�炤�߁A�I���[�u�A�u���[�x���[�̃K�[�f�����ł��܂����B���уX�C�����ƃ��_�J�̃r�I�g�[�v�����N�g�p���ĉ�ꂩ�����v�[���𗘗p���ċ������ɒu���܂����B�v���̂ق��A�c�������łȂ���������_�ɗV��ł��܂��B����ɂ킭�킭�ƗV�т��߂����̂����я���߂����āA�V�ѐS���h������V���n��܂��B
��10�����i2022�N10��1���j
�@�@���ӐS�n�悢�C��ɂȂ�܂����B���������������炬�A�q�ǂ������͒��ԏ�≀��Œi�{�[���₨���C�}�b�g�ł��Ƃ��������A�����@�����肵�ėV��ł��܂��B�Ă̊Ԋy�����ݎ��͂܂����N�̂��y���݂ɂ���Ƃ��āA�����V�����V�ѕ��������Ă��܂��B�Q�O�N�ԁA�����Ղ�V�傫�ȃA�X���`�b�N�����A���̔�Q�ɑ����A�}篂V���ɓP�����܂������A�Ւn���v�������L�X���Ă��ď������q�ɂ��V�т₷���Ȃ����̂ňٔN��ł̊ւ�肪�������̂͗\�z�O�ł����B�ی�҂̕�������Ă����������^�C���͉���ŖڐV�����V��ƂȂ��ċP���Ă��܂��B�܂��܂����낢��ȗV�т��ł��鉀��Â���Ƀ`�������W�������ł��B�@�@
�@�@�q�ǂ������������ɂȂ��ėV�Ԏp���v�������ׂȂ���A�������|�����Ɏ�Ԃ��|���A�m�b���i���Ă��ꂱ��H�v���đn�����鉀��Â���͕ۈ�̑�햡�ł��B�q�ǂ��̂���쌴�𑖂����ėV���Ƃ�����A������������A�悢�A�C�f�A������܂������Ă��Ă���������Ɗ������ł��B
�@�@�P�O���P�Q������ߘa�T�N�x�̕ۈ珊�����\�����݂��J�n����ɂ�����A���̂Ƃ��댩�w�҂������Ă��܂��B�R���i�Ђ▢�����̏㏸�Ȃǂɂ�鏭�q���̋}���Ȑi�W�������āA���͈玙�x�Ƌ��t���x���͈͂̊g����������Ă��邻���ł��B���̂��߈玙�x�Ɩ����̂P�Ύ��̕ۈ珊������������������Ǝv���܂��B�O�Ύ���������育�ƒ�ʼn߂�����͖̂]�܂����Ƃ��āA�ݑ�̕�q�ɑ���q��Ďx��������ɋ��߂��邾�낤�Ǝv���܂��B�P�Ύ��͐��b���Ă���邨�ƂȂƂ̈����W���������߂鎞���ł�����A�P�Ύ��ł̓����������Ă����Ƃ�����A�ʂ����Č��݂̕ۈ�̐��ň��S���S�̕ۈ炪�ێ��ł��邩�Ɗ뜜���܂��B�P�Ύ�4�l���P�l�Œ����ԕۈ炷�邱�Ƃ��ǂ�قǑ�ςȂ��Ƃ��A���͕ۈ猻��̎����m���Ăق����Ǝv���܂��B�@
��9�����i2022�N9��1���j
�@�@�W���̓R���i������V�g����������A�w�Z���ċx�݊��Ԓ����������Ƃ������ēo������q�ǂ�����������܂����B����A�Ђ悱�ۈ牀�̐E���₻�̉Ƒ�����������P�[�X�������A�o�ł���E���̓V�t�g�̒����ɂĂ����₵�Ȃ���A�ҏ��̉Ăɒʂ��ė���q�ǂ������̑̒��Ǘ��ɖ�����ꂽ�P�����ł����B�@
�@�@���~�ŋA�Ȃ��邱�Ƃ��܂܂Ȃ�Ȃ��ł������A��������̂�Ȃ���q�ǂ������Ƃ����̋x�ɂ��y���܂ꂽ���Ƒ��������������Ƃł��傤�B�x�ݖ����̎q�ǂ������̈��肵���\�������Ă��܂��B
�@�@�I�����C���ł̏A�J�������ĒʋΎ��Ԃ��������Ƃ͂����A���{�̎q��Đ���͍��ۓI�Ɏ�v�ȍ��̒��ł͈玙��]�ɂ̎��Ԃ��ł����Ȃ��u���ԕn���v�̏ɂ���ƌ����Ă��܂��B���ɐ��Ј��̋��������т̂R�����\���Ȉ玙���Ԃ�]�ɂ��̂�Ȃ����Ƃ������Ƃł��B�܂��A���ɍȂ̕����v�������ԕn���Ɋׂ��Ă��������A����͕v�̉Ǝ��Q�������Ȃ����Ƃɑ傫�Ȍ���������Ƃ��Ă��܂��i���o�W���Q�P���L�ځj
�@�@���{�ł����e�̈玙�x�Ɏ擾�������Ɍ����n�߂Ă͂��܂����A�����͂Ȃ��Ȃ�����悤�ł��ˁB
�@�@���̃R���i�����j���p�ɂɕύX����钆�ŁA���l�s�̎��g�݂����X�ς��A���A�s���Ԃł̎��m
�@�@�O��E���L�s���������Đ��m�ȏ����ł����A�ۈ牀���ی�҂̕��ɂ��`��������e�ɂ��킩��ɂ����_�����X���������Ǝv���܂��B�����_�ł̓R���i�����ɔ������p��������v�Z���s���Ă���Ƃ���ł��B
�@�@�u�R���i�����҂Ŗ��Ǐ�̏ꍇ�͊������O�ꂷ�邱�ƂŊO�o��F�߂�B�܂��A�S���c�����_�c���ɕύX����v�Ƃ������{�̕��j���o���悤�ł����A�������NJ��ƌo�ς̒�̒��ł�ނȂ��Ȃ�����A�g�߂ɓ��c���⍂��҂��吨���闧�ꂩ��͕s���������܂��B���߂ďd�lj�������������Ȃ��悤�ɂƊ肢�܂��B
��8�����i2022�N8��1���j
�@�@���ATV�ŔM���ǎw�������āA�S������Ƃ��낪�Ԃ܂��̓I�����W�F�ɓh���Ă���̂ɂ��肵�Ȃ��������n�܂�܂����A�ۈ牀�ɗ��Ďq�ǂ������Ɂu���͂悤�v�ƌ����ƃG�l���M�[���V�̂Ƀ`���[�W����܂��B�@�@�@�@
�@�@���C�����ς��̎q�ǂ������ɁA���ɂ́u�g�z�z�v�Ǝv�킳��鎖�Ԃ��܂܂���܂����A�q�ǂ��������v���苃������A�吺�ŏ�����A���܂�����ł�����{�͕��a�ł��ˁB�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�ŋ߂̎����ɐڂ��āA������o�ς̐��E�ɂ͈�ʐl�ɂ͗����ł��Ȃ����G�ȕ�����\�ɂ͏o�Ȃ��s�����ȗ��̐��E������̂��낤�A�Ƃ������x�ɂ͊����Ȃ�����A�C�O�Ő�Ђ̒��ł��т���q�ǂ������̉f����ڂɂ��邽�сA���ƍ��̗��Q�̑Η��Ŗu������푈�Ƃ͍��̂Ƃ��닗����u���������{�����ɕ��a�ł���͓̂���Ȃ̂��Ƃ��炽�߂Ďv���܂��B
�@�@�q�ǂ������ɐ푈�̔ߎS�ɂ��ē`���鎞�A�K�v�ȏ�ɕ|���点�邱�Ƃ͂Ȃ�����ǁA���a�̑�Ȃ��Ƃ͔N����ɓ`���Ă��������Ǝv���܂��B����ŁA�ŋߍ����ł��т��є������Ă��鎖���A���ɎႢ�������������܂�鎖���̑�����SNS���֘A���Ă��邱�Ƃɕs�����o���܂��B�ۈ牀�̎q�ǂ������ɂƂ��Ă̓p�\�R����X�}�z�͐��܂ꂽ������g�߂ł�����A�c���Ă������Ɋ���Ă���悤�ŁA���܂܂��Ƃ��Ȃ�����ςݖ̃X�}�z�Ў�ɑ�l�畉���̉�b�����Ă���l�q�Ɋ��S���܂��B���͔��܂������Ă��܂������������傫���Ȃ��Ĉ�l�ōs������N��ɂȂ������ɁA�Ԉ�����g���������Ȃ����ƁA�����̐S�Ƒ̂���邱�Ƃ�`���Ă������Ƃ��A�푈���N�����Ȃ��S�Ɨ�������Ă�̂Ɠ������炢�K�v���Ǝv���܂��B
�@�@�t�ɗV�������̉Ԓd�Ɏ�܂������q�}�������̂т̂тƂ������킢���Ԃ��炩���Ă��܂��B�����Ɏ�܂������R�X���X�͂܂���ւ����ł����A�ԃg���{�̔�Ԃ���ɍ炭���Ƃł��傤�B�y���݂ł��B
�@�@�ҏ��̉āA�R���i�����g��̉āA�M���ǂȂnj��������Ƃ���������ł����A�ċx�݂��Ƃ邲�ƒ�����邱�Ƃł��傤�B�̒��𐮂��Ċy�����߂����Ă��������ˁB�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
��7�����i2022�N7��1���j
�@�@���X�Ɣ~�J�������܂����B�ϑ��j��ł����������ł��B�A��35���z���ǂ��납40�������Ƃ��������Ƃ�����������ł��B�����炶�肶��ƏƂ�t���鑾�z�ɂ���ł����A�q�ǂ������͕ۈ牀�ŗF�B�ɉ�Ǝ���Ƀe���V�����A�b�v���Č��C�����ς��ł��B���܂߂Ȑ����⋋�ƃG�A�R���̓K���Ȏg�p�ŔM���ǂ̊댯������ĉ߂����Ă��܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�{���̓v�[���J���ł����B���V�шȊO�ɂ��̏����̒��A���C�����B�̃p���[�̔��U�͎v�����܂��A�畆������a�C�Ńv�[���ɓ���Ȃ��͎̂c�O�ł��ˁB�������N�f�f�Ŏw�E���Ȃ���܂���f���Ă��Ȃ����q����͑��₩�Ɏ��Â��܂��傤�B�܂��A�v�[���ۈ�\�����ɋL�ڂ��Ȃ��Ɩ{�l�͌��C�ł��v�[���ɂ͓�����Ȃ��̂ł����Ǝc�O�ł��B���q����̎��含�d����̂͑厖�ł����A�ی�҂̕��͔w��Ő����ȂǓo���x�x�̎菕�������Ă������������ł�
�@�@�U���������łɘA���̏����ŁA���ɊO�ɏo��ɂ��E�C������قǂł������A����ł͑����A�D�̊C���o�����܂����B�G���g�����X�̃��j�^�[�Ō��Ă����������ʂ�A����Ԃ���Ԓr��A�z�R�A�A�X���`�b�N�Ŏv�������͂��Ⴌ�A�D���𗁂тċ������悤�ɗV��ŁA�X�g���X���U�I�q�ǂ����Ċ��ꂽ�Ƃ���ł͂���Ȃɑ�_�ɗV�ׂ�ȂƁA���߂Ďv���܂����B������ςł����A��낵�����肢���܂��B���Ȃ݂ɓD����͐���Ă����ʂ�ɂȂ�Ȃ��̂ŁA����Ă��悢�������p�ӂ��������B�@
�@�@����̃P���L�̏����V�Ɍ������ė͋����L�тĖL���ɗt��点�A�q�ǂ������̓���ɖ؉A������Ă���Ă���̂����Ȃ���A�n�݈ȗ��Q�O�N�Ƃ������������ꂽ���Ƃ��������Ă��܂��B���F�ۈ珊����������̕ی�҂̂��s�͂Ŋ������̃P���L��A���Ă����������̂ł����A�����͊����ׂ�������܂�Ƃ��Ă����̂ł��B���ł͂Ђ悱�ۈ牀�̃V���{���c���[�Ƃ��ē��X�����Ɉ���Ă��܂��B
�@�@�R���i�����͂��߁A�������Q�O���N�L�O�s���͍��̂Ƃ�����{���Ȃ�����ł����A�V�������Ă��鉀��V���ݔ��̓_���E�C�U�ɂ��ẮA�Q�O�N�̐ߖڂƂ��ď��X�ɍs���ׂ��������Ă��܂��B
�@�@�Ђ悱�ۈ牀�ł̂т̂тƎq�ǂ����m���ւ�荇�����S��ۏႳ��āA��Q�̂��ƂƂ��Ĉ��S���ĉ߂�����悤�ɔz�����Ă������ƁB���ƂȂ̎���ő吨�̎q�ǂ������������Ԉꏏ�ɉ߂�������Ȃ��ۈ�̌���ł͂��ꂪ�ł����߂��邱�ƂƎv���Ă��܂��B
��6�����i2022�N6��1���j
�@�@�^�Ă̂悤�ȏ����ƂЂ���J�̓������݂ɗ���̂ŁA���镞�ɖ��������ł��B�����̃~�[�e�B���O�ł͓V�C�\��ƔM���ǎw���̊m�F���s���Ă��܂����A�~�J������߂Â��ۈ�̐i�ߕ������ʂƂȂ�܂��ˁB���̎��̂̕��p�ɂɏo�n�߂鎞���ƂȂ�A�C���A�v�[���ł̗V�т͗v���ӂł��B�c���q�ǂ������Ƃ̕�炵�́A���ł����S��̐��肪��ł��B
�@�@�T���̓R���i�E�B���X�����������Ŕ����������߁A�s���̎w���ɂ��ꕔ�x���̑[�u����点�Ă��������܂����B�F����ɂ͑���Ȃ����S�����������Đ\����܂���B�����_�ł͔����͂���܂��@
�C�͋����܂���B��������C�A���łȂǏo�������̊�������̂��Ă����܂��̂ŁA���ƒ�ł���A�����Ȃǂ����͂����肢���܂��B
�@�@�R���i�E�B���X���������E�I�Ɋg�U���āA�o�ρA�Y�Ƃ��傫���ω����Ă������ŁA�E�N���C�i�ւ̌R���N�U���������𑝂��Ă��܂��B������헐�������l���ɁA�����đ吨�̎q�ǂ������̔ߎS�ȏ̕ɕی�҂̊F���������ɂ߂Ă����邱�ƂƎv���܂��B���E���ɕp������s�K�ɋ���������Ȃ�����A���g�̃����^���͌��N�I�Ɉێ����Ă����w�͂��������鎞��́A���X�̕�炵�̒��ł̏����Ȋy���݂����āA������������Ƃ���Ȃ̂��Ǝv���Ă��܂��B���͒ʋ̎ԓ��ʼnf��̃e�[�}�~���[�W�b�N�̂b�c���̂��y���݂ɂ��Ă��܂����A���̂���S��h���Ԃ���Ȃ́u�Ђ܂��v�ł��B�@
�@�@�P�X�V�O�N�ɍ쐬���ꂽ�C�^���A�f��̃e�[�}�~���[�W�b�N�ŁA�ƂĂ��������S�ɐ��ݓ�������ł��B�u�Ђ܂��v�͑�Q�����E��풆�̃��V�A�ƃC�^���A�ɂ܂��f��ł����A���݂ɏd�Ȃ�e�[�}���Ɗ����܂��B�����ɋN���Ă���E�N���C�i�̐�Ђ̉����ƕ��a������ĉԒd�Ƀq�}�����̎���܂��܂����B
��5�����i2022�N5��2���j
�@�@�T���́u�܌�����v�Ƃ������t������悤�ɁA���ǂ��̓��A�����̂ڂ�A����������ȂǁA��͐����X�͎�t���G���Ēg�����̂ǂ��ȓ����v�������ׂ܂��B�ł����A���N�͘A�x��ڑO�ɂ����k�C���̊C��̂�E�N���C�i�̐�ЂȂǁA�c���q�ǂ��������]���ɂȂ��Ă���j���[�X�������A�����ɂ݂܂��B�@�@�@�@
�@�@�Ђ悱�ۈ牀�ɒʂ��Ă��Ă��铯�����炢�̔N��̎q�ǂ������͖����A�ڂ����ς��ɂ��邪�܂܂̎������o���Ȃ�������������ɐ������Ă���̂ɁA�����m��Ȃ����ɑO�r��ˑR�f���ꂽ�q�ǂ������́A�s�^�Ƃ��s�𗝂Ƃ��̌��t�ł͕ЂÂ����Ȃ��A�����Ɛ[���߂��݂̒��ɂ��܂��B�e�ɂƂ��Ă��q�ǂ��������Ƃ������Ƃ́A���Ƃ��悤�̂Ȃ��߂��݂Ƌꂵ�݂Ȃ̂��낤�Ǝv���Ƃ��A�푈�̂Ȃ����E�����邱�Ƃ͂������ł����A����̕ۈ璆�ł̎��̂ɂ��Ă͐�ɋN�����܂��ƋC���������܂�܂��B
�@�@�V�N�x�ɂȂ��Ă���P���������A�V�����������X�Ɋ���Ă��܂����B�͂��߂͖ڂ̑O�ɗp�ӂ���Ă��Ă���ŕ����قǂɋ��₵�Ă������H���A���ł͎�����L���ĐH�ׂ���悤�ɂȂ��Ă��܂��B�u�������v�̐����������܂��B�H�ו������������Ɗ����Ȃ�����ɂ��A�����̒��ɓ���邱�Ƃɂ���āA�S������������S�����C�����ɂȂ�܂��B�������苋�H�����ׁA�������Ɩ���A�p���[�������āA�[���A�͂���������Ɍ��C�Ȏp�͂��}���̎��ɖڂɂ����ʂ�ł��B�q�ǂ����吨�W�����ł́A�������Ȃ��Ɓi���ƂȂ��猩��ł����j�ł̂���厖�Ɏ���Ȃ�������o�����Ȃ�����A�ۈ牀�ɒʂ��q�ǂ������͍K�����Ȃ��Ɩ��������Ă��܂��B�q�ǂ������͖{�C�ɂȂ��Ď���g�ݍ����̂������Ă��A���炭���ċC���������������A�����Ȃ����݂���������������A�u���߂�ˁv���������肵�Ă��܂��B
�@�@���ܐ��E�ŋN���Ă���푈�́A�͂̋������̏����Ƃ���ɁA�l�Ƃ��Ă̗ǐS�̂�������������Ȃ��A�Ȃ�Ƃ����낵�����Ԃł��B�l�Ԃ̕��̖ʂ̍ł���Ƃ��낪�I�悵�Ă��܂��B����ǂ̂悤�ɂȂ��Ă����̂��A���̎s���Ƃ��Ă͊뜜���Ȃ��疈���̕�炵�̒��ŏ����ȕ��a���ێ����ׂ��w�߂Ă��܂��B
�@�@���A���E���Ɉ��S�ɏZ�މƂ̂Ȃ��A�Q���ɋꂵ�ގq�ǂ��������吨���܂��B���E�ŋN���鎖�ۂ̊������A�������͐l���܂��܂ł����A�Q�����q�ǂ������ɏ����ł��H�ו����킯�Ă�����ꂽ��A����͎������̏����ȍK���ɂȂ���悤�Ɏv���܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
��4�����i2022�N4��1���j
�@�@�����E�i�����߂łƂ��������܂��B��N��葁�����̊J�Ԑ錾���o�����N�ł����A���J�̉Ԑ����ڂɂ��Ȃ���{���A�������j����s���܂����B���N�x�͐V���ɂP�X���̉������}���܂��B�����������̂ł��炭�͌��C�����ς��̋����������ɂɋ����n��܂��B����ł��T���̘A�x���߂��邱��ɂ͂����Ԋ���ĕۈ�҂Ƃ̈����W���o�n�߂Ă��邨�q����̕\��̕ω��ɁA�ی�҂̊F������ق��Ƃ��邱��ł��B�S�����͗c���N���X�ł��ω��ւ̕s���̗��Ԃ��Ŗ��Ƀe���V��������������A�͂��Ⴂ���肵�Ĕ�ꂪ���ł��̂ŁA���q����Ɋ��Y���Ȃ���߂����Ă��������Ɨǂ��悤�ł��B
�@�@�R���i�Ђ̒��ʼn߂����đ��Q�N���������܂����B���܂œ�����O�̂悤�ɍs���Ă�������̕ۈ��s�����������Ȃ���s�x�A�����ɂ��Ă������A�Ђ悱�ۈ牀�炵�����@�͉����A�E���Ԃł��т��јb�������Ȃ��炱�̊Ԑi�߂Ă��܂������A�ی�҂̊F����ɂƂ��Ă͂������ł������B
�@�@�ۈ�͕ۈ牀���哱�Ői�߂�̂łȂ��A�ی�҂̕��Ƃ̋����Ŏq�ǂ������́u���Ɩ����̂��߁v�ɂ��ǂ��ۈ��͍����Ă�����ł��B�����荡���A�����Ė����������ł��q�ǂ������̔��B�Ɛ����Ɏ�����悤�ɁA�܂��A�ی�҂̊F����̏A�J�x�������s���Ȃ���A�݂�Ȃ����S���ĕ�点�鋏�ꏊ�ƂȂ�ׂ�
�^�c���Ă܂���܂��B���ݓI�Ȃ��ӌ�������������ƍK���ł��B
��3�����i2022�N3��1���j
�@�@�u������Q���A����R���v�̌��t�ʂ�A�V�^�R���i�E�B���X�Ή��ɒǂ��ĉ߂������Q�O�Q�P�N�x�ł����B�C�Â��Α��R���A�N�x���ł��B���N�ȗ��傫�ȍs���͎��{�����A���̂Q�N�Ԃ͂Ђ悱�ۈ牀�̗��j�̒��ł�����ł������A�q�ǂ������͑�l�̎v���ς�����͎��R�ɁA���������Ȃ�̊y���ݕ���T���Ă����悤�ł��B�����A�i�����T�������A���ꂼ��̎������ł�����������Ă���Ȃ��Ɗ����܂��B
�@�@�S���I�ɁA�܂����l�s�ł��R���i�E�B���X�����g��ŋx���E�x�Z�ɂȂ��Ă���ۈ牀�E�w�Z�����o���Ă��܂��B�Ђ悱�ۈ牀�ł͂܂��A�����x���ɂ͎����Ă��܂��A�ߗׂ̕ۈ牀�ŋx�����������钆�A����̉^�c����łǂ̂悤�ɂȂ邩���ʂ��������܂���B�p�[�g�̐E�������������肷��A�h�A�m�u�ȂǏ��ł����܂߂ɂ��Ă��ꂽ��A���C�ɂ��S�����ė\�h�Ă��܂��B���ƒ�ł��R���ɂȂ�悤�ȏ�����A��A�������A�}�X�N���s���Ă��������A�݂�ȂŌ��C�ɐV�w�����}�������ł��ˁB
�@�@�C�O�ł̓��V�A�̃E�N���C�i�N�U�ɂ���Ђɂ��āA�e���e�l�Ɏ��グ�Ă��܂��BTV��ʂ̉f���ɂ̓I�����s�b�N�C���̗�߂���Ȃ������ɁA�z�����ɂ��Ȃ������S��Ƌ��|�ƔߒQ�ɂ�����ʎs����q�ǂ��̎p���f���o����āA�̂�т萶�����Ă��鎄�����Ƃ̃M���b�v�̑傫���ɋ����ɂ݂܂��B
�@�@���V�A�ȊO�ɂ��V���A�A�A�t�K�j�X�^���Ȃǐ�ꂽ����吨���݂��Đ��������܂���Ă��鎖��������܂��B���{�ł͍��̂Ƃ��땽�a�Ȑ���������Ă��܂����A���ɂ͂������Ȃ�����Ă��܂����Ƃ�����Ǝv���܂��B�傫���͍��ƊԂ̐푈��p���f�~�b�N�ƂȂ����V�^�R���i�E�B���X�����A�������͐g�߂Ȑl�ԊW�ȂǁA���ł����S�ɕۏႳ��邱�Ƃł͂Ȃ��̂��Ǝv���܂��B���ł��u���ʃI�[���C�v�ɂȂ�Ƃ������S���̃o�C�A�X�ɂ������Ă��Ȃ����A���͐T�d�ɐT�d���d�˂ĐU��Ԃ鎞�ł��B
�@�@�傫�Ȏ��̂Ȃ����N�x���I�����邱�Ƃ�S�������Ă��܂��B�����͂��肪�Ƃ��������܂��B
��2�����i2022�N2��1���j
�@�@�����ł̓I�~�N�������̋}���Ȋ����g��A�p�����鎖�̂�ƍ߁A�C�O�ł̓A�t�K�j�X�^���̎S���E�N���C�i������卑�Ԃ̑Η��ȂǁA�ڂ��Ԃ莨���ӂ��������Ȃ�j���[�X�ɋC������Ă��邤���A�����Ƃ����Ԃɉ߂����P���ł����B�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@��N�̂��ƂȂ���Q���͑������T���������炮�݂̎q�ǂ������ɁA�Ђ悱�ۈ牀�ł̍Ō�̂Q�������v���o�L���ɉ߂����Ă��炢�����ƋC�z�肵�Ȃ���A����ŐV�N�x�̑̐��Â���ɒǂ��ĉ߂����܂��B
�@�@�P���X���ɊJ�Â����S�̐E����c�ł͂S�T���S���̏o�Ȃʼn��l�s�̕ۈ���Ђ悱�ۈ牀�̌���ɂ��Ċm�F���܂����B�G���g�����X�Ɍf�����܂������u�q�ǂ��Ƃ��čK��♡�Ɗ������u�ԁv�A�u����ȕۈ牀�������炢���ȁI�v�Ƃ̂Q�̃e�[�}�Řa�C���������ƃO���[�v���[�N���܂����B�Z���ԋΖ��A���K�A�E��Ɋւ�炸���R�̂Řb�����������u�݂�Ȃ̂������Ȃ������v�ł���ۈ牀�̓y��ƂȂ�ƁA�R���i�����h�~�̂��߉������Ă����S�E���Ԃł̘b����������ł��邱�Ƃ��Ċm�F���܂����B
�@�@���l�s�͑ҋ@�����������A�����ۈ牀�̖��Ԉϑ���V�݉��̊J���Ȃǂ��v��E�����������ŁA�F�ۈ牀�̔����ȏ�Œ�����ꂪ�N���Ă���悤�ł��B���ɂЂ悱�ۈ牀�������ł����O�Ύ��̓������������Ă���A�ً}�I�ɂP�E�Q�Ύ��ɓ��������ۈ牀���K�v�Ƃ���Ă��܂��B�R���i�E�B���X�����̕s������玙�x�Ƃ���������A�ݑ�ł̃e�����[�N�ȂǓ���������������Ƃ݂��Ă��܂��B�ۈ牀�s���A�ۈ�m�s��������ċv�����ł����A������E���q���E�l������������ɐi�݁A�߂������ɕۈ�m�s�������������Ƃ����\�������钆�ŁA�Ђ悱�ۈ牀���ǂ̂悤�ɉ^�c���Ă����悢���l�����ł��B
��1�����i2022�N1��4���j
�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��B
�@�@�Z���ڐG�҂�N���X�^�[�Ƃ������t���o�n�߂���N���A2�N�Ԃ�ɋA�Ȃ��Ă���������������ɑ��̊�����������ƌv�悵�Ă������Ƒ��͊�]�����Ȃ����ł��傤���B�s�u�j���[�X�ŁA�w�ŏo�}�����c����Ƒ��Ƃ̂��ꂵ�����ȍĉ��ʂ����邽�сA�ق��Ƃ����C�����ɂȂ�܂����B�Ƒ��̋C�z���v�����ɕ�܂�Ĉ�q�ǂ��͍K���ł��ˁB�����͗���Ă��Ă��N���Ɍ�����Ă�����S�����y��ɗL���ē����͕ۈ牀��w�Z�Ő��i��C���̈قȂ�F�����ƌ����A�����ŗV�肯������A���X�l�X�Ȍo�������Ȃ��琬�����Ă��܂��B
�@�@�V���ȂǂŁu�g�\���v�Ƃ������t��ڂɂ���悤�ɂȂ�܂����B�V�h�̕��꒬�́u�V�h����r���v�����̘H��̎��ʼnƏo�Ȃǂ���10��̏��N�������[��ɂ��ނ낷��ꏊ�Ƃ��Ē蒅���Ă��邻���ł��B���ł́u�O�����v�A���l�ł́u�r�u���v�ȂNJe�n�ɓ����悤�ȏꏊ���o���Ă��āA�ƒ��w�Z�����ꏊ�Ƃ��Ċ������Ȃ��q�ǂ��������ꏏ�ɂ��Ĉ��S�ł��钇�Ԃ����߂Ċe�n����W�܂��Ă��邻���ł��B�܂��A�������܂̉ߏ�ێ�Ȃǂ��݂��A�ƍ߂⎖���Ɋ������܂��P�[�X�������ƋL�ڂ���Ă��܂��B
�@�@�����w�Z�ł͕s�o�Z��w�Z�������N�X�������Ă��āA�����s��������ʂȎx���̕K�v�Ȏq�ǂ��ւ̑Ή����ǂ��t���Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ�����A�q�ǂ������ɂƂ��Ĉ��S���Đ������A�w�ԂƂ�����{�I�ɑ�Ȏ����w�͂Ő��E�ɒǂ��t�����Ƃ��鐭��̒��ŕK�������ۏႳ��Ă͂��Ȃ����ʂ��I�悵�Ă��Ă���悤�ł��B
�@�@�R���i�E�B���X�����̕s�������N�ɂ킽���đ����A�����l�����傫���ς�邱�Ƃ�]�V�Ȃ��������A�Ζʂł͂Ȃ��w�т�}���ɓ��������h�b�s�ȂǁA��l�������Q���������������Ă��钆�ŁA�������ǂ�����ƈ��芴�̂�����퐶���ł͂Ȃ��̂ł��傤�B�q�ǂ����������S���ĐL�т₩�Ɉ������ۏႷ�邱�Ƃ́A�ۈ牀�̐E���ł���`���ł�����A�吨�̕ۈ�҂̌��ɂ��ۈ���@���قȂ��Ă����̈Ⴂ���������Ȃ���A���Ђ悱�ۈ牀�ŏo���邱�Ƃ͉����A�����̕ω��ɂ��ڂ������ی�҂̕��X�̂��ӌ������������Ȃ���i�߂Ă��������Ǝv���܂��B�ۈ�҂ɂƂ��Ďq�ǂ������̏Ί炪����肤�ꂵ���ł��B�u�܂��A�������������ڂ��ˁI�v�̐��ɋ~���Ă��܂��B�@�܂��܂��A�R���i�E�B���X�̕s���͑����܂����A�ی�҂̊F����̂����͂̉��A���z���Ă��������Ǝv���܂��B���N����낵�����肢�v���܂��B
��12�����i2021�N12��1���j
�@�@��T�Q�U���i���j�ɂ҂�҂悮�݂̍��k��J�Â���܂����B���N�x�͂قƂ�ǂ̍s�������~�ƂȂ����̂ŁA�v���Ԃ�ɕی�҂̕��X�̘a�₩�ȍ��k�̗l�q���܂����Ō����A�ȑO�̂悤�ɋ����Ȃ����킪�߂��Ăق����ȂƂ��炽�߂Ďv���܂����B����̓R���i�E�B���X�����h�~�̊ϓ_����P�N���X���ɕ����Ă̊J�ÂŁA�Z��Œʂ��Ă��邲�ƒ�ɂ͉��x���Ζ��ނ��ꂽ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����A�I�����̍��G���ɘa����Ă悩�������ȂƎv���܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�ً}���Ԑ錾����������Ĉȗ��A�o�ς̕����A�����g��h�~�����荬�����Č���܂����A�ǂ�����������邤���ő�ł��ˁB��ÁA���A�ۈ�Ɍg���l�̏������P�A�����A�b�v�ɂ��Ă͂��肪�����Ǝv������A���Ƃ�|�Y�Ȃnj������ɒu����Ă�����X���吨���钆�ŁA��ÁA���A�ۈ�]���҂͐E�������Ƃ����s���͂Ȃ��A�����ǂ��Ȃ���������͌���ێ��ł��Ă��邱�ƂɊ��ӂ��Ă��܂��B
�@�@���N�����ƈꌎ�ƂȂ�܂����B�R���i�Ή��Ɏ��ԂƐS��D���Ă��邤���ɁA�����Ƃ����ԂɔN�����}�����C�����܂��B�Ђ悱�ۈ牀�Ɋւ�钆�ŕی�҂̊F�l�ɂ����낢��Ȏv��������Ƃ͎v���܂����A�q�ǂ����������S���Ă��y�����߂�����悤�ɑO�����ɘb�������Ȃ���߂����Ă�����Ƃ����ł��ˁB
�@�@��������������������ēy���k���Ă����������D�c�q�R�[�i�[�ŁA�������q�ǂ�������������ēD�c�q���ɗ��ł��܂��B���ɓ�����|�����Ă����������������ŋ�C������₩�ȋC�����܂��B���肪�Ƃ��������܂����B
��11�����i2021�N11��1���j
�@�@�A���A�S���̃R���i�E�B���X�����Ґ����������Ă��܂��܂ȋK�����������ɂ�A�J�ł̊y���C�Ȉ��H�A������ʂ�TV��ʂɗ�����Ă��܂��B�ǂ̐l�������Ԃ̍S������������Ă̂т̂т������[�h���Y���Ă��܂����A�^�K���O�ꂽ�悤�ɐl���������邱�Ƃő�U�g�����g��ɂȂ炸�ɂ��̂܂I���Ɍ������Ăق����ł��B
�@�@�E�B�Y�R���i�A�A�t�^�[�R���i�Ƃ������t������āA���܂ł̂悤�ɐl���Ζʂ�����ڐG�����肷��@����ׂĂ̎��ۂ��猸�炳��āA�f�W�^�����̗��ꂪ�}��������Ă����̂ł��傤�B�i�a���l�Ԃɂ͐h���ł��B�j
�@�@���̊ԁA���w�Z�ł��I�����C�����Ƃ���������A���l�s�ł̓��C���m�[�g��S�s���Z�ł����悤�ɂȂ�܂����B���E���w�Z����͎��X�ƕی�҂̃X�}�z�ɘA��������A�A�J���Ă���e�ɂƂ��Ă͕֗��ł���A���킵�Ȃ�������̂悤�ł��B�q�ǂ������͐��܂ꂽ�Ƃ�����X�}�z��p�\�R�����g�߂ł��̂ŁA�\���Ȃ��Ƃ����ƂȂ����삪�ł���悤�ł����A�����ɔƍ߂߂������ƂɊ������܂��@���������Ƃ������ƂŁA���ƂȂ����͎q�ǂ������Ƌ��Ɍ��S�ȃX�}�z��p�\�R���̗��p�ɂ��Ċw�Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���ˁB
�@�@�ۈ牀�͖����吨�̎q�ǂ��������o�����āA�����ԑ؍݂���ꏊ�ł��B�ۈ�m�͎��Ȏ咣����q�ǂ������������Ȃ��V�Ԏ��ɂ��傯�����Ȃ��悤�ɁA�����O�Ō��������Ƃ��Ȃ��悤�ɁA�ӂ����ĐH�ׂČ뚋���Ȃ��悤�ɂȂǁA�₦���C�z��ڔz�肵�ĉ߂����̂ŎႢ�ۈ�m�ł��[���ɂ͐S�g�����������ł��B�܂��A�����̕ۈ牀�⏬�w�Z�̐E���̊ԂŁA���J�ȑΉ��̕K�v�Ȏq�ǂ��Ɖƒ낪�����Ă��邽�ߋƖ����ԈȊO�ɂ����C�⎩�Ȍ��r�Ɏ��Ԃ��₵�Ă���Ƙb����Ă��܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@���ԊO�ɘj�钷���ԘJ���A������A�ی�ґΉ��ȂǘJ�������������Ƃ������]�ɕۈ�m�̂Ȃ�肪�Ȃ��A�ۈ�m�̑��D��ɂȂ��Ă���ɉ��l�s����͕ۈ�m�̋Ɩ����S�̌y����}�邽�߂�ICT���V�X�e�������̕⏕�����x������邱�ƂɂȂ�܂����B�Ђ悱�ۈ牀�ł͍��܂ŘA���[�ł̊m�F���v�Z�ł������o���A�~���̊Ǘ�����萳�m�A�ȕ։����邽�߂ɃG���g�����X�Ƀ^�u���b�g��ݒu���邱�Ƃɂ��܂����B���X�ɖ����Ȃ���������鎖���瓱�����Ă����܂��B�ی�҂̊F����ɂ͂��Z�������ł�����|�������̏�A�����͂����肢�������܂��B
��10�����i2021�N10��1���j
�@�@�ً}���Ԑ錾�����A�����}���ّI�A�䕗�P�U���Ɩ����ɂ��Ƃ܂��Ȃ����̍��ł��B�X�����͓o�����l�̗v���ɂ������Ă��x�݂��Ă��鉀�������āA��N�ɔ�ׂĐÂ��ł����B�P�O���݂͂�Ȍ��C�ɖ߂��Ă��āA���₩�ȏH�ɂȂ��Ă���C�z�ł��B�s���������ɘa����邱�Ƃɂ���čĂуR���i�E�B���X�����҂��������邱�Ƃ��Ȃ��悤�ɁA�g�߂ŏo���邱�Ƃ������������Ă����܂��傤�B
�@�@�P�O���P�Q������ߘa�S�N�x�̕ۈ珊�����\�����݂��n�܂邽�߁A���̂Ƃ���ۈ牀�̌��w�҂������������Ă��܂��B�������ē����Ă���ƁA�q�ǂ�����������Ă��Č��X�Ɂu����̃}�}�H�v���u�����ɗ����́H�v�ȂǂƐq�˂�̂Ō��w�҂���́u���C�ł��ˁv�A�u�̂т̂т��Ă��܂��ˁv�ƌ����܂��B
�@�@�Ђ悱�ۈ牀�̎q�ǂ������́A�u�݂�Ȃ̑傫�Ȃ��Ɓv��̌����邩�̂悤�ɓ����̂��炵�̎�l���Ƃ��Ď��Ԃ��߂����Ă��āA�]���܂���ď��Ă����A�����đ吺�ŋ����Ă����A�ǂ̊�����Ă��{���Ɏq�ǂ��炵���ȁA�Ǝv���܂��B
�@�@�s�}��ɂ͗l�X�Ȍo�c��̂̕ۈ牀������A���ꂼ��ɌŗL�̕ۈ痝�O�ʼn^�c���Ă��܂����A�Ђ悱�ۈ牀�̓y��́u�c�N�������Ԃ�炵�����炶������ƈ���Ăق����v�Ƃ����肢�ɂ��܂��B�ł����猩�w�҂ɂ́A��������ꂸ�Ɂu��Ăɋ����āA�F�������悤�ɂł��邱�Ɓv��u������w�K�v���d�����Ă��Ȃ��Ƙb���Ă��܂��B�[���͎q�ǂ������̕\���ǂݎ���Ăق����Ɗ���Ă̂��Ƃł��B
�@�@�ۈ牀�͂��������������ƁA�~�X�}�b�`�������Ă��s���������Ȃ��璷�����Ԃ��߂������ƂɂȂ�̂ŁA���ƒ�̕��j�ɂ������ۈ�A�ۈ牀��I��łق����ȂƎv���Ȃ���Ή����Ă��܂��B
��9�����i2021�N9��1���j
�@�@�@���{�ɂ��ً}���Ԑ錾���ߋy�щ����Ƃ�����펖�Ԃ̑����ŁA���X�A�����Ȏq�ǂ�����ĂȂ��瓭�����Ƃ��ǂ�Ȃɑ�ςȂ��Ƃ��Ƃ��@�����Ă��܂��B�W���̓R���i�E�B���X�����g��Ƌ��ɁA�I�����s�b�N��p�������s�b�N�Ƃ������ۓI�ȑ��̊J�Â̐���������Č��X���X�i���������E�����̐l�����₩�܂��������l�q�j�ł����B
�@�@�@�ۈ牀�̎q�ǂ������́u�y���ށv�Ƃ������_����͗�N�ƕς��Ȃ��Ă��߂������Ǝv���܂����A�ی�҂̊F����ɂƂ��Ă͂������ł������B�Ƒ����s����Ƃւ̋A�Ȃ��ł����A�q�ǂ��������D�ޗV���n�⓮�����A�����قȂǂ��吨�̐l���W�܂��Ė��ɂȂ�̂��|���čs���Ȃ��ȂǁA�C�x���g�Ƃ��Ă͕�����Ȃ�������������������܂���ˁB
�@�@�@�Q�R���A�H���̓��ɗ\�肵�Ă����e�q���������~���邱�Ƃɂ��܂����B�y���݂ɂ��Ă������ɂ͎c�O�ł����A��������������Ă������������v���܂��B�Ђ悱�ۈ牀�ł͒��A�[�ɊK�i�肷��⏰�A�I�A���̎V�ȂǏ��ł����Ă��܂����A����ł����̕ۈ牀�ŃN���X�^�[�����������A�x���ɂȂ����A�Ƃ̏��ɐG���ɂ��A�ĂтЂ悱�ۈ牀�ŋN������ƁA�s���͐@���܂���B���l�s�����ۈ牀�E���ǂ����������HP�ɂ��ƁA�W���ɂ͉��l�s���ł͂P�O�O���߂����x���̗J���ڂ����������ł��B
�@�@�@�R���i�Ђ̕ۈ�ł́A���܂Œʂ�ɂ͂ł��Ȃ�����ǔ��ʂŎq�ǂ�������L�т䂭��̂Ƃ��Č����Ƃ��A��l���}���ĉ��������Ƃ��A���Ȃ����Ƃ��łȂ��A���͂̂�������Ǝq�ǂ�������A�ǂ��������������A������������������厖���ȂƍĔF�������ʂ�����܂��B�Ђ悱�ۈ牀�͂��Ƃ��ƁA��l�����V���Ă��Ďq�ǂ��ɒ���ۈ�ł͂Ȃ��̂ł����A���܂���Ȃ��琷���R�ł͂Ȃ��A�]�v�Ȃ��̂₱�Ƃ��������Ƃ��ۈ���������̂��ȁA�Ǝv���Ă��܂��B
�@�@�@�ی�҂̊F������e�����[�N��]�V�Ȃ�������Ȃ��ŁA�ꏊ�̊m�ۂ��܂܂Ȃ�Ȃ����ƒ�����邩�Ǝv���܂��B�����l�ł��B�ی�҂̕��X�̋ꋫ�ɋ������Ȃ���A�܂��A�ۈ牀�������̎q�ǂ��̏W�܂�ꏊ�ł�����ꐫ���l�����킹�Ȃ���A���݂��ɋ�����b�Ƃ��āA���̍�������肽���Ǝv���Ă��܂��B
��8�����i2021�N8��1���j
�@�@�O���̂Ђ悱�����̂���ɂ́A�܂��A���N�`���̌��ʂŊ����������ł����܂��Ă����A�Ƃ������Ҋ����������̂ł����A�I�����s�b�N���n�܂��ĂP�T�ԁA���������̊肢���� ���ӂ����ǂ��납�A���܂łɂȂ��قǂ̋}���Ȋ����g��A�ً}���Ԑ錾�̗J���ڂ����鎖�Ԃɓ˓����Ă��܂��B�Ђ悱�ۈ牀���ӂł��A�c�t���A�ۈ牀�A�����w�Z�A����҂̎{�݂Ȃ� ������Ƃ���Ŋ����҂��o�Ă���悤�ł����A���Ǐ�̐l�������炵���̂ŁA�Ȃ�����ɕs���ł��ˁB
�@�@��ʐl�Ƃ��Ă͎�A���ŁA�l���݂������A�s�v�s�}�̊O�o�����Ȃ��ȂǁA����ɓO�ꂵ�Ă��������Ȃ��Ɖ��߂ċC���������߂Ă��܂��B
�@�@�I�����s�b�N�ł͂��ꂼ��̍��̑I�肽���̌�������p�͊����I�ŁA�v�킸TV�ɂ����t���ɂȂ��Ă��܂��܂����A�R���i�ЂƂ�����펖�Ԃ̑����ɁA�ꕔ�̐l�����Ղ葛���ɂȂ��� �͂��Ⴂ�łЂキ���A�I�����s�b�N�̐S����������A�₩�ȍՓT�̉A�ŋꋫ�ɒǂ����܂�čs���l�X���吨���邱�Ƃ�z���Ƃ��ɁA�J�Âɕs����������l�̑������ł̊J�� ���u���ʃI�[���C�v�ƌ�����Ƃ͎v���܂���B
�@�@�Ђ悱�ۈ牀�͎q�ǂ������̖�����邱�ƁA���S�Ȑ����Ɣ��B�Ɋ��Y�����Ƃ���̖ړI�ɂ��Ă���Ƃ���Ȃ̂Ō����ɂ���Ă͏��ɓI�ł�������A����̔g�ɏ��x��Ă��邩 ������܂���B����ǂ悭�����悤�Ɂu�������Ă̕���v�Ȃ̂ŁB�������邱�Ƃōň��̌��ʂɂȂ�����A�����Ԃɂ킽��̂̕s������ȂǁA�R���i�E�B���X�����ǂ̕|���������� �����Ƃ��Ȃ��͍̂K���ł����A�����̐g�ɂ͍~�肩����Ȃ��A�Ƃ����y�σo�C�A�X�ɂ͂܂��Ă���Ƃ�����|�����Ƃł��ˁB�����Ȃ�A�ċx�݂ŗ��s��A�ȂȂNJy�������Ƃ����ς��� �W���ł����A���N�݂͂�Ȃʼn䖝�̂Ƃ��A���N�͉��̕s�����Ȃ��y���߂�ĂɂȂ�悤�ɁA�܂������������\�h��O�ꂷ�邱�Ƃɂ��܂��B
��7�����i2021�N7��1���j
�@�@�����A�I�����s�b�N�ɂ��Ă̕��×����Ă��܂����A�R���i�E�B���X�����g��ɂ��ĂƃZ�b�g�̂悤�ł��B�����g��̌������l���ɂ���Ȃ�A�l�̗��ꂪ�傫��������I�� ���s�b�N�Ƃ������E�I�Î��ɊS���W���͓̂��R�ł����A�J�ƒ��~�i�����j�̈ӌ����傫������āA�s�����Q�������ł̊J�ẤA�Ȃ��y���݂������ł��B
�@�@
�T�V�N�O�̓����I�����s�b�N����㕜���̏ے��������Ƃ͂����A���̎��̍����̍��g���Ƃ͑傫�Ȋu���肪����܂��B�����A�U��Ԃ������ɁA�u�Q�O�Q�P�N�����I�����s�b�N�͍���Ȓ� �ŊJ�Â�������nj��ʃI�[���C�������ˁv�Ǝv����悤�ɁA����̐��T�Ԃ͐��O��ł��ˁB
�@�@����̐V���ɁA�s���������w�̍Z���搶�̓��e���f�ڂ���Ă��܂����B�wICT��ϋɊ��p���邱�ƂŐV�����s�o�Z��̎����Ɏ��g�݁A�L�p�������������x�Ƃ������e�ł��B������ ��Ɍg��钆�ŏo��������ʂȎx�����K�v�Ǝv����q�ǂ��������A���w�Z�A���w�Z�ƏW�c�̋K�͂��傫���Ȃ��Ă����ɂ�A�Ǘ�����̂łȂ��ۈ牀�̂悤�Ȉ��S���Ă������A�� ���̓��ӕ��삪�����ł���ꂪ��������ȂƊ���Ă����̂ŁA�ݐЂ��鏬�E���w�Z�ɐV���ȋ���I�r�W�������f���āA��l�ЂƂ�����߂Ă�������g�݂���������邱�Ƃ͑劽�}�� ���B
�@�@���l�s�̏��w�Z�ł͍�������S���k��IPAD���z�z����邻���ł��B���̎q�ǂ������͐��܂ꂽ�Ƃ�����PC��X�}�z�ɐڂ��Ă���̂ŁAICT�̓����ɂ͈�a�����Ȃ��ł��傤�B�A���A OECD�ɂ��Ɠ��{�̎q�ǂ������̊w�K�ʂł�ICT���p�͐��E��v���̕��ψȉ��A�w�K�O�ł͕��ψȏゾ�����ł��B���������Ίm���Ɍ����̃x���`�ő吨�̎q�ǂ��������Q�[���ɋ����Ă��� �p��ڂɂ��܂��ˁB
�@�@����̊��ω��������ẮA���킽����������ɓ˓����Ă������ɂȂ�܂����A���͂Ƃ�����A�q�ǂ����������炩�̕��@�Ŋw�тɑ���ӗ~�������Ăق����A����t�����Ă��鎩 ���Ɏ��M�������ĕ���łق����Ɗ肢�܂��B
��6�����i2021�N6��1���j
�@�@�ۈ牀�O�ʓ��H�ɖʂ����@�ʂ̐A�͍H�����I�����Ă����ς肵�܂����B�J���~�A�i�V���N�i�Q�̒��ԁj.��A���܂������A��������ł��ꂢ�ɍ炢�Ă��܂��B���z�����͎Ő���\����
�����̂ł������ɎG�����͂т���A���ɐA���ւ����ʗ�������܂��G���ɕ����Ă��܂��E�E�E�B�G���Ɛ키�̂͂�����߂܂������A�r�ꂽ�܂܂ɂ��Ă���ƎU�����̗������������Ȃ���
��q���������̂ŁA�n���̑���������ɑ��k���Ē�Ɋ����܂����B�ۈ牀�͂��ǂ��̏�ł�����A���̂Ȃ��A�G�߂���������Ԃ̍炭�A�F�ʂ⍁��̂悢�ԂŖ������Ă�����
���Ɗ肢�A���s�Ɉڂ��̂͂Ȃ��Ȃ����C�̂��邱�Ƃł��B�ی�҂̕��ŃK�[�f�j���O�̓��ӂȕ��A���͂��Ă���������Ɗ������ł��B
�@�@�ً}���Ԑ錾�������ɂȂ艡�l���Q�O���܂ł܂h�~���d�_�[�u���Ԃ������ɂȂ�܂����B���l�s����̂��ւ��z�z���܂������A�e���ƒ�ʼn\�Ȋ����\�h����̂��Ă����� ���悤���肢�������܂��B
�@�@�s���R���������钷�������l�����ɁA�C������Ȃ��A��J��������ȂǑ����̕����S�Ƒ̂̕s����i���Ă��܂����A�R���i�E�B���X�����g��Ƃ��������͂�������~�߂Ȃ��� �͂Ȃ�܂���B���܂��܂ȏ��̔×��̒��ŁA�܂��A���炭�����R���i�E�B���X�����\�h����̊�Ղɒu���A�l�C���łȂ������ƉƑ��̈��S�ȕ�炵�ɂ��Ă�������l����@ ��ɂł�������ȂƎv���܂��B����A�f�W�^�������}���ɐi�݁A���낢��Ȃ��Ƃ��X�s�[�f�B�[�Ō����悭�^�Ԑ��̒��ɂȂ��Ă��A�����Љ�Ŕ��������l�X�Ȏd�g�݂̕s�����v���N�� ���ƁA���E�ł��ˏo����������Љ�ƌ����鍑�Ƃ��̍������A����A���܂ňȏ�ɖL���ʼn��₩�ɕ��ނƂ͎v���܂���B
�@�@�ۈ牀�ł̍s�����قƂ�ǒ��~�ɂȂ��Ă��܂����A�q�ǂ������͖����̐������y���ݎq�ǂ��炵���̌����d�˂Ă��܂��B�ۈ�m�����̓R���i�̕s�����Ȃ��������Ƃ͈Ⴄ���@�ŕۈ� ���ł̐������y���ނ��ׂ��������Ă���Ƃ���ł��B
��5�����i2021�N5��1���j
�@�@�S�����{����A�x�ɂ����āA�Ђ悱�ۈ牀�͏C�U�E�H���ɒǂ��܂����B���ɃG�A�R���H���ł͂T���P���̓y�j���ɂ��ēo�����T���Ă��������悤���肢���܂������A���͂��Ă� �������A���肪�Ƃ��������܂����B���T���A�����I�����܂����B�{�i�I�ȏ����ɂȂ�O�ɏI���Ăق��Ƃ��Ă���Ƃ���ł��B��N�̂W���ɂ͓ˑR�A����ɐݒu���Ă���R���f���T�[���� ��ďC�U�s�\�ƂȂ�A2�K�̗c���ۈ玺�̃G�A�R�����S�łƂȂ�܂����B�X�|�b�g�N�[���[������������^�����đΉ����܂������A�債�����ʂ��Ȃ��q�ǂ������ɂ͑�ςȕs���R�������� ���܂��܂����B�c���ɂ��Ă͎q�ǂ������������Ă����̂ŏ���������ď����ł��������Ƃ���ʼn߂������Ƃ��ł��A�K���̒�������q�ǂ������Ȃ������̂ł����A�������ꂪ�P�K�� �G�A�R�����S�ł��Ă�����E�E�E�l����̂����낵�����Ԃł��B���̎��_�ō��N�̃S�[���f���E�B�[�N�ɂP�K�����̃G�A�R���̑S�ʌ������v�悵�܂����B�{�i�I�ȏ����ɂȂ�O�ɏI���� ��Ăق��Ƃ��Ă��܂��B
�@�@�Ђ悱�ۈ牀�͉��ɏv�H�ȗ��A��18�N���o�߂��Ă���̂ōŋ߂ɂȂ��Ă��܂��܂ȂƂ���ŕs����������Ă���A���̓s�x�C�U���Ă��܂����A���������łł���Ƃ���͓���I�� ���܂߂Ɏ���ꂵ�Ă���A�ۈ�m�����̓h���C�o�[�̎g���������ɂȂ�܂����B
�@�@�n����������Ζ����Ă���E���œ����Q�O�Α䂾�����l�͂S�O���A�R�O�Α䂾�����l�͂T�O���A�S�O�Α䂾�����l�́E�E�E�B�݂�Ȋј\���\�����܂����B���ꂩ��� �S�Ƒ̂̃����e�i���X��ӂ炸�A�q�ǂ���������p���[��������āA���L���ȕۈ���H�����Ă��������ł��B�݂�Ȃ��s���������Ĕ��Ă��邱��Ȏ��ゾ���炱���A�ۈ牀�͈��S�� ����ꏊ�A���邭�N�炩�ȏꏊ�ł��肽���ł��B
�@�@�A�x���̓R���i�E�B���X�������O��̌Ăт�����TV����p�ɂɗ���Ă��܂����B�S�s�{���łً͋}���Ԑ錾�������ɂȂ肻���ł��B�O���łȂ��ꖧ�ł��ł��������ăN���X�^ �[���������邻���ł����A�q�ǂ������ɋߊ��Ȃ��A�����o���Ȃ��Ƃ����͓̂��ꖳ���ł�����A���߂č��܂Œʂ�A��A�}�X�N�A���ł�S�|����悤�ɂ��Ă����܂��B����育�� ���̕����̒��s�ǂ̎��ɂ͎�f���Ă��������ȂNJ����\�h�ɂ����ӂ��肢���܂��B
��4�����i2021�N4��1���j
�@�@�����E�i�����߂łƂ�
�@�@�����A�P�X��ڂ̓������j����s���A�P�U�l�̎q�ǂ��������Ђ悱�ۈ牀�ɒ��ԓ���܂����B�i�������q�ǂ��������V�����S�C�ƒ��ɂȂ���ŐV���ɃN���X�̃J���[��n���Ă� �����ł��傤�B����͂����炮�݂̂��ǂ��������Ō�̎��Ԃ�ɂ��ނ��̂悤�ɍ��܂ŗV��ł����l�X�ȗV�т�H���Ă��܂����B�q�ǂ������̊��������ɂ��Ȃ���A�L���ȗc�N������� �����ė����ȂƊ����܂����B
�@�@�Ђ悱�ۈ牀�́u�������E�������v�ł͂Ȃ��A�u�������j����E�������j����v�Ƃ����Ăѕ������Ă��܂��B�u���v�ƌ����X������łȂ��A��l���ł���q�ǂ��ɂƂ��Ă����� �ۈ�̉�������Ɉʒu�t���Ă��邩��ł��B
�@�@����A�������j����s���P�X�l���������܂����B�����͎��R�z���Ƃ����̂̎q�ǂ������ł����A����ł��ْ����ĕ��i�͌����Ȃ��\������Ă��܂����B������Ƃ�����
��������������q�ǂ������̑ԓx�ɑ����̕ی�҂��܂𗬂��Ă�������Ⴂ�܂����B
�@�@��N�x�̓R���i�E�B���X�ɂ���ēˑR�A�ۈ牀�ł̉߂������A�s���̎�肭�݂Ȃǂ��]�V�Ȃ��ύX������Ȃ����������ʂ͔ۂ߂܂��A�ǂ�Ȃ��Ƃł��u���ǂ��ɂƂ��Ăǂ� �Ȃ̂��v�Ƃ������_�����������ƂȂ��ۈ��i�߂Ă����P�N�ł����B�܂��A�s�����k�����ꂽ���Ƃɂ�蕉�S�������������Ƃ������ł����B���N�͍�N���{�����ی�҃A���P�[�g�ɋL�� ���ꂽ���ӌ����Q�l�ɂ��Ȃ���A�V���Ȏ��_�ł̎��g�݂����Ă��������Ǝv���Ă��܂��B�܂��܂��R���i�E�B���X�����g��̕s���͕��@�ł��܂��A�\���ȗ\�h������Ȃ���q �ǂ������A�ی�ҁA�E���F���y���������ł���ۈ牀�ł��肽���Ǝv���܂��B���N�x�������́A���x�����������܂��悤���肢�������܂��B
��3�����i2021�N3��1���j
�@�@���ނقǂ̗z�C�Ɩk���ɑ̂�����点������s�����藈����A�܂��Ɂu�O���l���v�ő̒�������₷�����������Ă��܂��BT�u�ŃR���i�̊����҂������Ă���Ƃ̕��J��Ԃ� ��钆�ŁA���{���łً̋}���Ԑ錾�����̌���͈��H�ƂȂǂɌg�����̗���ɗ��Ă�ނȂ��̂ł��傤���A�q�ǂ��̈��S�����d�����闧��ł͍Ăъ������g�債�Ȃ����ȂƊ뜜 ���܂��B���N�`���ڎ킪��Ï]���҂���n�܂�A�����L���Ă������ʂ��ł����I�����s�b�N�J�Â̗L���͂Ƃ������Ƃ��Ĉꍏ���������ʂ����҂��܂��B
�@�@����P�W���A���������݂Ƃ��邩���݂̓����Ɂu���o�������ɃL�c�c�L�����ăR�c�R�c�Ɩ̊����������Ă���l�q���q�ǂ������ƌ����v�Ƃ̋L�ڂ�����܂����B�u���ԈႢ����� ���H����ȂƂ���ɂ���͂����Ȃ��v�Ǝv���A�����l�b�g�Łu�s�}��E�L�c�c�L�v�ƌ������Ă݂܂����B�Ƃ��낪�Ȃ�ƁA�l�G�̐X�����A�s�}���������ȂǗΐ[��������Z��n�ł��� �Ό��������Ă��邻���ł��B�Ђ悱�ۈ牀�̋߂��ɂ����Ă��ꂽ�ȁA�Ƃ��ꂵ���Ȃ�܂����B���Ȃ݂Ɂu�L�c�c�L�ڃL�c�c�L�ȃR�Q���܂��̓A�I�Q���v�炵���ł��B�ߗׂɗ̑� �����ŕۈ炪�o����K������X�����Ă��܂����A�r���̒��ŕۈ���c�܂���Ȃ��ۈ牀����������A�R���i�Ђ̒��ł̂���J�͂������肩�Ǝv���܂��B�ǂ̕ۈ牀�̎q�ǂ� ��������̉��Ŏv��������V���Ă��������ł��ˁB
�@�@�R���i�ɂӂ�܂킳�ꂽ���̂���Q�O�Q�O�N�x�ł������A�ۈ���Ϗk�����邱�ƂȂ��q�ǂ������ɂ͍��܂Œʂ�ɗl�X�Ȍo���������Ă��������ƁA�H�v���Ȃ���i�߂��P�N�ł����B �ی�҂̊F����ɂ͕�����Ȃ�������ꂽ��������������Ƃ͎v���܂����A�ۈ�҂Ƃ��Ă͎蔲���������Ƃ͂Ȃ������ƐU��Ԃ��Ă��܂��B�S������́A�܂��A�V���ȑ̐��Ŋy������ ��ɂ������Ǝv���Ă��܂��B�l�X�Ȃ����͂��肪�Ƃ��������܂����B
��2�����i2021�N2��1���j
�@�@�����͐ߕ��B���N�͖����R�O�N�ȗ��A�P�Q�S�N�Ԃ�ɂQ���Q���ɂȂ邻���ł��B�ۈ牀�ł͗�N�S�ގ������Ă��܂������N�͏����ς������@�ŋS�ގ������܂��B���Ƃł��q����ɂ� ��Ȃ������������Ă݂Ă��������ˁB
�@�@�ʋΎ��̌i�F���ς���Ă��܂��B�V���b�^�[�X�Ƃ͌���Ȃ��܂ł��A�p�ƁA�x�ƁA�u�e�C�N�A�E�g�ł��܂��v�̊Ŕ⒣�莆���悭�������܂��B�R���i�E�B���X�����g��ɂȂ�ȑO �ɂ́A�A��r���̎Ԃ̑�������������ɂ��X�ɓ���Ƒ���ߋA��̓����Ǝv�����l�����̎p���悭���������̂ł����A���͂���ȗl�q������܂���B�ً}���Ԑ錾�������ƂȂ�悤�� �����A�F�����l����������Ă���̂��ȂƎv���܂��B
�@�@�����ȑO�̐����ɖ߂�邱�Ƃ��肢�Ȃ�����A�ˑR�̃R���i�Ђɂ���܂œ�����O���������������������ʂ�����C�����Ă��܂��B�ߏ�ȂقǂɎ��R�C�܂܂ɉ߂����邱�Ƃ���A�� ������Ɨ��������������A�m�b���o�������čH�v���ĉ߂������Ԃ��o�����邱�Ƃ��o�����͕̂s�K���̍K���ł����H�����������ƋΖ��ƈ玙�ƉƎ��Ƃʼn����ƍQ���������߂��Ă����� ���������Ɨ����~�܂��Ă݂܂��H
��1�����i2021�N1��1���j
�@�@�����܂��Ă��߂łƂ��������܂�
�@�@�V�^�R���i�E�B���X�̊����g��ɒN�������₩�Ȃ�ʓ��X���߂�������N�ł����B����ł��V�����N�͂��ׂĂ̐l�ɕ����ɓ������āA�������͂����ʂ�Ɂu���߂łƂ��v�ƈ��A�� ���킵���퐶���𑗂�Ă��܂��B��N�A�N���N�n�͈�Ë@�ւ��A�x�ɂȂ�̂ŕs���ɂȂ����������̂ł����A���N�͓��ɃR���i�̎�������A�����Ȃ��q����⍂��̉Ƒ��̂�����ɂ� ���Ắu�����A��������Ȃ�����E�E�E�v�ƕs�������債�����ƂƎv���܂��B
�@�@���̔N���N�n�͊����g�傪�}���Łu�O�o�͔����܂��傤�B�Ƃɂ��܂��傤�v�ƍ��⎩���̂̌Ăт���������A�����̐l�X���������܂������A�����g�ɂ��Ƒ������Ȃ���N���N�n�ɋx �ݕԏ�Őf�Â��Ă�����������t�A�Ō�t�A�����Z�t���̕��X�ɂ͖{���ɓ���������܂��B�g�����������ē����Ă���������̂ł��ˁB���肪�������Ƃł��B���̂悤�ȕ�ڂɂ� �āA�������ۈ�҂����͂Ȃ����A�}�X�N�A���łȂǕۈ牀���ł̊����\�h�ɓw�߂܂��B
�@�@�܂��A�R���i�̋��Ђɉ����āA�����������ۂɖڂɂ��邱�Ƃ̂Ȃ����E�̏��X�ŋQ���n���A�푈��e�����������Ă��邱�Ƃ�Ō��������Ă��܂��B�Ђ悱�ۈ牀�Ŏq�ǂ��炵
��������ۏႳ��Ă���q�ǂ������Ɠ����N���̎q�ǂ������̔ߎS��`���������҂Ƃ��ĉ����ł��邱�Ƃ�����i��l�ł���̂łȂ��݂�ȂŎv�����āj.�Ǝv���܂����A�ǂȂ���
�����͂��������܂��B�i�ی�ҁA�E���ŕ������Ȃǁj
�@�@��N�͕ی�҂̕�����ۈ�^�c�ɂ��đ����̂��ӌ����܂����B���A��l��l�̂��ӌ���ۈ�҂����S���ɓ`���Ĉӌ����o���Ă�����Ă���Ƃ���ł��B�Ђ悱�ۈ牀�̕ۈ�� ��ɂ��Ă��闝�O�ƁA����̕ω��ɍ��킹�ď_��ɉ^�p���ׂ��Ƃ���Ƃ��ǂ̂悤�ɒ��a�����Ă����悢���B�����āA�݂�Ȃ��[���ł�������ɕς��Ă����ۂɂ͕ی�҂̕��X�ɂ� �ǂ̂悤�Ɋւ���Ă��������̂��B�l����ׂ����Ƃ���������܂��ˁB
�@�@���N�͉N�N�B���͌Â�����H���A�����A�k���Ɛl�Ԃ̕�炵���x���Ă��������ł��B�S�苭���E�ϋ��������Ƃ���A�N�N�́u�䖝�v�A�u���W�̑O�G��v�̔N�ƌ����邻���ł��B�� ����]�����Ă܂��ˁB�E�B�Y�R���i����A�t�^�[�R���i�ցA�������A�̂�т�A��䍂��Ȃ�����݂������̂ł��B�Ԉ���Ă��u�����v�ɂȂ�Ȃ��悤�ɐS�����܂��B
��12�����i2020�N12��1���j
�@�@���N�A�t�A�āA�H�Ɏ��{���Ă����l�X�ȍs�������̕ۈ�̉c�݂��A�ύX������k�������肵�Ȃ���q�ǂ������Ɗy����ʼn߂�����8�����ł����B���̒��̓R���i�s���ɖ|�M����Ă� ��l���ł����A�����V�����̎��X�͕ς�炸�G�߂������čg�t�A���t���āA�F�Ƃ�ǂ�̂��イ������v���[���g���Ă���܂����B�Ђ悱�ۈ牀�̉����������A�҂�҂悮�݂̐Ԃ��� �炭���炮�݂̂��˂�����A���ɂ������܂ŁA�����t�̊��G�i���Ă�������y���݂܂����B�U����ŏW�߂������t��h���O���A�̎��Ȃǂ��Ƃɂ�������̂��y�Y�������� �������̂œ����̕ۈ�̗l�q���v�������ׂĂ����������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�@�@���R���^���Ă������̂ɐ[�������������A�q�ǂ����m���S��`�������Ċւ���Ă��鎞�ȂǕۈ璆�ɂ͎q�ǂ��Ȃ�ł͂̊��������Ă���ȁA������Ă����Ă���ȂƎv ����u�Ԃ����т��т���܂��B����ȏ�ʂ�ۈ�҂��Ɛ肵�Ă͂��������Ȃ��̂ŘA������h�L�������e�[�V�����A�A���{�[�h�Y�t�́u�����̕ۈ�v�A���X�̃X���C�h�V���[�Ȃǂł��` �����Ă��܂����A�R���i���������čĂѕۈ�Q���ȂǂŎq�ǂ������̐��̎p�����Ă���������������邱�Ƃ��肤����ł��B
�@�@�c���N���X�ɂȂ�Ǝq�ǂ������͔p�ނ�������������Ďv���v���ɐ��슈�������Ă��܂��B�S�����ꏏ�̊����i�̃L�b�g�ł���{�ʂ�ɑn��̂ł͂Ȃ��A��l��l�����R�ɃC�� �[�W������i��n���Ă��܂��B�������A�v���t���Ŏ��|���������̂̂����r���ŖO���Ă��܂�����A�p�ނ����W���邱�Ƃɂ�������Ă��܂����肷��q�����܂��B����ł��F�B�ƃe �N�j�b�N�������������肵�Ȃ���A����Ɏ��ۂ̗V�тɎg�����i���o���オ��悤�ɐi�����Ă��������Ԃ�͂������Ȃ��ƒE�X�ł��B���X�ATV��G���ŏЉ���O�q�A�[�e�B�X�g�� ��i�Ƃ�������Ȃ��̂�����A�u����͏����L�]�����E�E�E�I�v�Ɛe���Ȃ�ʉ������ɂȂ��Ă��܂��B
�@�@�Ђ悱�ۈ牀�ł͕ۈ�m�����͎q�ǂ����������ƂȂ̊�F�������������ƂȂ��A����ǁA�����Ǝ��͂̐l���Ɏv���銴����݂Ȃ���L�ѐL�тƈ���Ăق����Ɗ���Ď��s���낵�Ȃ���ۈ���H�����Ă��܂����A�v���悤�ɂ������ɁA�肢�Ƃ͈Ⴄ�����ɐi��ł�����������܂��B�q�ǂ������Ɠ����悤�ɂЂ悱�ۈ牀�����낢��Ȍo����ƂƂ��āA
�@�@�ی�҂̒m�b�Ƌ��͂Ȃ����ۈ牀�ł��肽���ȂƁA�R���i�����ňϏk�������Ȃ��̂���Ɏv���Ă��܂��B
�@�@�Q���������߂���Q�O�Q�O�N�ł����A���N�͗����t�����N�ɂȂ��Ăق������̂ł��B��A�}�X�N�ȂNJ�����̊�{������Ă��������A�c��̓��X�����₩�ɂ��߂������������B
��11�����i2020�N11��1���j
�@�@�P�P���ɂȂ�A�X�H���̂����傤�����t���͂��߂܂����ˁB����̃��~�W���Ԃ��Ȃ��Ă��܂����B�ߗ����ł̃X�Y���o�`���������܂�Ή��O�ۈ�ł܂��A�v�������ɑ��������� �A�����t��h���O���E���i�ł��܂��ˁB�X�Y���o�`�̏�������狳���Ă��������B
�@�@�Ђ悱�ۈ牀�̉���ɂ͕ۈ玺����̕ی�҂���̊ł���L�O���P���L�̑���͂��߁A�J�c���A���~�W�o�t�E�A�J�G�f�A�T�N���A�E���A�l���m�L�A�V���J�V�A�J�i���A�n�i�~ �Y�L�A�t�W�Ȃǂ̖�A�q�������S�A�E���A���}�����A���X���E���A�u���[�x���[�Ȃǎ��̂Ȃ���A�����Ă��܂��B�ۈ牀�̒�ɂ͎��̂Ȃ���q�ǂ������Ɗy���݂����ĐA������ �ł����A�����I�ɂ͂܂������n���Ȃ������ɂ��܂܂��Ƃ̑f�ނɂȂ��Ă��܂��Ă��܂��B���ƂȂƂ��ẮA�g�z�z�I�ł����q�ǂ������������ɂȂ��ėV�ԗl�q�ɁA��������肩�ȁA�Ǝv ���Ă��܂��B�t�Ƀt�W�����J�ɂȂ邱��A���N�����I�ɔ������������܂����B��N���������ŗ����炩�������ЂȂ����������̂ł��ڂ��Ă���̂ł��傤���H
�@�@���̎q��Ă�������đ��̉��ɃV�[�g��A�q�ǂ������ɂ͐Â��ɗV�Ԃ悤�ɋ����Ă���ۈ�҂̎p�͋P���Ă��܂�����B����ȓ�����߂����q�ǂ������͂����킹�ł��ˁB
�R���i�E�B���X�����̕s�����獡�܂Œʂ�ɂ͂ł��Ȃ����Ƃ������A������܂肵�����ȕۈ�ł����A�傫�ȁA�ڗ��ۈ犈�����o���Ȃ����Ƃɕs����X�g���X�����̂ł͂Ȃ��A�D�� �S�������ē���̒��ɂ��y������V�������������邱�Ƃ̂ł���q�ǂ���������A���ƂȂ����͂�������̎��������Ă�����Ă��܂��B�����ȍK�����Č��\�g�̉��ɂ�������B��Ă� ���ł��ˁB
��10�����i2020�N10��1���j
�@�@�����͒�9��30������A���l�s���ǂ����N�NJč��ۂɂ��2�N��1�x�̈�ʎw���č������{����܂����B�č��ۂ̒S���W����S���E���A�h�{�m�A�ۈ�m�Ȃǐ������������āA���O�ɒ� �o������������ɁA�ו��ɂ킽��_���E�m�F���܂����B���N�x�͐V�^�R���i�E�B���X�����ǂ��������Ă���̂ŁA��N�̂悤�ɁA�{�݂�ۈ玺�����ώ@���ĉ�邱�Ƃ͂���܂���ł��� ���A�o����ς��X���v���v�����`�F�b�N���܂��B�ۈ牀�̉^�c�A�q�ǂ������A�E���̏����A�ۈ�̌v��A�ی��q���A���H�̎��{�A�����ĉ�v�E�o���ɂ��ĂȂǏ��ނ��ׂ� �����ׂ܂����B
�@�@�Ђ悱�ۈ牀�͈ꌩ����Ɖƒ�I�ł̂�т�A�ق�킩�������͋C�ł����A���̂��߂ɂ͑����̒Z���ԋΖ��E���̔M�ӂɂ��O����Ȑ��|����ł̂������ŃR���i�s���̒��A�q���� �E���S�ʂň��S�������������藧���Ă��܂��B�\�ʂɂ͕\��Ȃ��l�X�ȓ�����z���������Ă����A���߂ĕۈ牀�����������ƋP���Ă�����̂ł��B
�@�@�S���I�ɕۈ珊�̐E���s��������ꑱ���Ă��܂����A�Ђ悱�ۈ牀�ł͒n��̕��X�̂��x���������č��܂ŁA�q���q���A�n���n���̏�Ԃł̕ۈ��������ꂽ���Ƃ͂���܂���B�� �����ی�҂̊F�����E�������킹��Ƒ������̐l�ԊW������̂ł�����A�ׂ��ȃg���u���͂���Ȃ�����A�݂�Ȃ��������̂Ƃ���Łu�q�ǂ������Ƃ��ĉ�������v��T��� �A�܂��A�ی�҂̕��X�ɂ��������Ă������������ƁA�Ԃ�Ȃ��ł��邱�Ƃ�����̊�b�ɂȂ��Ă���̂��Ǝv���܂��B
�@�@�ߘa2�N�x�͓o�����l���Ԃ�玙�x�ɂ̉��������������߁A����0�Ύ��N���X�ł͓���������8���ȍ~�ɂ��ꍞ���ƒ�������A���܂��V�w���̗l���ł��B�܂��A�s���ȂǍ��܂ł̂� ���ɂ͏o���Ȃ����Ƃ������A�ی�҂̒��ɂ͕�����Ȃ��������Ă�����X�������܂����A�q�ǂ������͂���Ȃ��Ƃ͂��\���Ȃ��ɍ���������̒��ł��ꂼ��̑z���͂Ɖ��p�͂���g�� �Ė������y����ł���Ȕ�펖�Ԃɂ��������Ă��܂��B��l�ЂƂ肪�����̐��E�̒n�������g���Ă����Ă���悤�ɂ������܂��B���܂ł̂悤�Ȑ����ɂ͖߂�Ȃ����낤�ƌ����n�߂� ���邱��Ȕ�펖�Ԃɂ����A�����łȂ��Ă͂����Ȃ��A��������˂Ȃ�Ȃ��A�Ƃ����Œ�I���l�ς���E�o���āA��l�����͑O�����ɁA�q�ǂ��������f���Ȋ����Œz�����Ƃ��Ă��鎩 �R�Ȑ��E������Ă��������Ɩ]�݂܂��B
�@�@
��9�����i2020�N9��1���j
�@�@�Ђ悱�����X�����A�Ə����āA�u�����A�����X���Ȃv�Ǝv���܂����B�����̉߂�����͓̂�����O�̂��ƂȂ̂ɂS���̐V�w���ȗ��̐������������������̂̂悤�ȁA���邢�͖��̒��̏o�����̂悤�Ɋ����Ă��܂��܂��B
�@�@�R���i�E�B���X�����ɂ��u�V���������l���v�Ƃ������t���l�X�ȏ�ʂŎg���āA�������̂�����X�͓���̒��ɂ��܂�������āA�ǂ��ɂ���炵�Ă���̂ł��傤���A�]�݂��̌ł��Ȃ��������́u�ǂ����Ă���Ȃ��ƂɂȂ����낤���A�Ƃ����������Ȃ������낤���v�Ƃ̎v�����₦��������ł��āA�s���R���Ɠ��ĂǂȂ��{��������Ă��܂��B
�@�@�T�O�N�ȏ�̂̂��Ƃł����A�w���̍��A�Љ�w�̎��ƂŁu�Ȋw�͐l�Ԃ��K���ɂ���̂��H�v�Ƃ������Ƃ��e�[�}�ɂ����u�`�����L��������܂��B�����̐i����M�����Ă����l�ނ̑傫�ȕ��̈�Y�Ƃ��Đ푈�⌴�����������c�Ƃ��������e�ł����B�s�^�ʖڂȊw�����������͒P�ʎ擾������ړI�Ƃ��Ă����̂œ��e�͑S���o���Ă��܂��A�����A�l�Ԃ̗��v���ŗD�悵�Ēn����̑����̕����⎩�R���𗘌ȓI�ɗ��p���ė������Ƃ̂����A����̃R���i�Б����Ɩ��W�ł͂Ȃ��̂��ȁA�Ɗ����܂��B
�@�@�ŋ߁ATV�Ȃǂŏ��a�̐�������p�i�����グ��ԑg�������Ă���C�����܂��BIT��AI�ȂǃA���t�@�x�b�g�ŋL�ڂ������̔×��̒��ŁA�V���킸�̂̂̂�т肵�����Ԃ̒��ɐg��u���Ă݂����Ǝv���l������̂ł��傤�B
�@�@�ۈ牀�ł͍�N���A�c������̖������E���H���H��̎��ȕ��S���E�ً}���Ԑ錾�E�o�����l�˗��ȂǁA���܂łɂȂ��^�c���@�̕ύX�ɔ����W���ނ̍쐬�Ȃǎ�����Ƃ��c�剻���܂����B�܂��A�ی�҂̊F����ւ̓`�������s�\���ƁA�ꕔ�̕���育�s���̐������������܂����B���������s�̎{�ς�邽�тɁA�ۈ珊�P�ʂŕύX���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����Ƃ��N���Ă���Ǝv���܂��B�ی�҂̕��ɂ͓s�x�A�o������蒚�J�ɂ��`�����ď����ȕۈ��i�߂����Ɗ���Ă��܂�
��8�����i2020�N8��1���j
�@�@�V���R�O�����X�F�R�W�A��ĂɃz�����z�����Ƒ剹�ʂ������������狿���Ă��܂����B����Ɂu�ً}�n�k����ł��B�����h��Ɍx�����Ă��������v�Ƃ̃A�i�E���X���B�q�ǂ�������ۈ牀�ɗa���ĐE��Ɍ������ی�҂̕��͂����ْ����ꂽ���ƂƎv���܂��B������f�b�L�ŗV��ł����c���������т����肵�ĕۈ�m�̉��ɏW�܂��Ă��������ŁA�u�������ɔ��P���̌��ʁI�I�v�ƕۈ�m�����͊��S���Ă��܂����B���X�̌J��Ԃ����đ�ł��ˁB
�@�@�R���i�����҂��P�O�O�O�l/�������Ƃ�����@�I�̒��A�n�������������ɂ��Ă����J�A�X�ɂ����ő�n�k����������E�E�E�B�]���ɔߎS�Ȍ��i�������т܂������A�Ƃ肠�������Ƃ������Ƃő�n�k���Ȃ��Ă悩�����ł��ˁB
�@�@�u�ۈ�m�������߂����v�E�u�������W�c����������c���S������v�Ƒ匩�o���ŐV���ɋL�����ڂ�܂����B�ǂ̕ۈ牀�ł��q�ǂ������Ɂu���v�Ȋ��������ׂ��l�X�ȑ���Ƃ�A�܂��A���܂߂ȏ��ł��A�}�X�N�Ȃǂ�O�ꂵ�Ă��Ă��l�̏o���肪�����̂Ő₦���������X�N�ɂ��炳��Ă��܂��B�Ђ悱�ۈ牀�ł͕ی�҂̕��ɂ������O�̎�ƃ}�X�N���p�̋��͂����Ă��������Ă��܂����A����ł����S�ɂ͒������Ǝv���܂��B
�@�@�V���ɂ��Ɓu��ÁE���]���҂Ɏx������鍑�̈ԘJ���x���Ώۂɕۈ�J���҂����O���ꂽ�̂ōX�Ɍ��ꂪ�敾���Ă���v���ȏ������ł����A�ʂ����Ă����Ȃ̂��H�������ɂ����͂����炠���Ă��ז��ɂ͂Ȃ�܂��A���^�͑����ɉz�������Ƃ͂���܂��A�����ȕۈ�҂��ł��肤�Ƃ���͎q�ǂ������̈��S�ƈ��S�̓��X�ł��B
�@�@�u�������A�q�ǂ������Ɍ��₩�ŖL���ȂP�����߂����Ă��炦���v�Ƃ����B�����ƁA�����̕ۈ�ւ̊肢��ی�҂ɂ��������Ă����������Ƃ��̏[�������G�l���M�[�ɂ��Ė��������Ă��܂��B
�@�@�R���i�Ƃ������Čo���������Ƃ̂Ȃ��ЉЂɒ��ʂ��āA�Ђ悱�ۈ牀�ň�l�������҂��o���Ȃ��w�͂ƁA�ی�҂̕��X�Ƃ̋��͊W����ɁA����̍��ׂȂƂ��납����������P���ď����Ă����܂��傤�B
��7�����i2020�N7��1���j
�@�@�N�x���̑������j������肩�猻�݂܂ŁA��N�Ƃ͑S���قȂ�ۈ牀�̗l�q�ł����B�N���o���������Ƃ̂Ȃ��V�^�R���i�E�B���X�̋��Ђɕی�҂̊F����͂��ߐE�����A�ْ����Ȃ���߂��������̐������ł����B�U���œo�����l�v���������ɂȂ����Ƃ͂����A�����ł͂��̐����A�T�O�l���銴���҂��������Ă���Ƃ����j���[�X������܂��B�܂��A���E���ł��ꂩ��嗬�s���N����̂ł́H�Ƃ�����̌����Ȃ��s��������A�N���������S���ĉ߂����Ă͂��Ȃ��A�Ƃ����̂������Ǝv���܂��B
�@�@�s�u��ʂ���̓����[�g���[�N���e�����[�N���I�����C����c�i�ۂ݉�E�E�E�j���A�J�^�J�i�̌��t���Ђ�����Ȃ��ɗ���A����߂ď��a�I�ł���l�ԂɂƂ��Ă͖����̐���������s�\��Ԃł����A�߂��Ă����q�ǂ������̌��C�Ŋ��C���鐶�̐��ɍ��܂ňȏ�Ɋ��ӂ��Ă��܂��B
�@�@�ۈ牀�ł̋Ɩ��͎q�ǂ������Ɖ߂������Ԃ�_�����Ɠ������炢�ɋL�^��v��Ɋ|���鎞�Ԃ���������ł��B�Ɩ��ȗ͉��E�h�b�s���������ċv�����A��������߂�Ǝ҂������ł����A������킹�āA�\������Ȃ���̘b���������Ƃ̊y�������̂Ă��ꂸ�A�Ђ悱�ۈ牀�ł͑S�����W�܂��Ẳ�c�����{���Ă��܂��B
�@�@�u�V�^�R���i�E�B���X�ɌW��ۈ珊�̑Ή��ɂ��Ă̂e�`�p�v�i���l�s�g�o�j�ɂ͕ۈ珊�s���̒��~�ɂ��Ă̕s���̐����オ���Ă��܂����A�Ђ悱�ۈ牀�ł̓R���i�����h�~�Ɛe�Ǝq�ǂ��̕ۈ珊���y���ތ����Ƃ��͂���Ɋ|���Ȃ���s�����ǂ̂悤�Ɏ��{���邩�������ł��B�ی�҂̕��X�ɂ����ꂼ��̓��ӕ�������āA�o����Ƃ���ő傢�ɎQ�悵�Ă��������A�m�b�Ɨ͂�݂��Ă��������Ă݂�Ȃŕ��S���������Ȃ���A�݂�Ȃ������ł���Ƃ����ڎw���܂��傤�B
��6�����i2020�N6��1���j
�@�@�Q�����̓o�����l���o�����A�������Ɏq�ǂ�������e�����̃X�g���X�����܂��Ă��܂��B���l�s�ł͈ˑR�Ƃ��ēo�����l�̗v�����o�Ă��܂����A�Z�펙�̕��U�o�Z���n�܂�����A�e�̍ݑ�Ζ����������肵�Ă���̂ŁA���������R���i�ȑO�̂悤�Ȏ��R�Ȑ����ɂȂ�̂��ȂƁA�W�����҂������������܂���ˁB�s�u�ɉf���o����Ă���X���̗l�q�����Ă��Ă��u�ً}���Ԑ錾�����v�̕����̈Ӗ��������g����߂���Ă���ȂƎv�����Ƃ���������܂��B
�@�@�u�����Ƃ邩�o�ς��Ƃ邩�v�Ƃ������蓾�Ȃ���ґ���̖��ɁA�Ђ������`�Əo�Ă����̂��u�V���Ȑ����l���v�̊T�O�ł��B���̌��t�����ł��g�����f�B�[�ɂȂ��Ă��܂��ˁB
�@�@�ł́A�����I�ɕۈ牀�ł̐V���Ȑ����l�����A�ǂ��n���Ă������B�O���������Ƃ����Ă��q�ǂ������ɋ߂��ȁI�吺���o���ȁI�͂��Ⴎ�ȁI�Ƃ͂ƂĂ������܂���B�s�\�ł��B�L�X�Ƌ������Ƃ����e�[�u���ŋ��H��H�ׁA�ʁX�̕������g���Ă������ƌߐ����Ƃ�A�q�ǂ������͈�l�Â\���ɊԂ������ĐÂ��ɗV��ł���c���z�ł��B����ꂽ�l�I�A���I���̒��Ŋ������X�N��Ȃ��悤�ɁA�������[�������V�т�ۏႵ�Ă��ꂩ��ǂ̂悤�ɕۈ炵�����̂��A���܂ł̕ۈ�o���̒~�ςƐE���Ԃ̓������ɕ����Ƃ���ł��B
�@�@�S���A�T���̓o�����l���Ԓ��͎q�ǂ������̐l�������Ȃ��A�E�������͕ۈ牀���O�̊������ƁA�Ǝ҂ɂ��s��̏C�U�ɖ������܂����B�P�W�N�Ԃ̕ۈ珊�^�c�ł���قNj�Ԃ��L�����͂��Ė��������̂ŋ��X�܂œ_�����āA�q�ǂ��������߂��Ă������ɔ����܂����B���N�x�́A�s���Ȃǂ͎v���悤�ɂ͂ł��܂��A�q�ǂ������̊��҂Ɗ肢���Ԃ��Ȃ��悤�ɁA���J�ɕۈ���e���������Ď��H���Ă����܂��B����Ȏ������A���O�ꂾ�Ǝv���̂ł��B
��5�����i2020�N5��1���j
�@�@�V�^�R���i�E�B���X�̘b��ɏI�n���閈���ł��B���ɐ����A�������Ă���قƂ�ǂ̐l�ɂƂ��Čo���������Ƃ̂Ȃ����ԂɓˑR�������āA�܂�ŁA�������̂̔����f��̒��ɂ��邩�̂悤�Ȕ��I�C���𖡂���Ă��܂��B
�@�@�ی�҂̊F����ɂ́A�ݑ�Ŏd��������A�����̕s���������Ȃ���E��ւƓd�Ԓʋ�����A�܂��A�d���������Ď���������������ƍ���ȏ̒��ɂ��������邱�Ƃł��傤�B�܂��A�q�ǂ������������Ԃ̎���ҋ@���������Ă��āA���ƂȂ��q�ǂ����X�g���X�����܂�ɂ��܂��Ă��܂��ˁB
�@�@�ی�҂̒��ɂ͊�����֘A�E���Ŋ댯�Ƒ��Z�̉Q���ɂ���������܂��B�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂��B���̂悤�ȕ������钆�ŋً}���Ԑ錾�����o���Ĉȗ��A�o�����T���邲�ƒ낪�����Ȃ�A�ۈ牀�͘A���A�o�Ȏ��������������Ă��܂��B�F����̂����͂ɂ��A�E�������Ŏ���ҋ@�o���Ă��܂��B�����̎q�ǂ��𑼂̕ۈ牀�ɗa���ċΖ����Ă���ۈ�m�A�V�e�̉������Ȃ��瓭���ۈ�m�����܂����A���̑��̐E����������O�ł͂Ȃ����̒��̏�����Ɠ��l�ɗl�X�ȍ���Ɛ܂荇�������Ȃ���A���݂��Ɏv������ă`�[�����[�N�悭�N�炩�ɕۈ�^�c���Ă��܂��B
�@�@�ŗL�̎���Ől�����ɒ[�Ɍ������ۈ牀�ɒʂ��q�ǂ����������āA�����̗F�B�ƃ_�C�i�~�b�N�ɗV�Ԏ��͏o���܂��A�����ȏW�c�ł̂����т�A�ٔN��ł̗V�т��H�v���Ă��܂��B�������q�ɂ��Z�����A���o�����ƌ����ďƂꂽ�\���������q�A�傫���q�ɂ͂��߂͋��鋰��߂Â�����ɂׂ�����Â���q�A���i�Ƃ͈Ⴄ�ۈ牀�Ō�����q�ǂ������̖��������\�������Ɍ��������āA�q�ǂ�������߂��܂��Ȃ��悤�ɁA�g�߂ȂƂ���ň�l�Ƃ��Ċ����҂��o���Ȃ��悤�ɁA�ꍏ���������̐����ɖ߂��悤�ɂƊ���Ă��܂��B
�@�@�����ǂɂ��ẮA��̗�s�A�P�G�`�P�b�g�A�l���݂������A�\���Ȑ����ƃo�����X�̂Ƃꂽ�H���ȂǁA���i����ǂ��Ƃ���Ă����{���m���ɂ��A�ْ����ƖړI�ӎ��������Č��������Ƃ��K�v�ł��ˁB
��4�����i2020�N4��1���j
�@�@�����A�i�����߂łƂ��������܂��B�q�ǂ������͐V�����N���X�ɂȂ��ă��N���N����Ɠ����ɁA�S�C���ς���Ă�����ƃh�L�h�L�����Ă��܂��B�����Ƃ����Ɨ��������Ȃ����̎����A���Ƃł͂������ƌ��������Ă����Ă��������B
�@�@�~���Ă킢���悤�ȐV�^�R���i�E�B���X�����ǂ̋��ЁA���{���قڑS��Ŋ������g�債�Ă���A�L���ȃR���f�B�A���̂r���S���Ȃ����j���[�X�ɑ����̐l�X����債�A���̕a�C�̕|�����v���m�����Ƃ���ł��B�S���������̌����Ȃ��G�ɂ��̂̂��A���������̍��̋G�߁A�V�w���̐���₩�ȋC�����䖳���ł��ˁB
�@�@�q�ǂ������͌��t�ł͒m���Ă��Ă����R�Ȃ���{���̕|���͒m��܂���B�ۈ�ł͂�������ɕs�����������ċ������̂łȂ��u����������邱�Ɓv�A�����ĉ������ۂɎ����������ł��邱�Ƃ���������`���āA�������H���Ă����܂��B�H���̑O���V��A�O�o����߂����Ƃ��ȂǁA�����ڂɂ͉���Ă��Ȃ��Ă������������鎖�A���i�����ƌ����Ă���悤�Ȃ��т���������ƐH�ׁA���Q���N�����邱�ƂȂnj��N�I�Ȑ������q�ǂ������ɕۏႵ�Ă��������Ǝv���܂��B���ƒ�ł����͂��Ă��������܂��悤���肢�������܂��B
�@�@�I�����s�b�N��1�N�����ƂȂ����悤�ɁA���̍ЉЂ�����ǂ̂悤�ɐ��ڂ���̂��S�������Ȃ��ł����A�{���ɂ����Ă��A���N�x�̍s�����̌v�悪���m�ɂ͗��Ă��Ȃ��ł��܂��B���߂ł́A���܃v���[�U�Ђ悱�ۈ玺���ォ��s�}�Ђ悱�ۈ牀�ւƁA�J���ȗ�37�N�Ԃɘj�葱���Ă����u�Ђ悱�܂�v�͍��N�x�͒��~����������Ȃ��ƍl���܂��B�X�ɏ����w�Z�̌v��\�肪�傫���ύX���Ă��钆�ŁA�Ȃ܂��^������ǂ��������̂��v�Ă��Ă���Ƃ���ł��B��N�A�N�x���߂ɒ��Ă���N�Ԃ̍s���v��͂��炭���҂����������悤���肢���܂��B
�@�@���A�������Ă��鎄�������N���o���������Ƃ̂Ȃ����̕a���g��̊�@���A��l��l�̎��o�Ɠw�͂��Ȃ��ŏ��z���Ă����܂��傤�B�q�ǂ������ƕی�҂̊F����ƁA�ۈ珊�E���ň��S���ďW�������S�҂��ɂ��Ă��܂��B
��3���ŏI���i2020�N3��2���j
�@�@��N�Ȃ�A�ЂȂ܂�̂ق�킩�Ƃ����C���𖡂키���ł����A���N�̓R���i�E�B���X�����Ǒ嗬�s�̕s���ɂ�������u���������Ă��܂��B3���͔N�x���̑�ȍs������������
��A�ی�҂̕��X�ɂ͍���ǂ��Ȃ邱�Ƃ��Ɨ��������Ȃ��l�q�������܂��B�Ђ悱�ۈ牀�Ƃ��ẮA�c��1�������q�ǂ������ɂƂ��čőP�̎����߂����Ă��炢�����Ɗ���Ă��܂����A
�ڂɌ����Ȃ��E�B���X�����肾���ɁA�Ή���ɂ��Ă͎��Ȕ��f�łȂ����≡�l�s�̎w���ɏ]���ق��Ȃ��ƍl���܂��B�吨���W���ۈ牀�ł����炻�ꂼ��Ɋ��o���Ⴂ�A����̑Ή��ɂ�
���đS���ɉ������Ă��������͖̂������Ǝv���܂����A�Ђ悱�ۈ牀�̎�l���́A1���̑啔���������ʼn߂����Ă���q�ǂ������ł���A�q�ǂ������ɂƂ��Ăǂ��Ȃ̂��A����`�ɂ�
�Ĕ��f�������Ƃ����ۈ�҂̋C�����͂������������������Ǝv���܂��B
�@�@�q�ǂ��������ۈ牀�ł̂��܂��܂ȏ�ʂŁA��l�����̎v�f���Ċy�����������Ă��邩�A�F�B�Ɗւ�肠���Ȃ������Ă��邩�A���̂��Ƃ��厖�Ȃ̂��Ǝv���Ă��܂��B
�@�@��N�̉Ĉȗ��A�G���g�����X�ɓ���̕ۈ畗�i�ʐ^���f�����Ă��܂����A����͕ی�҂Ɏq�ǂ������̏���Ȃ�����̂܂܂̈炿�̎p�����Ă����������Ƃ�ړI�Ƃ��Ă��܂��B�l�� �����邽�߂ɕ\�����点��̂łȂ��A�q�ǂ����m�̐��E�̒��ŁA�f���Ȋ������J�Ԃ����Ă���Ƃ����ۈ�m�̊����ŃV���b�^�[�`�����X�Ƃ��đ��������̂ł��B�����o���ɏ����ꂽ ���t�𖡂킢�Ȃ���A�F�B�Ƃ̊W�Â���ɗ��ł���q�ǂ��������Ĕ������Ă���������Ǝv���܂��B
�@�@���ꂼ�ꂪ���s�����Ĉꍏ�������R���i�E�B���X�̗��s���I�����Ă����Ƃ����ł��ˁB�����āA�V�N�x4���ɂ͐V���������}������āA�����̕ۈ牀�����ɖ߂�邱�Ƃ�ؖ]�� �Ă��܂��B���N�x�����낢��ȏo����������܂������A�����͂����������肪�Ƃ��������܂����B�@�@�@�@�@�@
�@�@�����炮�ݕی�҂̕��ɂ͒����ԁA�s�}�Ђ悱�ۈ牀�̉^�c�ɂ����͂����������肪�Ƃ��������܂����B�s�\���ł͂���܂������A�d��Ȏ��̂Ȃ��傫���������đ�������邱�Ƃ� �E���ꓯ���g���Ă���܂��B�̂���킸���ȓ��X���q�ǂ������ƂƂ��ɏ[���������ԂƂ������Ǝv���܂��B�Ō�̓��܂ł�낵�����肢�������܂��B
��2�����i2020�N2��3���j
�@�@���̂Ƃ���~�Ƃ͎v���Ȃ��g���ȓ����Â��A�q�ǂ������͉��O�ł̗V�т����\���Ă��܂��B2���͕ʖ��A�@���Ƃ��������̂��ꂢ�Ȋ������N�Ԃōł����������ł��B�\��ł͍��N�� �������ɂ₩�悤�ł����A����ł��̂��₳�Ȃ��Ō��N���ʼn߂����܂��傤�B
�@�@�_�ސ쌧�Ɖ��l�s����V�^�R���i�E�B���X���u�w�芴���ǂ���ь��u�����ǁv�Ɏw�肷��|�A���m�˗������͂��܂����B���A�ۈ牀�ł͊������ݒ�����C���t���G���U�����s���Ă� ��̂ŁA����Ɏ�A�������Ȃǂ̊�{�I�ȗ\�h����������肵�ď��z���Ă����܂��傤�B�}�X�N���s�����Ă���悤�ł����z�Ŏ���ł������ł���ˁB
�@�@�����A�ʋ̎ԑ�����^���X�g�����̐A�͂Ɏ{���Ă���d���������܂����B���A�A���ۂɂ͂��炫��ƋP���Ė��͓I�Ȍi�F�ł������A���̌��̒��Ō���i�F�͔�����Ă��Ă��Ȃ� �M���b�v������܂����B���H�ۂ̊X�H���̍����ɐA�����Ă���p���W�[�͂���Ȃ�ɂ��킢�炵���炢�đ��݊�������A�X�͍ʂƂ�ǂ肾�ȂƊ����܂����B
�@�@2���͂����Ƃ����Ԃɉ߂��āA�N�x����3���ɂȂ�܂��B�����炮�݂ł͂Ђ悱�ۈ牀�ň�����q�ǂ��������߂����Ō�̎��ɂȂ�܂��B�ŋ߁A�����炮�݂̎q�ǂ������̗l�q������ ���ς���Ă��Ă���̂́A�ނ�Ȃ�ɑ������Ă������̎₵���������Ă���̂ł��傤�B�ی�҂̕��ɂ�����Ȏq�ǂ������̑z���Ɋ��Y���Ă���������Ǝv���܂��B�@
�@�@�Ђ悱�ۈ牀��4���ɐi�����ĕۈ玺��S�C���ς���Ă��A���������ς��Ă��܂��Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A����Ă���ۈ�m�����������Ȃ���A����܂ł̕ۈ�Ƃ̘A�������ɂ��� �A�q�ǂ������̏Ί炪�L�����炵���l���Ă����܂��B�q�ǂ��������������̂т̂тƋ����Ȃ��A�����ɂȂ�邱�Ƃ������o���ėF�B�Ɗy���݂Ȃ���V�ׂ��炵�A�ی�҂̕������S ���ē������炵��T���ĐV�N�x�̏�����i�߂܂��B
��1�����i2020�N1��6���j
�@�@�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��B�N���N�n�͓V��Ɍb�܂�܂������A�ǂ̂悤�ɉ߂�����܂������B���̊E�G�ł͐��ꒅ�p���������������炵�����قǂقǂɐÂ��Ɋ����܂����B��N�͓V�c���ʂō����������A�����̏j���������Ȃ�Ɩ��ɂ���Ă̓V�t�g���������G�������悤�ł��B���č��N�͂��悢��I�����s�b�N�J�Âł��̂ŁA���N�x�̔N�Ԍv����ǂ̂悤�ɂ��邩�v�Ă��Ă���Ƃ���ł��B�ۈ牀�͗l�X�ȓ������̕ی�҂̂��q���������Ă���̂ŁA�ی�ҕ��S�����Ȃ��悤�Ɍv�悵�Ă͂���̂ł����A����ł����ׂĂ̕ی�҂̖����͓���Ȃ��Ă����Ǝ������܂��B�@�ۈ牀�Ƃ��Ă͕ی�҂̊F����ɂ͎q�ǂ������̒��ɐ�߂�ۈ牀�����̏d�݂𐄂��ʂ�A�q�ǂ��Ƌ������A�Ƃ��Ɋւ�邱�ƂŊy����ł���������A�Ǝv���܂��B���Ƃ������ł����Ă��q�ǂ��͕ۈ牀�̓��X�ɗl�X�Ȃ��ƂŊ����āA�v�l�����グ�Ă����܂��B�c���ɂȂ茾�t���B�҂ɂȂ��Ă���̔����Ɂu���[����ȕ��Ɋ����Ă����v�Ƌ������Ƃ�����܂��B�c�����Ɍ�����悤�ɂȂ�l�X�Ȏq�ǂ��̎p�́A���������班�����ςݏd�˂��Ă��Ă���̂ŁA1��1�����ƂĂ���Ȍo���̐ςݏd�˂ł��B
�@�@�ߘa2�N�͉₩�ōQ���������N�ɂȂ�\�������܂����A��@�Ǘ���O���ɒu���Ȃ�����ی�҂ƈꏏ�ɂ�������Ǝq��āE�ۈ���y����ł�������Ɗ���Ă��܂��B
��12�����i2019�N12��2���j
�@�@���N�x�����A�O�Ύ��҂�҂悮�݂͂V������̃X�^�[�g�ł̂�т�A�������Ƃ��Ă��܂������A���X�ɓ������Ă����̂ŁA�P�P���ɂ͂Q�O����������ς��ɂȂ�A�G���g�����X�� �͖����傫�ȋ��������������Ă���悤�ɂȂ�܂����B
�@�@���̃N���X�ɉ����̑��}�ŗ�����ی�҂̒��ɂ͐Ԃ�����܂��\��̕������l�����������邵�A�T�l�Z���S�l�Z��̉��������āA�R�l�Z��͒������Ȃ��̂ŁA�Ђ悱�ۈ牀 �ɂ��邩����́A�u���q���v�Ƃ������t���؎��Ɋ������Ȃ��C�����܂��B����ǁA���ۂɂ͓s�}��ɂ����q���̔g�͊Ă��āA������ꂵ�Ă���ۈ牀������悤�ł��B�V���� �͌����J���Ȃ̐l�����ԓ��v�ɂ��ƍ��N�A�P�`�X���ɐ��܂ꂽ�q�ǂ��̐��U�V���R�W�O�O�l�ō�N�����ɔ�ׂĂT�D�U���̌����A�N�ԏo�����͂T���ȏ�̌����ƂȂ錩���݂ŁA�P�X�W �X�N�ȗ��R�O�N�Ԃ�̑啝���ƂȂ肻�����Ƃ������Ƃł��B
�@�@����A�����s�҂ɂ��Ă͕ی�҂ɂ��s�҂ŖS���Ȃ������q����ɂ��ĂȂǗl�X�ȕɋ���ɂ߂���������Ǝv���܂����A���̂P�O�N�Ŋm���Ɍ������Ă��܂��B�s�Җh�~�@�ɂ�� �Z���̒ʍ��`�����K�肳��ċs�҂ɂ��Ă̊S���[�܂������Ƃ������A�q��Ă̊��������������A�i�����A�e�̐g�̓I�A���_�I�A�Љ�I�ȍ���ȂǗl�X�ȗv��������Ƃ������� �ł��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�ۈ牀�ł͖����q�ǂ������̂͂���������̃p���[�Ɉ��|����܂����A����Ȓ��ł��q�ǂ��������悭���Ȃ���A�����ȕω������������Ȃ��悤�ɂ��Ă��������ƍl���܂��B�e �S�Ƃ��Ďq�ǂ��Ɉ��ׂȏ�����ۏႵ�����A���悢�l���̂��߂ɂ��������Ɗ肤�͓̂��R�Ȃ���A��Ȃ��Ƃ́A�u���ƂȂ̍s�ׂ����ƂȂ̑��̍l����Ӑ}�Ŕ��f����̂łȂ��A�q �ǂ��̑��ɗ����āA�q�ǂ����g����ɂƊ����Ă��邩�ǂ����Ŕ��f���邱�Ɓv�ƌ����Ă��܂��B
�@�@�ۈ��i�߂邤���ŁA�������ۈ�҂��q�ǂ��Ɗւ�钆�łӂ��킵���Ȃ����������邩�U��Ԃ�A�Ƃ��Ƃ�q�ǂ�������Ă�����ۈ�ҏW�c�ł��肽���Ǝv���܂��B
��11�����i2019�N11��1���j
�@�@��^�䕗�ɂR����ꂽ���{�B���X�Őr��Ȕ�Q���y�ڂ��A�܂��C���t���̕�������̍Č��̂߂ǂ������Ȃ������吨�ł��B�P�P���ɂȂ�A�����Ƃ����ɂӂ��킵���}�Ɋ� ��������Ă��܂����B���ʼn߂������̐g�ɂ͌������ł��ˁB�Г�͓ˑR�N����Ƃ����܂����A�������Ȃ����X�ދ��Ǝv������킪�M�d�Ȃ��ƂɎv���܂��B
�@�@�����͕ۈ牀�̍s���͂���܂��A�j���������̂ŋߗׂł͗l�X�ȍÂ�������A�Ƒ��Ŋy���ދ@��������Ƃł��傤�B�V�C�Ɍb�܂�āA�H�i�ł���Ƃ����ł��ˁB�ۈ牀�� �͍��A�h���O���₵���̎��W�߂ɖ����ł��B
�@�@�^����͋�͗l�Ƃɂ�߂����łЂ�Ђ₵�Ȃ���̊J�Âł����B������肨�ٓ��̗p�ӂ�������o�̂����͂��肪�Ƃ��������܂����B�䕗���ʉ߂�������̕s����ȋC�ۏ̂��� �A�̈�قŎ�ڂ�Z�k���čs�Ȃ��܂������A�z�z�����A���P�[�g�W�ʂɂ���悤�ɗl�X�Ȋ��z��ӌ����܂����B�\�l�\�F�ǂ��납�P�O�O���ƒ낪�Q�W���Ă̍s���ł��̂Ŏ� ���~�ߕ��͈���ē��R�Ȃ̂��Ɗ����Ă��܂��B�����A�Ђ悱�ۈ牀�͂ǂ�ȏ�ʂł��q�ǂ������������t�����ĂłȂ��A����̈ӎv�Ŏ��g�ނ��Ƃ��ɍl���Ă���̂ŁA�ی�҂� �猩��Ǝ�ڂɂ���Ă͂܂Ƃ܂肪�Ȃ�������A���u���Ă���悤�ɂ��������邩�Ǝv���܂��B����ǁA�q�ǂ��������������Ă������ł̌o���Ƃ��āA�^����������I�_�ł͂Ȃ��P �ɒʉߓ_�ł���Ƃ���ƁA�������^����Ŕ�I�����l�X�ȋZ�ɂ���ɖ����������悤�ƈꐶ�����Ɏ��g�ގq�ǂ������̎p�͕ۈ�m�̑z���ɉ����Ă���Ă���Ɗ����Ă��܂��B
��10�����i2019�N10��1���j
�@�@���x����^�䕗�Ɍ������Đr��Ȕ�Q����A����̐�������������Č��N��Q�������ǂ��Ă�������吨���������邱�Ƃ��A��������Ă��܂��B�Ђ悱�ۈ牀�̋ߗׂł� �傫�Ȕ�Q�����ɂ��܂��A�䕗�̐ڋ߂ɔ����ă^�[�t���O���A���ɂ������Ĕ�Ԃ�����̂�����i���Œ肷��Ȃǂł��邱�Ƃ͂��Ă��܂��B����A14���䕗�ł�2�K�����瑤�f�b�L �̃e���g���j����Q������A�ی��̓K�p��\�����Ă���Ƃ���ł��B
�@�@8�N�O�̓����{��n�k�̂Ƃ��́A���H�ɖʂ��Đݒu���Ă����A�C�r�[�̗��܂������[�o�[��A�����`���[���O��2�K�f�b�L�̃��[�o�[���傫�����˂��Ă����̂ŁA�|���ꍇ�̊댯 �����l���đ��A�P�����܂����B�{�̂͂��������ӏ����Â炵���O�ϐv�ł������A���S���ɍl���ĕۈ�ɒ��ڕK�v�łȂ����̂�����������j�ɉ����Ă̎��ł����B
�@�@�ۈ牀�͖����吨�̎q�ǂ����W���A�����Ԃ��߂����ꏊ�̂��߁A�����Ďq�ǂ������͂�����u�ЊQ��ҁv�@�Ƃ������݂ł��̂ŁA�o�������̔������K�v�Ǝv���Ă��܂��B������ ��A����Ă������őS���댯�Ȃ��Ƃɑ������Ȃ����Ƃ͕s�\�ł����A�����̐g�͎����Ŏ�邽�߂ɕK�v�Ȍo���͏d�˂Ăق����Ƃ��v���܂��B
�@�@10���ɂȂ�A�q�ǂ������͉^�����҂��]��ł���l�q�ł��B�I�����s�b�N��O�r�[�ł̏����̗l�q���s�u�ŗ���Ă���̂����Ă���̂ł��傤�B�q�ǂ������͂�������꒚�O�� �A�X���[�g�C���ł��B�����������甭�������t�ŁA�q�ǂ��������m�Ő���オ���Ă��܂��B���Ƃł��^����̂��Ƃ�b��ɂ��āA���M�������ĉ^����ɗՂ߂�悤�ɁA�̂������Ƃ� �y������{�������Ă����Ă��������B�@�@
��9�����i2019�N9��2���j
�@�@�߂܂��邵���V��̕ω��ɉċx�݂̌v�悪�܂܂Ȃ�Ȃ��������ƒ�������Ƃ͎v���܂����A���q����Ƃ̂����Ƃ͈�������Ԃ�o�����ł����ł��傤���B�ۈ牀�̐E����������� �ŋx�ɂ�����ċA�Ȃ◷�s���y����Ń��t���b�V�����܂����B���肪�Ƃ��������܂����B
�@�@8�����͕ۈ���M���Ǒ�ɒǂ�ꂽ��������܂����B��[�����܂��g�p���Ȃ��犷�C�ɂ��C��t���āA������V�����[�����܂߂ɍs���܂����B����ł��������Ɏq�ǂ���������J�� ���܂����悤�Œ��ӂ��������Ȃ������̍��A��N��𒆐S�ɔ��M��ݒ���Q���N�����q�ǂ��������Ă��Ă��܂��B���ƂȂ��̒��̊Ǘ����������肵�Đ����R�̏H�ɔ����Ă��������� ���ł��B
�@�@�Ă̊ԁA���N�̃I�����s�b�N��p�������s�b�N���Ԃ̔M���Ǒ�̘b��Ŏ�������ł������A�ď�̎q�ǂ������̋��ꏊ�ɂ��Ă͂قƂ�ǎ��グ���Ă��Ȃ����Ƃ��c�O�ł��B �������g�킸�ɐS�n�悭���p�ł���Ƃ���E�E�E�}���ق⎙���فA�n��Z���^�[�Ȃǂ����C���ӂ��q�ǂ��������W���ɂ͋������e���ł��B�܂��A�ۈ牀�ł͎q�ǂ��������ď������ ��悤�ɏo�������̔z�������ĉ߂����Ă��܂����A�Ƃɂ�����c���͂ǂ��ɂ��s���Ƃ��낪�Ȃ��A�ǂ̂悤�ɉ߂����Ă���̂ł��傤�B��q�Ŏϋl�܂��Ă��܂��̂��A���������Ă��� �q�ǂ��̋s�҂Ɩ����łȂ��Ɗ����܂��B�q��Ďx���Z���^�[����ϊ撣���Ă��������Ă��܂����A�ǂ��t���Ȃ��̂�����ł��B�ۈ牀���A�q�ǂ���l��l�ɖL���Ȏ��ԂƋC�z�肪�K�v�� �Ȃ��ʂ������Ă��Ďl�ꔪ�ꂵ�Ă��܂��B����ō��⎩���̂����z�̕⏕�����o���ĐV�݂��悤�Ƃ�����Ɨ��ۈ牀���H���r���œڍ������Ƃ����j���[�X�����傭���傭�ڂɂ��܂��� �A�������x�������M�d�Ȑŋ��͂�����ƗL���Ɋ������Ăق����Ɗ肢�܂��B
��8�����i2019�N8��1���j
�@�@����A�ċx�݂����ė]���Ă��鑷�ɂ������Ă�����č`�k���}�ŃA�j�����ς܂����B�ċx�݂Ƃ͂����C�V�C���͂����肹�������ӕ���o�Ă����̂ŋߏ�ʼnJ���~���Ă����v�Ȃ� ����A�Ƃ������Ƃʼn��\�N�Ԃ肩�ł����B
�@�@���s�ŋN�������Ύ����̕ŃA�j�������E����Ȋ����Ă��邱�Ƃ�m��A�܂��A��l���������̉Ќ����ڑO�ɂ��ĉԑ���������ė܂𗬂��p�����āA�����̑S���m��Ȃ����E �������C���������Ƃ��A�����^���R�̈�ł��B
�@�@��������ł��邾�낤�Ɗo�債�Ă��������̂̎v���̊O�A���w���͂قƂ�nj������炸�A���Z������w�����炢�̒j�q���������Ă��ċ����܂����B�A�j���͎q�ǂ���������̂� �v���Ă����̂ŁA�������ǂꂾ������ɂ��čs���Ă��Ȃ��̂��A�������ɋ���������Ǝ������܂����B�c���ł����X�}�z�𑀍삷�鎞��Ȃ̂ł�����A������m��Ȃ��ł͎q�ǂ����� �����ڂ��Ȃ��ł��ˁB
�@�@�Ȃ܂�ɂ͑����̎q�ǂ�������ی�҂̕����W�܂��Ċy����ł��������āA���ƂȂP�T�V�l�A�q�ǂ��P�T�W�l�̎Q���ł����B���O������ی�҃R�[�i�[�̊��E�^�c�A�܂��A�� ���̂��ƂȂ���e���g�݉c�Ȃǂ��肪�Ƃ��������܂����B���N�͍�N�܂ł̗���ƕς��āA�O�p�����ł̃I�[�v�j���O�̌�A�q�ǂ��̗V�уR�[�i�[��ی�Ҏ�ẪR�[�i�[�ƕ��s���� �H�����Ԃ�ݒ肵�܂����B�I���̂P���Ԃ��݂�Ȃłǂ�ɏW�����ėV��ł��炤�Ƃ����ӌ��ł������A�����s���ō����������Ƃ����l�т��܂��B�J���[��a�a�p���ی�җL�u�̕� �̂����ӂŒł��Ă��邱�ƂȂ̂ŁA���N�͍��܂łɌo���̂Ȃ����X�ɂ��ϋɓI�Ɋւ���Ă��������A���y�����A��肨�����������オ���Ē�������Ǝv���܂��B�����u�݂�Ȃ� �n��グ��s���v�ł��邱�Ƃ��Ђ悱�ۈ牀�炵�����Ǝv���܂��B
�@�@�Ȃ܂�Ɋւ��ẴA���P�[�g�͏W��o������A�F����ɂ��`�����܂��B�Ȃ�ׂ����v�]�ɂ������ł���Ƃ͎v���܂����A���e�ɂ���Ă͕ی�҂ƕۈ�҂̋����ōs�����Ƃ��x �X�g�ł��邱�Ƃ����X����悤�ł��̂ŁA���̍ۂɂ͊F����Ɏ���A�݂�Ȃ���������Ȃ܂�ɂ������ł��B
��7�����i2019�N7��1���j
�@�@���������J�̓��������A�A�M���o���q�ǂ��������Ă��܂��B��������͕ۈ牀�ɓ��������Ƃ���A�a�C����Ŏd�����x�ޓ��X�������Ă���ی�҂̕��X���������܂��B�M�ʼn����� �x�݁A����Ɖ������ēo�������̂ɐE��ɂ��ĊԂ��Ȃ��A�ۈ牀���炨�}���̗v���̓d�b�E�E�E�B�q�ǂ��̂��Ƃ͓��R�S�z�����ǁA�d�����R�ς��Ă��Ă����������A���������� �Ȃ��A�A�t�A�~���[�T�|�[�g�Ȃǂɗ��ނȓx���ꂼ��Ɏ��s�����Ă��܂����������Əő��������܂��ˁB
�@�@�u�W�c�ɓ��肽�Ă͕a�C���������Ǐ����Â̂�����ď�v�ɂȂ�܂���v�Ɨ�܂��Ă��܂����A��ς��낤�ȂƎv���܂��B�ۈ牀�ł͊�����Ƃ��ăg�C���A���������h�A�̎� ����ȂǁA�s���[���b�N�X�A�A���R�[���ł̂��܂߂ȏ��łɗ��ӂ��A���������̓��{�̌����������ɂ̓G�A�R���ł̉��x���x�̊Ǘ���K�������V�����[�Ŋ��𗬂��A����K���ɊJ���ĕ� �ʂ���ǂ�����ȂǑΉ����Ă��܂����A��{�I�ɂ͉ď�ɑ̗͂��ێ�����ɂ́A��J�����߂Ȃ����ƁA��Ԑ�������������Ƃ邱�Ƃ��Ǝv���܂��B�₦�����Ȃ����x�ɃG�A�R�����g���� �����悤�ł��B�ۈ牀�ł̌ߐ����ɂ��G�A�R�����g�p���Ă��܂��B�V���͎q�ǂ��������y���݂ɂ��Ă���Ȃ܂肪����܂��ۈ牀�ŗp�ӂ����J���[��Ă�����H�ׂȂ���A�܂��A�� �낢��ȃQ�[����ǂ���y���݂Ȃ���A���̉Ƒ��̕���ۈ�҂Ƃ̌𗬂��y����ł�����������Ǝv���܂��B����̃A���P�[�g�ł͕ی�҂̑������ۈ�҂Ƃ̃R�~���j�P�[�V������ �]��ł��܂����B�A�A�A�s���̐܂͕ۈ�҂Ƃ����ЋC�y�ɂ��b�����������B�܂��A�J���ȗ��A���N�Q���ڂ̖~�x��ɂ̓��[���[�ނ���{�����e�B�A�Ƃ��ďo�X���͂��Ă��܂��̂ł����� ���y����ł�����������Ǝv���܂��B
��6�����i2019�N6��3���j
�@�@�T���͊e�n�ő�J��ҏ��Ɍ������āA�̂Ɉٕς������������吨���炵�����Ƃł��傤�B�����͔~�J�ɓ���̂ł��Ƃ��ƁA���Ƃ��Ƃ̖���������Ă���̂��ƗJ�T�ȋC���ɂȂ肪 ���ł����A�ۈ牀�̂��ߏ��̂���ɂ̓A�W�T�C�����ꂢ�ɍ炢�Ă��Ă��̎����Ȃ�ł͂̊y���݂�����܂��ˁB
�@�@���s�ŋN�����X�N�[���o�X�ł̎����ɂ��āATV��V���Ȃǂŗl�X�ɕ���Ă��܂����A�����N����̎q�ǂ��A���A�܂��v��A���q�Əd�ˍ��킹�ē��{�����߂��݂╮��A��� ����Ȃ��v���ɕ�܂�Ă���̂́A��������ɉԂ�������A������킹�ė܂��Ă���l�X���r��Ȃ����Ƃ�������炩�ł��B
�@�@�u�����������Ƃ����Ă��Ȃ��̂ɂȂ�����Ȗڂɂ����̂��H�v�A�u�Ɛl�͂Ȃ�����قǂ̎c�s�Ȕƍ߂�Ƃ��Ɏ������̂��H�v,�ƍߐS���w�҂�_�Ȉ�A�h�Ƃ�q�ǂ��̈��S�ɂ��Ă̌� ���҂��W���A�l�X�Ȋp�x���炱�̎����ɂ��ĉ𖾂��悤�Ƃ��Ă��܂��B�܂��A���̎����ɂ��Ă̒̕��ɂ́A�����������s�o�Z���֘A���邩�̂悤�Ȕ���������܂����A���f�B �A�̉e���͂��l����ƐT�d���Ɍ�����Ɗ뜜���܂��B�d�厖���̔w��ɂ͈꒩��[�ɉ𖾂ł��Ȃ��傫�ȃu���b�N�z�[�������݂���悤�ŕs���ɂȂ�܂����A���Ƃ����āA���������ɂ� �̂̂��Ă������ł͔\������܂���ˁB
�@�@�����������ɂł��邱�Ƃ͕ۈ牀�ɖ����ʂ��ė���q�ǂ������₻�̌Z�킽���������Ɋ������܂�Ȃ��悤�ɁA�܂��A�n��̎q�ǂ����������C�ɂ����Ď��ӂł̏���`�������A�� �ƂȂ����͂Ƃ��ɍl���Ȃ���s�����܂��傤�B�ЂƂ�ő傫�Ȏ��͏o���Ȃ�����ǁA�����ȗ͂��W�܂�Α傫�Ȕƍߗ}�~�̈ꗃ�͒S����̂��Ǝv���܂��B
��5�����i2019�N5��7���j
�@�@�V�N�x�ɂȂ��ĂЂƌ����߂��܂����B�q�ǂ������͐i���������̕ω��ɂ��A��l��l�����ꂼ��̂����ŏ��z������悤�ŁA�q�ǂ����Ă������ȁA�Ƃ��炽�߂Ďv���܂��B���N�͓V�c�ވʂɊ֘A���ĕۈ牀�͂X�A�x�̒������x�݂����������܂����B�x�ɂ̎��Ȃ��������炵�āA���q����̗a����ɋꗶ���ꂽ���ƂƎv���܂��B�����͂��肪�Ƃ��������܂����B
�@�@�S���Q�V���i�y�j�ɂЂ悱�܂���s���܂����B���������ł������A��������n��̎q�ǂ��������吨�Q�����čĉ����э����Ă��܂����B���ɐV1�N���̎q�ǂ�������1�����Ԃ�̕ۈ牀�Ɉ��S�����l�q�ł����B�q�ǂ������ɂƂ��ĕۈ牀�������ς�炸�u�����ɂ��邱�Ɓv�̑������������Ǝ~�߂˂A�Ɗ����܂����B���O�Ƀ|�X�^�[�⍩���̃v���[�g�Â���A���[���[�̏����Ȃǂ̂����͂��肪�Ƃ��������܂����B�܂��A������������^�[�t��������Ă�������������������A�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B���̑��ɂ��Ԍ˃T�b�V�̏C�����X���Ă��������܂����B�d�˂Ċ��Ӑ\���グ�܂��B���i�A�댯�ȂƂ����s��ȂƂ���̎蒼�������Ă������ł���Ȃ���A�������Ă��邱�Ƃ��������Ƃɉ��߂ċC�Â�����܂����B���̂₯���ɂȂ肩�˂Ȃ��̂ł��܂߂ɓ_������悤�ɓw�߂܂��B
�@�@���N�̓^�[�t����ɕی�҂̕��̎Q�������Ȃ��A�ۈ牀���N�x����̑��Z���ɂ��܂��ĕی�҂̊F����ւ̌Ăт���������Ȃ������Ɣ��Ȃ��Ă���܂��B����A�V��20���i�y�j�ɂ͉Ă܂�i�ǂ�j��\�肵�Ă��܂��B�܂��A�����[���ɂ͂�������̍��e����\�肵�Ă��܂��̂ŁA���̐߂ɂ͍���o���Ȃ�������������������Ђ��Ђ��Q�������肢�������ł��B�s���̎��͕��i������킹����A�b�����肷�邱�Ƃ̂Ȃ����ƃR�~���j�P�[�V�������Ƃ�悢�@��ɂȂ�Ǝv���܂��B���Ԃ̓s�������悤�ł�����A�����i�K����ł����킹�Ȃǂɂ��Q�悵�Ă���������ƁA�u�݂�Ȃł������s���v�ɂȂ�A�y�������{�����邱�ƊԈႢ�Ȃ��I�ł��B�ۈ牀�̑��}�����łȂ��u�q�ǂ��������ł��q�ǂ��炵�����鎞�ԂƋ�ԁv�ɂ��ƂȂ������X�ɉ�����ĎQ�悵�Ă�������悤�Ɋ���Ă��܂��B
��4�����i2019�N4��1���j
�@�@�Ђ悱�ۈ牀17�N�ڂ̏t�A�V�N�x�̕ۈ炪�n�܂�܂����B���a���Ɍ����Ȃ�u�Z�u���e�B�[���̏t�v�ł��B�����Ƃ��߂��悤�Ȃ������Ƃ��N��Ƃ����ł��ˁB�V����������ڑO�ɁA���������q�ǂ��������݉����Ă���q�ǂ����������A���N���N�ƃn���n���̍��������C���ŁA���ɕs����ɂȂ邱�Ƃ����邩�Ǝv���܂����g����������Ă����Ă��������ˁB
�@�@����A�ސE����E���A���E����E���A�V�����N���X�S�C�̂��m�点�����܂����B�N�x���ւ�邽�тɌJ��Ԃ��l���ٓ��ɂ��Ă͑O�N�̉Ă̏I��肩�猟�����n�߂܂��B���ɕۈ珊�͏����̑����E��ł��̂ŁA���߂ł����o�����������A���̂��Ƃ�����ɓ���Ȃ��玟�N�x�̑̐����l���܂��B���̍��́u���������v�v�Ƃ������t�����s��ɂȂ��Ă��܂����A�Ђ悱�ۈ牀�ł͈ȑO����l���̐ߖڂƂȂ�l�X�ȏo�����̂��тɁA������s���������Ȃ��œ�����E�ꕗ�y������Ă�����Ǝv���Ȃ���̗p���������Ă��܂��B���N�x���ۈ�m�s���������Ƃ���l�X�ȏɂ��đ����̕����钆�ŁA�����̐E�����̗p���ď[�������̐��ŐV�N�x�����������邱�Ƃ��A�Ђ悱�ۈ牀�̂Ƃ��߂��̈�ɂȂ��Ă���̂�������܂���ˁB
�@�@�ۈ牀�ł̕ۈ�����ƒ�ł̈玙�����ꂼ��̌�������A�����ƒZ���͕\���ł����A��l��l�̎q�ǂ���������Ŏx���Ă���钇�ԂƂ��ƂȂ͑����قǂ����ł��B���N�x���A�����苃������A���낢��Ȃ��Ƃ��N����A���ɂ͕s���ɂȂ��邱�Ƃ����邩������܂��A���ߍ��܂��ɗ����ɘb�������ĉ������邱�Ƃ��ۈ�̉��P�Ǝq�ǂ������̈��S�ɂȂ���Ǝv���܂��B�S�z���Ȃǂ���܂����牓���Ȃ������k���������B���N�x����낵�����肢���܂��B
��3�����i2019�N3��1���j
�@�@���悢��3���ɂȂ葲����i���A�܂��A�ق��̕ۈ牀�A�c�t���ւ̓]���Ȃǎq�ǂ������ɂƂ��đ傫�����������ω����鎞���ɂȂ�܂����B�ۈ�҂��N�x���őސE����ҁA���E����҂�����܂��̂ŁA�l�I�Ȋ����傫���ς���
���B�q�ǂ������ɂƂ��Ă͖����ʂ��Ē������Ԃ��߂����ė����Ƃ͂����A���������Ȃ������ƂȂ肪���ł����A����̂��ƂȂ͂ǂ�����ƍ\����4������̐����Ɋ��҂������ď��z���܂��傤�B
�@�@�ۈ�m�����͂��̈�N�Ԃ�U��Ԃ��āA�q�ǂ������̈���Ă��������l��l�����z���Ă������B�̐ߖڂ����ǂ��Ď��̒S�C�ւƂȂ��鏀����i�߂Ă��܂��B�ۈ牀�͗c�t���⏬�w�Z�̂悤�Ɋ����̋x���͂Ȃ��̂œ���̕ۈ�Ǝ��N�x�̏����Ƃ���s���Ă����A��N�ōł��Z���������ɂȂ�܂��B�q�ǂ��������l�A�Ђ悱�ۈ牀�̕ۈ�m���������܂��܂Ȍ��̎�����œ��ӂȂ��Ƃ����l�Ȃ̂ŁA�C�����S��}��Ȃ���V�N�x������i�߂Ă���Ƃ���ł��B
�@
�@�@���͂Ƃ�����A�u���N�x�����낢��Ȃ��Ƃ�����������ǁA�݂�ȁA�Ђ悱�̎q�炵���̂т̂тƈ���Ă��ꂽ�ˁv�ƕی�҂̊F����Ɗ�э�����悤�Ɏc��̓��X���߂��������Ɗ���Ă��܂��B�����͂��肪�Ƃ��������܂����B
�@
�@�@�����炮�ݕی�҂̕��ɂ́A�����ԁA�s�}�Ђ悱�ۈ牀�̉^�c�ɂ����͂����������肪�Ƃ��������܂����B�͕s���̂��ߕs�\���ȂƂ���𑽂��c���Ȃ���ł͂���܂����A�d��ȉ��䂪�Ȃ����q����������邱�ƂɐE���ꓯ�ق��ƈ��g���Ă���܂��B����͏��w�Z�̐搶���Ƀo�g���^�b�`���Ēn��̒��ł��q����̐��������Ă��������Ǝv���܂��B�c��킸���ł����A���܂łƓ����悤�ɁA�[���������X���q�ǂ������Ɖ߂����Ă��������Ǝv���Ă���܂��̂ōŌ�̓��܂ł�낵�����肢�������܂��B
��2�����i2019�N2��1���j
�@�@2���́u�ߕ��v��u�݂�Ȃ̂킭�킭�X�e�[�W�v�Ƃ�������Ƃ͈قȂ�o�����˂炢�ɂ����s��������܂��B�ߕ��ɂ͋S�����đ�\�ꂷ��̂ŁA���Ƃ̐���s�����킩���Ă��邭���炮�݂ł����|����q�����܂��B����݂ł͋��N�̂��Ƃ��͂�����Ɗo���Ă��āA�u���������I�j�����ˁ[�v�ƃr�r���Ă��܂����B�����S������Ƃ����͂��Ȏq���勃�����ĕۈ�m�ɂ����݂��Ă���T��ŁA���ƂȂ��߂̎q���F�B�������A�S�Ɋ��R�Ɨ����������Ď�Â���̓��𓊂����Ă�����i���悭�����܂��B�F�B�W�Ŏq�ǂ������̈ӊO�Ȉ�ʂ�������s���ł��B
�@�@�u�݂�Ȃ̂킭�킭�X�e�[�W�v�ł͎q�ǂ������̌ւ炵���ɉ̂��l�q�ɁA��l��l�̐����Ԃ�͂������ł������Ԃɍ��킹�ĉ������d�グ��Ƃ����͂̈炿�����邱�Ƃ��ł��܂��B�吺���o���ĂǂȂ�̂ł͂Ȃ��A���t�̃s�A�m�̉��F�ɍ��킹�ď�i���l���Ȃ���̂��悤�ɁA���g�~�b�N�̐搶�ɋ����Ă��������Ă���̂ł݂�Ȑ^���ł��B�����Ɏ���q�ǂ������̕��݂��v�������ׂȂ���ςāA�����Ă���������Ǝv���܂��B���g�~�b�N�̌�͗]�C���y����Ŏq�ǂ������̊Ԃ��玩�R�ɉ̐�������o�āA�]��ł����u�̐��̗����ۈ玺�v�ɋ߂Â��Ă���ȂƂ��ꂵ�������Ă��܂��B
�@�@�����炮�݂͏����̐搶�ɗ��Ă��������Č��Ɩn�ƖѕM���g���Ĕ����ɏ�������A���p�̐搶�ɂ͊G�M�ƊG�̋���g���ĕ`����w�����Ă��������Ă��܂��B����I�Ɏ��R�z���ɗV�сi�n���`����܂߂āj�ɔM�����邱�Ƃ͎q�ǂ�����ɂȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł����A�ォ�狳�����ނƂ����̂łȂ��A�傫�������Ȃ�|�p�̓�������`�������Ǝv���Ă̂��Ƃł��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
��1�����i2019�N1��4���j
�@�@�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��B
�@�@�U���Ԃ̒������x�݂����肪�Ƃ��������܂����B�V��Ɍb�܂ꂽ�������ł����ˁB�E���͋A�Ȃ�����A�Ƒ��ł������߂�������ƕ��i�ł��Ȃ����Ƃ��y����ŐV�����N�̏��߂��߂����܂����B���悢��ۈ炪�n�܂�A�q�ǂ������̌��C�����ς��Ȋ�����č��N���y�������Ƃ����ς��ȔN�ɂ������Ɗ���Ă��܂��B�N���N�n�ɏA�J����Ă����ی�҂̕����吨���炵�����ƂƎv���܂��B�d�˂Ă���\���グ�܂��B
�@�@�N���N�n��ۈ牀���痣��ĉ߂������q�ǂ������́A����܂łƂ͈�����\��������邱�Ƃ�����܂��B�������Ƃ����Ƒ��Ƃ̎��Ԃ������Ղ�Ɩ�����ď����ς̂悤�Ȃ��́A����ΉƑ��̒��ł̈ʒu���m�F�����̂��ȂƊ����܂��B�ۈ牀�œ��N��̗F�B�Ɖ߂������Ԃ͒����̂ŁA���݂��ɉe���������Ȃ������Ă��܂����A����ȏ�ɉƒ�ł̎��Ԃ�Ƒ��̊ւ肪�q�ǂ������ɗ^����e���̑傫���������܂��B�q�ǂ������₩�ȕ\��ł��邽�߂ɂ͎���̂��ƂȂ����̋C�������������ƈ��肵�Ă��邱�Ƃ���Ȃ�A�ۈ�҂̕\������₩�ł�����悤�ȐE�ꕗ�y�ɂ��Ă����Ȃ���Ǝv���Ƃ���ł��B
�@�@�o�Ύ��A�ۈ牀�ɋ߂Â��ɂ�Ďq�ǂ������̌��C�ł̂т̂т����������ɋ����Ă��܂��B���̎q�������߂������A���{���x���邨�ƂȂɂȂ��Ă����̂��ȂƑz���Ƃ��ɁA�ۈ�Ƃ����d���ɂ܂��l�X�ȔC���ւ̐ӔC�ƁA�������炢�ɖʔ����Ɗy�����������Ă��܂��B
�@�@�V�c���ʁA���������A����ő��ŁA�c�����疳�����ȂǍ��N���߂܂��邵���Ȃ肻���ł����A�ۈ牀���q�ǂ������ɒ��ׂ��u�őP�̗��v�v�͈�A�̗���ɐU��ꂸ�ɁA��������ƒn�ɍ����Ď���Ă��������ł��B���̂��߂ɍł��K�v�Ȃ��Ƃ́A�ی�҂̊F����̂������Ƃ����͂āA�s���ȂǓ��ʂȂ��ƂłȂ����C�Ȃ������̓s�}�Ђ悱�ۈ牀�̕ۈ�����Ԃ������Ă����n���Ă������Ƃ��Ǝv���܂��B���N����낵�����肢�������܂��B�@
��12�����i2018�N12��1���j
�@�@�،͂炵1�����������ƂȂ��t�����}����͎̂���39�N�Ԃ�Ƃ̂��Ƃł��B�R�[�g�݂̋𗧂Ăđ����ɕ������܂͐l�ɂ���Ă͉f���1�V�[���ɂ��Ȃ�܂����A���N�͂܂�������قǂ̊����ɂ͑������Ă��Ȃ��̂ő̂��y�ł��ˁB�����Ƃ��A�q�ǂ������͏����낤�������낤�������̂������������ėV��Ō��C�����ς��A���������ł��B�͂Ƃۂ��ۂ��݂₤�������݂̎q�ǂ����������̎����ɂ͌��Ⴆ��قǂɈ���Ă��āA�����`���[���̃X���[�v�ŔN��̎q�ɍ������Ă�����A�ۈ�m�ɘA����Ď������ɂ��o���I����悤�ɂȂ�܂����B���N�O�ɂ͎������ɗ���Ȃ�l���m��ŋ����Ă����q�ǂ����������U���J�[�h����������Ǝ�n�����Ă���܂��B���ɗ���Ƃ��͌��t��Y���Ă���邩�ȁH
�@�@���N4�����炢�悢��c�����疳�����̑�1�e���n�܂�悤�ł��B�܂��͐�s�Ƃ��ĔN��������A����10���������ő��łɍ��킹�Ă��ׂĂ�3�Έȏ㎙�ɓK�p����悤�ł����A�܂��������肵�����͗��Ă��܂���B�Ƃ����ꋋ�H��̎�����̘b������悤�ł�����A�ۈ猻��͍������Ď����I�ɂ��X�ɔώG�ɂȂ��Ă��܂����Ƃł��傤�B
�@�@�u�q�ǂ��ɂ����鋳��������ʼnƌv�̕��S�������A���z�Ƃ��邾���̎q�ǂ���]�߂Ȃ��̂ŏ��q���̐i�s�Ɏ��~�߂�������Ȃ��v����A�܂��A�u�c������̏[�����q�ǂ��̏����I����Ɛ����̕ۏ�ɂȂ���v�Ƃ������ۓI�Ȍ������ʂ܂��ď��O���̗c������̖������ɏK�����Ƃ������Ƃł����A�ۈ牀������Ȃ��A�ۈ�m�̗��E�������A�{���Z�V���̕ۈ�m�̐�ΐ����s�����Ă�����{�̌���ɂ����Ė��������ʂ����Ăǂ���p����̂��A�s�����o���܂��B����ɋt�s����悤�ł����A�ƒ�ł������Ǝq��Ă���I�������傢�ɕ]�����ׂ����ł͂Ȃ����A�ƒ�玙�ɓ��������蓖�̏[���͍l�����Ȃ����̂��Ǝv���܂��B
��11�����i2018�N11��1���j
�@�@10�����Ɏ�����̎�Âł��邨�܂�i���ꌴ1���ڃn���E�B���E�p�[�e�B�[�j������܂����B�����͋斯�Ղ���e��ōs���ăC�x���g�����肾������ł��ˁB�V�C���ǂ����ɉƑ���F�B�ƊO�ɏo�Đg�߂ȍs�����y���ނƁA�C�������͂�ꂷ��̂ł��傤�A���o�������ɏW�����q�ǂ������̕\��݂͂�Ȋy�����ŁA��������Ƃ��Ă������Ă��܂����B�V��͑̂ƐS�̗����ɑ傫�ȉe�����y�ڂ��܂��ˁB
�@�@30���A31����TV�j���[�X�ł͏a�J�̃Z���^�[�X�ł̃n���E�B����������X�I�ɕ��Ă��܂����B����Ȍ�������������DJ�|���X�H�͂��ߑ����̌x�����x���ɂ����钆�A�g�����X��ԂɂȂ��Ė\�k�������l���������|���ɂ����y�g���b�N�ɏ�荞��ő呛�����Ă�����A�X�܂̃V���[�E�C���h���Ă���f��������Ă��܂��B���̎���ɂ���h��ɉ��������l�X�͂Ȃ����y�������ɌQ��Ă��܂��B�u�݂�ȂŖ\���Ε|���Ȃ��v�Ƃ����Ƃ���Ȃ̂ł��傤���B
�@�@TV�������̊ԂŌ��Ă��鑤�̔����͗l�X�Ȃ̂��낤�ȂƎv���A�ǂ������������n���E�B���̏�����œ��X�������Ƃ�s���Ɋ����鎩���́A���ǂ��̕����ɂ͋��������o���܂��B���Ƃ��ƁA�l�̂܂˂͂��Ȃ��������_���h���Ă��鐫���Ȃ̂ŁA�ǂ����Ă������ɌQ�W�S���Ƃ������A�R�}�[�V�����Y���ɏ悹���Ă���悤�Ɋ����Ă��܂��̂ł��B
�@�@����A���������Ō@���������A���������ŏW�߂������t�ŏĂ��āA�����������H�ׂ�A����ȓ���͂Ђ悱�ۈ牀�ɂ���Ƃ������ł͂Ȃ��ł��傤���B�N����������Ƃ�������Ƃ��Ƃ������ƂƂ͖����ȕۈ牀�ł̂��y���݂ŁA���������A�Ђ����疳�S�ɔM�X�̂������ق���q�ǂ������̕\���D���ł��B
��10�����i2018�N10��1���j
�@�@�ҏ��ɂ����������N�̉Ă�����Ǝ��܂��Ă��܂������A�䕗��H�̒��J�ɉ^������T���Ă₫�������Ă���ۈ牀�A�c�t���A���w�Z�ł��ˁB�C�ۂ̂��Ƃ͂ǂ����悤���Ȃ��̂ł�����A�u�܂��A����Ȃ��Ƃ����邳�v�ƁA�s���s�������ɕ����ʂ�A�V�ɔC���čs���܂��傤�B
�@�@�c���N���X�ł͂��̎����A�q�ǂ������͂��������[�̃A�X���[�g�C���ł��C���X�A�撣��C���X�ł��B�ۈ�m�������q�ǂ������̋C�����g���d�|���Ă���߂�����܂����A����͂���Ŏq�ǂ������̑̌����鐢�E���g�����Ă��邱�Ƃƌq�����Ă��܂��B�q�ǂ�����������撣�낤�A�`�������W���悤�Ƃ����S�ƈӗ~�͈꒩��[�ɂł���̂ł͂Ȃ��A�����̉��C�Ȃ��̌��̒��Ŏ��������͂ɔF�߂��Ă���A�Ƃ������S���������Ă�������̂ł��B
�@�@����A�v���Ԃ�̐���Ԃɒ��ԏ�ŗc���̌����������������ł����A���H��H�ׂȂ���u������������Ċy������ˁv�Ǝq�ǂ��̒e�������ɂ��܂����B�������肵����̉��ł����A���邩�A������̎q�ǂ����������݂��̋��Z���������Ȃ���蔏�q��ł��Č����������ŁA�F�B�ƕۈ�m�݂�Ȃ��y�������Ă����ʂ��A�q�ǂ������ɂƂ��ĉ����̈��S���Ɍq�����Ă���ȂƎv����o�����ł����B�傫�������Ȃ�u���a�v�𖡂���Ă���̂��ȁA�ƁB
�@�@�^����͕ۈ牀�ł͍ł��傫�ȍs���ŁA�����Ƃ��̉Ƒ����S����ꏊ�ɏW�܂��ĉ߂����܂��B�ق��̉Ƒ��ƐH�������ɂ�����A�v������������ׂ肵���肵�Ȃ���A�q�ǂ������̊撣�����p���ق߂Ă����Ă��������ˁB
�@�@�^�c�ʂł͗�N�ʂ�9�������A�ۈ�m�͂��ߑS�E���̗��N�x�̏A�J�ɂ��Ă̒����ƌl�ʒk���s���Ă��܂��B�S���I�ɕۈ�m���̕s���Ƒҋ@�����̑����������ȏł����A�Ђ悱�ۈ牀����g�ɂ��܂�鎖�Ԃ��N���邩������܂���B����܂ł������ł������u���ꂸ�A�Q�Ă��A�n���ɃR�c�R�c�Ɓv�����b�g�[�ɁA�u�q�ǂ������ɂƂ��Ĉ�ԗǂ����Ɓi�őP�̗��v�j�v��T��Ȃ���A�ۈ�^�c�𑱂��܂��B
��9�����i2018�N9��1���j
�@�@�挎�W���U���A���l�s���ǂ����N�ǂɂ��w���č�������܂����B��v�A�@�l�^�c�A�ۈ�A���H�ȂǕۈ珊�ۈ�̏d�_���ڂɂ��Ċč��ېE���S�l�������ؕ[�A�ۈ�v���L�^�A���H�Ɋւ��鏑�ޑS�ʂ��P�������Ē����m�F���܂����B���N�A��N�Ɠ�N�����ĉ��l�s���̔F�ۈ牀�ŕۈ�^�c��̕s���⎄�I���p���������̂ŁA�ו��ɂ킽���Ċč����O����ɍs����悤�ɂȂ��Ă��܂��B��������������ėV�q�ǂ�������������Ƃ̊ԐÂ��Ƀ����b�N�X���ă��Z�b�g���鎞�ɍD��Ŏg���Ă���ᔽ���̃N�b�V����������܂����i�c���̃N���X�ƃ����`���[���ɒu���Ă���ΐF�̂��̂ł��j����[�i����̎����ƌ������m�F���Ă��܂����B�Ђ悱�ۈ牀�ł͋��K�ɂ������s�ׂ͓��ɐ��m�ɂ���悤�ɐS�����Ă��܂��̂ŁA�ǂ��������Ă��s���ĂȂƂ���͂Ȃ��Ƃ�������������܂����A�ی�҂̕�����a����l�X�Ȍ����ɂ��Ă����R�A���m�ɐ��m�ɋL�����Ă��܂��B�����ۈ痿���H��A�I���c���[�X��A���F�X�q�オ��Ȍ����̎���ł����A�䏳�m�̒ʂ�A�Ђ悱�ۈ牀�ł͉�����s���ɂ܂���p�͕ی�҂���͈�ؒ������Ă��܂���B
�@�@���A���l�s����̒ʒm�ɂ��ƁA�Q�O�P�X�N�i�����R�P�N�x�j���ی�҂���̎�����ɂ��āy�ی�҂ɕ��S�����邱�Ƃ��K���ƔF�߂�����́i���[���A������A�s���Q����Ȃǁj�ɂ��Ă͎�������邱�Ƃ��o����z�Ƃ��Ă��܂����A���݂̌������J����Ђ悱�ۈ牀�ɒʂ��Ă���l�X�ȉƒ�̏���݂āA�o�������ی�҂���̎�����͏��Ȃ��������ƍl���Ă��܂��B�Ђ悱�ۈ牀�ł͑����ɔ�ׂāA�q�ǂ������̂��������V��Ȃǂ̕ۈ�ޗ��⋋�H�̐H�ޔ�Ȃǂ̎��Ɣ�ɂ͏\���Ȏx�o��ۏႵ�Ȃ���A������x�o���ɗ͗}����悤�ɓw�߂Ă��܂��B����͓��X�̕ۈ�^�c�̒��ŏo���邱�Ƃ͊O�������Ɏ��������ōs���A�傲�ƂɂȂ�O�ɏ��܂߂ɕs���ȂƂ�����C�U����A���̂ʂɂ��Ȃ��ȂǁA�����Ƃ����d���ł��̂��ł��邱�Ƃ�\�ɂ͏o�Ȃ��Ƃ���ł̐E�������̓w�͂ɕ���������������m���Ă������������Ǝv���܂��B�����e�i���X�Ȃǎq�ǂ��ɒ��ڊւ��Ȃ��d���͊O�����������ۈ玑���̏ȗ͉��ɂȂ���Ƃ����l����������Ƃ͎v���܂����A�ۈ牀�������̏�ł���Ƃ���Ȃ�A���ۑS�̂��߂ɏ��܂߂ɓ����ۈ�҂̎p�͎q�ǂ������ɋ���I���ʂ�����Ƃ��v���Ă̂��Ƃł��B
�@�@����E�ۈ���s���ɂ������ẮA��������艿�i�Ƃ��Ĕ�p���x������܂����A�ۈ珊�������債�A�ۈ�m�̏������P��̔P�o�ō������l�ꔪ��̒��A���艿�i�̐L�т͊m���ɗ}�����čs�����Ƃł��傤�B�����A������O�̂悤�ɁA���C�Ȃ��߂��Ă����ۈ牀�ł̕ۈ炪����Ƃ���Ȃ������悤�ɁA�ی�҂̊F����ɂ͉����ۈ痿�A��H��A���ނ㓙�A���ȕ��S���ׂ����̂͒�������������Ĕ[�߂Ă��������悤���͂����肢���܂��B
��8�����i2018�N8��1���j
�@�@�V�����߂ɂ͐����{�𒆐S�Ɋe�n�ō��J�ЊQ���������A�Q�O�O�l�ȏ�̕����S���Ȃ�܂����B�啔�����y�������͐�̔×��A�]���ɂ����̂������ł��B����ɑ䕗�P�Q���ł͔�Вn�ɒǂ��ł���������l�Ȕ�Q���o�Ă��܂��B
�@�@�����̂s�u�j���[�X�ō���̏������u�y���ɂ̂ݍ��܂ꂽ��Ƃ̕Еt�����܂܂Ȃ�Ȃ������ɍĂсE�E�E�B����ȂƂ���ɂ͏Z�߂Ȃ��A�Ǝv���Ă��܂��v�ƌ���Ă��܂����B��c��X���Â����Ƃ�y�n�A�n�����������Ȃ������邱�Ƃ̋�Y�͌v��m��Ȃ��̂��낤�Ǝv���܂��B
�@�@���{���u�P��������Љ�v�Ƃ������Ȃ���A����ł��т��т̎��R�ЊQ�ő����̖����������Ԃ�s�^��ōς܂�����̂��A���Ȍ������z�����댯���̖h�Б�̗\�Z�𑝂₵�Ăق����Ɗ肤�̂͒P��������̂��A�����I���o�Ȃ̂��B�ۈ牀�ŗ\�Z��g�ގ��ɂ͐悸�A�q�ǂ������̈��S��S�̖L���Ȑ������l����̂ŁA���h���̗ǂ����R�҂���̕]���͓�̎��ł����A���ƃ��x���ł͂����������Ȃ��̂ł��ˁB
�@�@���̂��т̑䕗�ł͕ۈ牀���ӂ̒n��ɂ����������o����ĉ��l�s�h�Ѓ��[�����Ђ�����Ȃ��ł����B�s�}��͒ߌ��삪����Ă��Č�ݍH�����������肳��Ă��܂����A�ߋ��ɂ͉��x���×����ď���Z�����邱�Ƃ��������ƌÂ�����̏Z���͘b���Ă��܂��B���i�͉��₩�Ȏ��R�ł����A���ɉ���ނ��đ傫�Ȕ�Q���N���邱�Ƃ��A�����������ǂ̂悤�ɑΏ����ׂ����A�q�ǂ������ƈꏏ�Ɋw��ł��������Ǝv���܂��B
�@�@�ċx�݂ɃL�����v��C�����ɂ��o�����\��̂��ƒ�����邩�Ǝv���܂����A�C�ۏɂ͏\���C�����Ċy�����v���o������Ă������������ł��B
��7�����i2018�N7��1���j
�@�@4���V�N�x�J�n�ȗ��A5�����Z�E������A6���莞�]�c����Ɩ@�l�^�c�ōł��Q�����������������z���A�Ȃ܂��n��̖~�x��ȂljĂ炵�����y���݊����ڂ̂V�����������܂����B�~�J�������āA���̂Ƃ���̖ҏ��Ŏq�ǂ������͂�������ċC���ł��B�ۈ�m�������A�Ȃ◷�s�̊y���݂��T���Ă��܂����A���̑O��8���ɉ��l�s�̎w���č�������̂ō�N�x����̗l�X�ȋL�^���̓_���ɖZ���������𑗂��Ă��܂��B
�@�@����������v�֘A�@����Q�c�@�{��c�ʼn��E���������Ƃ̃j���[�X������܂����B�c�Ǝ��Ԃ̏���K���⓯��J����������Ȃǂ����荞�܂�Ă��邻���ł��B���{�l�̓��[�J�[�z���b�N�ƌ�����l�������قǁA�O���Ɣ�ׂĒ����ԓ����l�������Ƃ����Ă��܂����A�ߘJ���₤�a�Ƃ������������т��іڂɂ��܂��B�����ԑO�̂��Ƃł����u���[���c�Ј��v�Ƃ������t�����s������������܂����B
�@�Ђ悱�ۈ牀�ł͕ۈ�m�͋Ζ�����8���ԁA�x�e����1���ԁA�S��9���ԋΖ��ɂȂ��Ă��܂��B����A�q�ǂ������͒Z���ԕۈ��8���ԁA�W�����ԕۈ��11���ԁA�����ĉ����ۈ玙�͍Œ���13���Ԃɂ��Ȃ�̂ł�����A�ǂ��l���Ă��q�ǂ������ƈꏏ�ɉ߂������ԈȊO�ɕۈ�̌v���L�^�ɔ�₷���Ԃ����Ȃ��̂�����ł��B�x�e���Ԃ����ł�肭�肵�ĘA�����������Ȃ���ł����A�Ζ����ԏI������x�e���ł��܂������ނ���������A���ޏ��������Ă���p������ɂ��A�u���b�N���Ȃ��Ǝv���܂��B�ۈ�⋳��͎q�ǂ��̎p���悭���Ȃ���A���ɂ͐S�̉��ɂ܂ŗ�������Ȃ���Ί��������������H�ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ�����ʂ�����̂ŁA���ԊO�ɂ��q�ǂ��̎p����荇�����̂ł���ۈ�m�̊W����厖�ɂ���ƑދΎ��ԂɐH������ł��܂��܂��B
�@�u�ۈ�m�s���v�̌����̈�Ɏd���̃n�[�h�Ȏ��⋋�����̏������ł��邱�Ƃ�����܂��B���̓x�A���������ĕۈ�m�̏������P�̂��߂ɂ����ނˌo��7�N�ȏ�̕ۈ�m���Ɍ��z�S���~�̎蓖���x������邱�ƂɂȂ�܂������A����̒����I���ʂ��͗����Ă��܂���B
�@�@����̐e�̉���A�w�O�̎q�ǂ�����ĂȂ���̐E���������Ă��܂��B����͕ۈ珊�݂̂Ȃ炸�A�ǂ̋ƊE�̔Y�݂ł�����A����̑傫�ȉۑ�ł����A�����������āA�Ђ悱�ۈ牀�ł͐E���Ԃ̋����͂����߂A���������ł��邱�Ƃ�[�܂炸����A���݂����v�����A���������Ďd������E�E�E���_��`�Ɲ������ꂻ���ł��ˁB
��6�����i2018�N6��1���j
�@�@��T���A�j���[�X�ԑg����킵�Ă��郏�[�h�Ƃ����m��w�A�����J���t�b�g�{�[�����̔����v���[�A�l�w���A�j�w���Ƒ�����b�Ƃ̊ւ��A���ۓI�ɂ͕Ē���]��k�ł��傤���B�s�u��ʂ����ς��ɉf���o�����ʁX�͔ۉ��ɂ����x���ڂɓ����ė��Ă��܂��܂��B�����Ԃ������ɂ��A���̓x�̑傫�ȕ���������ʎs���̐g�̉��ɐ��N����l�X�ȃg���u�����A���̋ؓ��͑��ʂ���Ƃ��낪������̂��ȁA�Ə��X���肵���C���𖡂���Ă��܂��B���ꂼ��̗���ŕېg���旧�̂��l�Ԃ̐��Ȃ̂ł��ˁB
�@�@�������P�ł���ƐM����Ƃ���ɒ����ɐ����A�s�������Ƃ��āA���ꂪ�ق��̐l�X�̕��a��K���Ɍ��т��Ȃ����͒����̃e���␢�E���ɑ������݂����̎p�����炩�ɂ��Ă��܂��B���Ƃ͂ƌ����K���ɐ�����悷���ł���͂��̏@���ɕ����̔��[������Ƃ����̂�����ł��ˁB�@�@�@�@�@
�@�@�Ђ悱�ۈ牀�ɂ́A���т��у��j�Z�t�A�����Ȃ���t�c�A���A�t�m�gCR����Ȃǂ��琢�E�Ō����ɋN���Ă���ߎS�ȏ̕Ǝx���̗v���������Ă���̂ŁA�G���g�����X�̌f���ɓ\���Ă��܂��������ɂȂ��Ă��܂����B
�@�@�ۈ牀�̗c���q�ǂ������ɐ��E�ŋN���Ă���l�X�ȔߎS���ǂ̂悤�ɓ`���邩�A�܂������ł��p������c���ɑ���s�҂�ƍ߂́A�ƂĂ����G�œ�������Ǝv���Ȃ�����A����ł����ۂɓ����n����ŁA�������̒��Ŏ����Ɠ������炢�̗c���q�ǂ����������Ă���o�����⎖���ɖ��S�ł��Ȃ����͎q�ǂ������̈炿�䂭�ߒ��Ō����Ė��ʂɂ͂Ȃ�Ȃ��ƐM���܂��B
�@�@�u�������s�K�Ȗڂɉ���Ă��Ȃ��ėǂ������v�Ƃ�����ڐ��Ȉʒu����ł͂Ȃ��A�u�݂�Ȃ��K���ň��S���Ă����Ă悩�����v�Ƃ��������q�ǂ��Ƃ��ƂȂ����Ɉ�߂Ă������炢���ł���
��5�����i2018�N5��1���j
�@�@�V���������}���ĂR�O�N�x�̕ۈ炪�n��A�͂�P�J�����߂��܂����B�҂�҂悮�݂ł͂��ꂼ��̂��ƒ�̓s���ɍ��킹�ĕ�q�ʉ������˂������Ă��܂������A���悢��{�i�I�ȕۈ牀�ł̐������n�܂�܂��ˁB�c���N���X�ł͗F�������ł��Ċy�����ɉ߂����Ă���l�q�ł��B�������c������ł��ˁB
�@�@�Ђ悱�܂�ł͑������̋v�X�̍ĉ����э����p�����邱�Ƃ��o���܂����B�������Ă܂�1�J�����������Ă��Ȃ��̂ɂ݂�Ȃ�����Ƒ傫���Ȃ����C�����܂����B���w�Z���w�Ƃ����傫�ȐߖڂɁA�ǂ̎q�����t�ɂ͂��Ȃ��Ă��A�s���Ȃ��Ƃ�₵�����A�߂������Ƃ��낢��ȑ̌���������̂ł��傤�B�����I���������z���Ă������ˁB
�@�@�Ђ悱�ۈ牀�̓���������ł́A�u�ǂ̎q�ǂ����ی�҂ɂƂ��ĉ�������ȕł��邱�ƁA�����Ă����͈�l�ŎЉ�Ƃ�����C�ɉj�������Ă����q�ǂ������ł��邱�Ƃ��������o���ĕۈ�ɂ����肽���v�Ƃ��b�������Ă��������Ă��܂����A�ۈ牀�Ƃ����吨�̕ۈ�҂��₦��������͂���Ή����̂悤�Ȃ��̂ł��B���̒��Ō�����ē��X�l�X�Ȏ����o�����Ȃ���A�F�����W��z���A�������J��Ԃ��Ȃ��������q�ǂ��͓y�̒��ɂ�������ƍ���n�߂Ă���Ǝv���܂��B�n�\�ɏo�Ă��镔���͂܂��ق�̑o�t�ɂ����Ȃ��̂ł����A���������ƒ�̒��œK�x�̉h�{�����������āA������{�t�����A�Ԃ��炩���A�������Ԃ悤�ɂȂ��Ă����܂��B����̑�l�����͂��̓����y���݁A��сA���Y���Ă������Ƃ����̖�ڂ̑啔���Ȃ̂��ȂƁA�v���Ă��܂��B
�@�@�������ɂ͂Ђ�����Ȃ��ɉ��������̑̑������A�p�ꋳ�����̊��U�̓d�b������܂����A�����̕ۈ牀�ł����������ۈ���e��������Ă���̂ł��傤�B1�������Ԃŋ���ėl�X�ȋ�������ۈ牀�ȂǁA���낢��ȕۈ�ς����Ă���̂������̕ۈ玖��Ȃ��Ǝv���Ȃ�����u�V�т��������V�ׂ�̂͗c�����̓����I�v�Ƃ���A�q�ǂ������������ŗV�Ԏp���y����ł��܂��B
��4�����i2018�N4��1���j
�@�@�i���E�������߂łƂ��������܂�
�@�@�u������@��������@�����˂���v��A�u�܂��@�����Ɂ@�����тɁ@���Ăˁ�v�@�ȂǁA�q�ǂ������̐L�ѐL�тƊy�����ȉ̐������ɓ��̂����炱����ŕ��������R�����҃X�s�[�h�ʼn߂��܂������A���̊J�Ԃ���N��葁���V��ɂ��b�܂ꂽ���N�́A���Ԍ����y���܂ꂽ���ƒ낪�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�@�R�����ɂ͋������炮�݂Q�P�l�̎q�ǂ������Ƃ��Ƒ������ꂼ��ɗl�X�ȑz�������ɁA�s�}�Ђ悱�ۈ牀���瑃�����čs���܂����B�ǂ̎q���ۈ牀�ɂ���Ԃɂ͋�������{�����肢�낢��ȕ\��������Ă����̂ɁA�����������w�Z�Ƀ����h�Z����w�����Ēʂ��̂��ȂƎv���ƁA�s�v�c�Ƃ��낢��ȏ�ʂł̎q�ǂ������̏��Ă���炪�v�������т܂��B�@�@
�@�@�������̌���قƂ�ǂ̎q�ǂ��������ǂ���ɓo�����Ă���ۈ牀�́A����ׂɂ͕��i�ǂ���Ȃ̂ł����A�������Ă����q�ǂ������͑傫�Ȋ������߂Ă���̂ł��傤�B���w�Z���w�Ƃ������߂Ă̎����Ɍ��������Ă���q�ǂ������A�Ԃ����̍����瓯�����ɂ̒��ŁA������C���z���ĉ߂������q�ǂ������Ɂu�����I�v�ƃG�[���𑗂�܂��B
�@�@���N���҂�҂悮�݂ɂP�S���A�͂Ƃۂ��ۂ��݂S���A�������P���A����݂P���A���邩���݂Q�����V�������ԓ��肵�܂��B���炭�͋������œ��₩�ȓ��X�ɂȂ�܂���������������Ă��ĉ������B
�@�@�S���P���́u�G�[�v�����E�t�[���v�B�ŋ߂͂��܂茾���Ȃ��Ȃ����C�����܂����A�����q�ǂ��̍��͂悭�u���������Ă��������v������ƁA�q�ǂ����m�ł��������������y�����̂ł��B�u�����͊w�Z���x�݁I�v�Ƃ��u�ΐ��l�ɉ�����I�v�ȂǂقƂ�ǂ������̂Ȃ����Ƃł������A���X�͓x���߂��ē{��ꂽ������܂����B
�@�@���̂Ƃ���A�s�u��V�����ʂł͂����ς�u�l�w�����v��肴������đ�ɂ��킢�ł����A�G�[�v�����E�t�[�����ǂ��͂���������ɂ��Ăق������̂ł��B�u���������ցv�Ƃ������Ƃ킴������܂����A���ʂ��K���Ɍq����u�����v���Ăǂ�Ȃ��Ƃ�����̂ł��傤�H�@
�@�@���N�x�������������ɋC�����āA�ۈ牀�̂�����E��̂��ƂȂ��������͂��Ȃ��琽���Ɂu�����v�̖����ۈ��Nj����Ă����܂��B�ۈ�̒��ł̂��ƁA�����I���̂��ƁA�^�c�ʂł̂��ƂȂǁA���ݓI�Ȃ��ӌ�����K���ł��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�s�}�Ђ悱�ۈ牀�@�����@��㏉��@�@�@
���ŏI���i2018�N3��18���j.�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�������߂łƂ��������܂�
�@�@3�����ɂȂ�ƁA���킩�ꉓ���₨�킩��p�[�e�B�[�ȂǁA�����炮�݂𒆐S�Ƃ����s���������̂ŕ��i�̕ۈ牀�ł̐����Ƃ͏��X��ς���Ă���悤�ł��B�q�ǂ������́A�ق�6�N�Ԃ��ꏏ�ɉ߂����āA����������̑؍ݎ��Ԃ��c�t���⏬�w�Z�Ƃ���ׂĂ����ƒ����̂ŁA�܂��Ɂu���ꌴ�̑傫�Ȃ������v�̑�Ƒ��̂悤�ɂ��ĉ߂����Ă��܂����B�����̉��O�ۈ�ł͎v��������̂����āA���R�C�܂܂ɍD���ȗV�тɖv�����Ă��܂�������̗͂͏\���ɂ��Ă��܂��B3���̋��H�͍P��́u�����烊�N�G�X�g���j���[�v�Ȃ̂ŁA�D���Ȃ����������M�ɎR����ɂ��Ă����炰��p�������܂��B�u�������ł�����Ȃɂ������ׂ�́H�v�Ƃ����˂�ƁA�u�ۈ牀�̋��H�̕���������������v�Ƃ̂��ƁB���H����鑤�Ƃ��Ă͂�낱��ł�����ł���ˁH
�@�@�u�����Ղ肠���сA�����Ղ肽�ׁA�����Ղ�˂ނ�v�Ƃ����̂��Ђ悱�ۈ牀�ł̎q�ǂ������̐����ł����A��̑O�Ȃ瓖����O����������Ȋ�{�I�Ȃ��Ƃ�ۏႷ��̂����A���͓���ȂƂ��Â������Ă��܂��B
�@�@�q�ǂ����m�����ԂƂ��ċ����Ȃ��Y��āA�킪�܂܂₢��������̌����Ȃ�����܂荇�������Ĉ�A�Ƃ����̂��{���̋���ł���Ƃ����������������ŁA�u�S�͔M�������ɑłāv�ƁA���ƂȂ̌��߂����[���ɒ����ɏ]�������������A���S�ŁA���ƂȂ̌������ɏ]���Ȏq�ǂ����悢�q�Ƃ��������������Ă��Ă���Ɗ����܂��B
�@�@���q���E��������i��œ��{�̑��l����������钆�A�q�ǂ��̐l���͌������Ȃ�����ۈ珊�̎��v�͂��Ȃ����ɂȂ��Ă���Ƃ��������ɁA����A���̕ۈ琭�傫���ς�邱�Ƃ͕K���ł����A�ۈ珊�ɓ���ׂ��q�ǂ����S�������ł���{��A�������ʂł͂Ȃ����̖����N���A�[�ł���ۈ珊�𑝂₷���Ƃ͕����̂��Ƃł͂���܂���B�Ђ悱�ۈ牀�͉ߋ��̓��{�̕ۈ��A�Ȃƈ��ł�����y���̕ۈ�ɕ���āA�u�q�ǂ��������q�ǂ��炵�����������v�悤�A���͂Ȃ��炱�ꂩ����ۈ�Ɍg����Ă������Ǝv���Ă��܂��B
�@�@�݉����͕ۈ�^�c�ɂ����͂����������肪�Ƃ��������܂����B�܂��A���܂ł̂��ƒ�ł̎q��ĂɌh�ӂ�\���܂��B���ꂩ������q�����^�ɍK���Ȃ��ƒ�ł��葱���܂��悤�ɁA�E���ꓯ�S������Ă���܂��B�@
�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�s�}�Ђ悱�ۈ牀�@�����@��㏉��@�@�@
��3�����i2018�N3��1���j
�@�@2�����͕����I�����s�b�N�ł�������ł����B�s�u�ɂ����t���Ŋy�����������������ł��傤�B���_�����l�������I����A�ɂ������������I����A�{�Ԃł͂ق�̈�u�̏����ɋC�̉����Ȃ�悤�ȗ��K���d�˂Ă����̂��낤�ƁA�������܂����B10��20��̎Ⴂ�I��������A�c���̍�����u�I�����s�b�N�ɏo��I�v�ƁA�ڕW�������f���Ă��낢��Ȏ��╨���̂ĂĂ̓w�͂̂��܂��̂Ȃ̂ł��傤�B���Ƒ��̋��͂�肢�ȂNJ����������Ă̂��Ƃł��傤���A��l�̎q�ǂ��̂��߂ɂ��ꂾ���̔M�ӂƈӎv���p���ł���e���������Ȃ��Ǝv���܂��B���Ȃǂ́A�u�����̎q�ǂ������炱��Ȃ��́E�E�E�v�Ƃ��܂���҂��Ȃ��ʼn������قǂقǂŗǂ��A�Ƃ��ė��܂������A�q�ǂ��ɂƂ��āu�e�̊��҂��ǂ��Ȃ̂��v�����̎q���������Ă�����łǂ̂悤�ɍ�p����̂��A�����[���ł��B
�@�@�ۈ牀�ł͖����̕ۈ��ʂŁu��l�ЂƂ肪���_���X�g�v�ł����Ăق����Ɗ���Ă��܂��B�����[��h�b�W�{�[����S�_�A�|�n�A�꒵�тȂlj^���ʂł̔\�͂�҂ݕ���H��Ȃǎ��̊�p���A���G���������Ȃ��ƁA���ꂢ�Ȑ��ʼn̂��邱�ƂȂǁA�������ʂŁu���Ԃ���������I�v�Ǝv���邱�Ƃ����t������A�ۈ�m���C�t���Ă�����������ȂƎv���܂��B�������D���œ��ӂȎ����y����ő�������A�]���͌ォ��K���t���Ă�����̂ł��B
�@�@�ŋ߁A�C�O�̒����œ��{�̎q�ǂ��́u���ȍm�芴�̒Ⴓ�v���悭�����Ă��܂��B�����q�ǂ��Ɋ��҂��邱�Ƃ�������ƓI�O��ɂȂ��Ă��邹���Ȃ̂��Ȏv����������܂��B�c����������u�������������B���������̂Ȃ��q�Ȃv�Ǝv���Ȃ��ŁA�߂����Ȃ�ĂƂĂ��h�����Ƃ��Ǝv���܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�ۈ牀�ʼn߂�������ő�ɂ������̂́u���[�A�������y���������B�������������ȁv�Ɖ��ƂȂ������ċA�H�ɂ��q�ǂ������̎p�ł��B�������A�����A�Ƃ������Ƃ�������A�v���悤�ɂ����Ȃ������肵�ĕs�@�����������A�邱�Ƃ�����̂ł��傤���A���ƒ�Őe�Ɏ���A�ۈ牀�ł͕ۈ�m��F�B�Ɛl�ԓI�Ȋւ�����ނ����ɏ����A�K�������I�ȑf�G�Ȃ��ƂȂɈ���Ă����ƐM���Ă��܂��B
�@�@���N�x�Ō�̌��ɂȂ�܂����B�܂��A�C���t���G���U���I�����Ă��Ȃ��悤�ł����A�傫�Ȏ��̂Ȃ��I������悤���Ӑ[���c��̓��X���߂����܂��B1�N�Ԃ����������͂��肪�Ƃ��������܂����B
�@
��2�����i2018�N2��1���j
�@�@�S�N�Ԃ�̑��ɑ������g�̓����ŁA���l���X�Ђ��Ȃ�܂����B���ԏ�����O�̕����A�V�����ȂǑ�������Ⴉ�����ĉ�����������������A�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B���������A�ی�҂������]�|�ʼn��䂷�邱�ƂȂ��o���o���܂����B���̌������ł̓W���u�W���u�r�ɕX������A�O���q�ǂ��������������Ղ̎c��n�ʂ͑������܂���͗l������Ă��܂��B�������q�ǂ��������V�т������ɂ͗n���n�߂ăh���h���A�x�`���x�`���ɂȂ��ĕی�҂̕��X�����点��^���ɂȂ邱�Ƃł��傤�B�������ɌC�͉�����A�Y�{����V���c�͂ǂ�܂݂�ɂȂ��A�ő�ςł��ˁB����A���N�x������]�̕������w�ɗ��āA�͂Ƃۂ��ۂ̎q�ǂ�����������ŗV��ł���l�q�����Q���Ȃ��炶������݂ċA���܂����B�u���ł�����ȕ��ɗV��ł���q�ǂ��������ł��ˁv�ƁB�u�s�}��ɂ͂�������ۈ牀������A�ۈ���j�����l�Ȃ̂ł��ƒ�̈玙�ςɍ������������ł��������ˁB���ꂪ�q�ǂ�����ɂƂ��Ĉ�Ԉ��S�Ȃ��Ƃł���v�Ƃ��b�����܂����B
�@�@�R�O�N�x����V�ۈ珊�ۈ�w�j���{�s���܂����A�����ۈ�ɂ��Ă��ڍׂɋL�ڂ���Ă��܂��B���ێЉ�ł͈ȑO���c������̑O�i�Ƃ��Ă̓������̕ۈ�̏d�v��������Ă��܂������A���{�ł��q�ǂ��̕n����s�҂�������������A�c���������ʂ��āA�ۈ珊�ɂ���������ۈ�ɍ��x�Ȑ�含�����߂���悤�ɂȂ����̂ł��B�@�@
�@�@�ۈ珊�́u�q�ǂ���a�����Ĉ��S�ɗV���Ă������x�̂Ƃ���v�Ǝv��ꂪ���ł����A���ꂩ��̎���Ɍ������Ĉ炿�䂭�q�ǂ������ɂ́A�����y�����[�������ۈ牀�����𑗂�A�w�����ȍ~������w�ю�̓I�ɍs������ӗ~����l�ɂȂ��Ăق����Ɗ���Ă��܂��B���̂��߂ɂ͌����ɖڂ̑O�ɂ���q�ǂ������̎p���݂Ȃ���A�ۈ痝�O�Ɠ��X�̕ۈ���H�ɂ��Č������Ă������Ƃ���Ǝv���܂��B
�@�@�ۈ珊��肪���܂łɂȂ��[�������Ă��邽�߁A���������ĕۈ�m�̏������P�Ǝ����̌���𐭍�ۑ�Ɍf���Ă��܂����A��̍�̈�Ƃ��āA�ۈ�m�ɃL�����A�A�b�v���C���ۂ����鎖�ɂȂ�܂����B���N�x�͂܂��N���X���[�_�[�̕ۈ�m�������猤�C����u���āA�w���Ƃ�S�E���ɓ`���Đ��ʂ����L�ł���A�Ɗ���Ă��܂��B
�@�@���̉��ꌴ�ɉ��l�s���L�n���Q�O�N�_��̖����ݗ^���ĔF�ۈ珊���J�����A���P�T�N���߂����N�x�͎c��̎l�������n��܂��B�����Ƃ��Ă͖��F�̓����ۈ玺���ォ������Ă����A�q�ǂ��̍K���ƕۈ�ɑ���v���͕ς�炸�A�E���ɂ��n�݂̑z����`���Ă��܂������A���̒��̕ω��̃X�s�[�h�͎q�ǂ��̈炿�ɉe�����y�ڂ��Ă���̂��A���邢�͎q�ǂ��̖{���͕ς��Ȃ��̂��A�܂��A�ی�҂ƐE���̑z���͂ǂ��Ȃ̂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�q��Ďx���V���x�ւ̈ڍs�ɑ����ۈ珊�ۈ�w�j�̉���ȂǁA�������ۈ�҂ɂނ��ċ��߂��邱�Ƃ͕ۈ琧�x�̉��ςƂ����ꑤ�ʂɂƂǂ܂炸�A�u�q�ǂ����K���Ɉ���Ɓv�ɂ��čl���邱�Ƃł��B
�@
��1�����i2018�N1��4���j
�@�@�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��B
�@�@�N���N�n�������x�݂������������肪�Ƃ��������܂����B�N���N�n�ɂ������̎��Ə����J���Ă��܂����B�Ζ��𑱂����Ă����ی�҂̕��ɂ͂��q����̕ۈ�ɂ��đ�ς��������ƂƂ��@�����Ă��܂��B�\����܂���B�ۈ�m�����͂��ꂼ�ꎩ�R�ɉ߂����āA���t���b�V���o���܂����B�V���ȋC�����ň�l�ЂƂ�̎q�ǂ��ƌ��������ĕۈ�ɗ�ނ��Ƃł��Ԃ��������Ǝv���܂��B
�@�@���l�Ƃ��ẮA�N���N�n�͂ǂ��ɏo�|����Ƃ��������Ȃ����i�ƕς��Ȃ������ł������A����̕��e�Ƃ̕�炵�͎��Ԃ̗��ꂪ�������Ƃ��Ă���̂ŁA����1���Q�S���ԂƂ����ǂ��ۈ珊�Ζ����Ƃ͂����Ԃ�Ƃ��������̂��Ɖ��߂Ċ����܂����B�ی�҂̊F�����ƒ�ł��q����Ɖ߂����ꂽ�N���N�n�͂ǂ̂悤�Ȏ��Ԃł����ł��傤���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�S������͑n�݂��ĂP�U�N�ڂɓ���܂����A�����̌㔼���o�߂����N�ɂ͐V���������ɂȂ��ĕۈ珊�^�c���Ȃ����Ă����̂ł��ˁB���70���N���o�Ďq�ǂ���������芪�����͑S���ς��܂������A�u�q�ǂ������ɍőP�̗��v��ۏႷ��v�����ۈ珊�̋`���ƐӔC�ł��邱�Ƃ͕ς��͂�������܂���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�l�H�m�\�E�`�h�Ƃ����������悭�ڂɓ���悤�ɂȂ�܂����B������E���q�����i��ŘJ���͂̕s���������ɂȂ��������A���ꂩ��͑����̏�ʂŃ��{�b�g������Љ�ɂȂ�悤�ł����A���ǂ��̑z���Ɋ��Y�����Ƃ��ۈ�̎n�߂ł���ȏ�A�ۈ�܂ł��������Ȃ�Ƃ͍l�����܂���B�q�ǂ������ɂ͐��g�̐l�Ԃ̑̉�����������ۈ���������Ɗ肢�܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�q�ǂ��������q�ǂ�����ɂ����܂Ƃ��炾�Ƃ��������������g���đ傫������߂ɂ́A�g�̉��̕ۈ���𐮂���ׂ��ۈ�҂̐ӂɕ����Ƃ��낪�傫���Ǝv���Ă��܂����A�ۈ珊�̂ЂƂ�悪��ɂȂ�Ȃ����߂ɂ��ی�҂̊F����̃A�h�o�C�X���������������ł��B���N����낵�����肢�������܂��B
�@
��12�����i2017�N12��1���j
�@�@�C�ەϓ��̌������ɐU��ꂽ���̎c��H����A��������~�Ɍ������Ă���悤�ł��B�����A�X������Ă���Ƌ�Ǖ�����͂�͂�Ɖ����F�̗t���ς������~��Ă��܂����B�l�X�������ɍs�������ܓ��͗����t�ɖ�����āA�u�Ȃ�āA���Ă��I�܂�Ńu���[�j���̐X�v�Ƃ���A��������V�b�N�ȋC���E�E�E�ł��A���X�ܑO���`���I�ɂ���������
�@�@�|�ڂ����ő|����Ј��̎p�ɂ����Ƃ����ԂɌ������E�Ɉ����߂���܂����B���̊Ԃ̃t�A���^�W�[�ł����B
�@�@�t�A���^�W�[�̐��E�ƌ����A���������݂̎q�ǂ��̃u�[���͂��܁A�j�̎q�����̎q���F�Ƃ�ǂ�̈ߑ���g�ɂ܂Ƃ����P���܂�A�C�h���ɂȂ肫���Ċy����ł��܂��B�d����\��F���ۂ��Ƃ������E�E�E���Ƃ��E�X�ł��B���ɂ͂��P���܁A����������A���������A�ʂĂ͂��ʂ�˂��ɂ܂Ŏ��R�ɕϐg�ł���͂͗��������ł��B
�@�@�c���Ƃ��Ȃ�ƊO�V�т̌o���̐ςݏd�˂���������Ƒ̂ɂ��ݍ���ł���̂ł��傤�A�ӂƂ������ׂȂ��Ƃ���C���[�W�������Ղ�Ɩc��܂��ċ�z�̐��E�ŗV�Ԏ����ƂĂ����ɂȂ��Ă���A��������A�_�A���ȂǃX�P�[���̑傫�ȕ�����肱�ޑf�n���萶���Ă���Ɗ����܂��B�@
�@�@����͂��邩���݂��U���̍s���Ɍ��o������������̏Z��Ŗڂɂ��������^���[�̂悤�ȓS���i�H�j���A��ɂ͐Ռ`���Ȃ������Ă����I�����ŁA�q�ǂ������́u�F���D�ɋz�����܂ꂽ��Ȃ��H�v�Ƃ��u�o�^�����Ĉ��������ē|������Ȃ��H�v�Ƃ��吷��オ�肾�����ƒS�C���������܂����B�j�̎q�����̎q�����ꂼ��Ɏ����̍l�����咣���āA���荇��Ȃ��l�q���ڂɕ����Ԃ悤�ł��B���Ɏ����Ă���m���������Ă���₱���ƍl���Ȃ���A����ɗF�B�Ɛ܂荇�������čs���p�͂��̔N��̗c���̗��z�I�Ȏp���Ǝv���܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@��z�̐��E�ƌ����̐��E���s�����藈���肵�Ȃ���A�g�̉��̏����Ȏ��R�⎖��������傫�ȑ��蕨����邱�Ƃ��o����q�ǂ������̊����̈炿�ɓ��X�A�S���܂�v���ł��B
��11�����i2017�N11��1���j
�@���N�قlj^����̎��{�ɂ��ċC�����N�͍��܂ł���܂���ł����B�ߗׂ̏��w�Z�ł͏����Ɏ��������Ŕ��f���鑤�Ƃ��Ă͑傢�ɔY�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�u�������^����A����lj^����v�Ƃ������ŁA�s����ȋC�ۏ̒��u���A���Ȃ��v�͎q�ǂ������͂������A�Ζ��₨�ٓ��̗p�ӂȂǑ�l���̓s��������A�S�����P�O�O��
�@�@�������Č�����~�߂�͕̂s�\�ł��B����ǁA�������Ԃ��܂߂ĉ^����Ƃ����s����ʂ�ʂ����q�ǂ������͉�������傫�Ȏ��n�Ĉ���傫���������Ă���̂ł�����A���ƂȂ����͐S����J�߂Ă��������Ǝv���܂��B
�@�@����A����������N�f�f������܂����B�҂�҂�͕ۈ玺�ŁA�͂Ƃۂ��ۂ��炭����͈ꎞ�ۈ玺�ʼn���̗L�{�搶�ɐf�Ă��������܂����B�f�@�̍Ō�ɐҒ����Ȃłāu�悩�낤�I�v�ƌ����ĉ�����̂��������낭�A�����q�ǂ������́u�悩�낤�I�v�ƌ��^�����Ă��܂����B�҂�҂�A�͂Ƃۂ��ہA�������A�����A���邩�A������Ƒ傫���N���X�ɂȂ�ɂ�A�q�ǂ������̎�f����ԓx���������肵�Ă��܂��B������Ƃ��Ȃ�Ɓu���˂������܂��I�v�u���肪�Ƃ��������܂����I�v�ƕۈ�m�������Ă��Ȃ��̂ɂ����ƈ��A����l�q�ɁA�Ԃ����̍��A�f�@���������đ傫�Ȑ��ŋ����Ă�������v���o���܂����B�����m�̒ʂ�A���i�͂��Ȏq�ǂ������ł�������킫�܂��邱�Ƃ��������w��ł���̂��ȂƎv���܂����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�e���r��Q�[���̉e���Ȃ̂ł��傤���A�q�ǂ����������\�Ȍ��t���������ɕs���̐����悭���ɂ��܂��B�q�ǂ������ɂƂ��Ă͂����������q�[���[�̂܂˂ł�������A������傫���������������Ƃ�����]�̕\��Ȃ̂ł��傤�B�����Ȃ��ɂ��������łȂ��A���퐶���̒��ł�����邨�ƂȂ��������������t�����Ɖ��₩�ȑԓx�Őڂ���Ȃ�A�قƂ�ǂ̎q�͏���킫�܂��Č����悤�ɂȂ��Ă����܂��B���t���̂��̂��ǂ�Ȏv���Ō��t���Ă��邩�A�����A�y�����������ĉ߂����Ă��邩�A�C�ɂ����Č�����čs�������Ǝv���Ă��܂��B
��10�����i2017�N10��2���j.�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�P�O���ƌ����Ȃ�Ƃ����Ă��u�^����v�I���悾���Ă܂ŁA�v�[���Ŋy����ł����q�ǂ������ł����A���X�ƋC��������ւ��A�c���N���X�ł͑O�N�̋L�����͂�����Ǝc���Ă���̂ŁA������������ƃA�X���[�g�C���ł��B�����[�̗��K�ł��ǂ������珟�Ă邩�A�q�ǂ������Řb�������l�������Ă��܂��B�u�����Ă��ꂵ���A�����ĉ������A�͂Ȃ�������߁v�ł͂���܂������������ӎ����Ă������o���ł�����܂��B�����ɂ́A�������ς��͂����Ĉ�l�ЂƂ肪�B�����A�[�����ɖ�������ė~�����ł��B�����Ă������Ă��A�͂����킹�đn�����^������ꏏ�ɉ߂������ƂŁA�����Ɓu�Ƃ��������Ă����ȁv�ƐS�̒��ɍ���ł���鎖�ł��傤�B
�@�@���i�̕ۈ�̒��Ōo�����d�˂����Ƃ���ڂɎd���Ă�v�Ƃ����̂��A�Ђ悱�ۈ牀�ł̉^����̂˂炢�ł����A�u�����͈Ղ��s���͓�v�ŁA�e�N���X�S�C�͂��ꂱ��l���A�S������̎q�ǂ��̎p�⌾�t���v���N�����Ȃ���N���X��ڂ����肵�܂����B���C�Ȃ��P��ƂȂ��Ă��鉀�̍s���ł����A����Ȃ��Ƃ��m���Ă���������Ɖ^����̊y���ݕ�������������邩�Ǝv���܂��B
�@�@�[���Â��Ȃ鎞���������Ȃ�܂����B��ɂ͒��̉������������ƕ������܂��B���g�~�b�N�̂Ƃ��Ɏq�ǂ��������̂��̂����̊Ԃɂ��H�̉̂ɂȂ��Ă��܂����B�N��̂����������̂��̂��ƂĂ������āA�������肵�Ă���Ƃ����ɔN�x���ƂȂ��āA������̎q�ǂ������͏��w�Z�ɍs���悤�ɂȂ�܂��B�����āA�ǂ̎q���P�N���X�Âm���ɐi�����܂��B
�@�@�k���N�A�O�c�@���U�A�V�}�����E�E�E�ȂǍQ�����������̒��ł��B�ǂ�������߂��邨�����ȓ����ł����A��������ʐl�ɂ������ꉽ������]�g���y��ł�����̂ł��B���قǗ���̑������������ゾ���炱���A�ŏ��P�ʂł���ƒ�̖������傫���̂��Ǝv���܂��B�y�ɂ܂��ꂽ�킩��萶�����o�t�����Ɍ������ĐL�т悤�Ƃ���悤�ɁA�q�ǂ������͂ӂ�����Ƃ����ƒ납��{���Ĉ���čs���܂��B�q�ǂ������͂������ł����₦�ԂȂ��L�тĂ��܂��B
�@�@�^����ł͑傫����Ƃ��Ƃ��Ă���q�ǂ������̂��Ȃ��Ȏp���A���Ƒ��F����ł�������Ƃ����ɂȂ��Ă��������悤�ɂ��肢�v���܂��B
�@
��9�����i2017�N9��1���j
�@�@���T����菬�w�Z���n�܂�܂����B���ٓ��Â��肩��������Ăق��Ƃ��Ă���������܂����H�ċx�ݒ��͂��ǂ��̑̒��s�ǂ�~�J�ɋt�߂肵�����̂悤�ȓV��s���ŁA�v�悵�Ă������s��������߂����ƒ���������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�c�Ȃ��q�ǂ��̂���ƒ�ł͌v��ʂ�Ɏ����^���A���O�܂ł₫�������邱�Ƃ������ł��ˁB
�@�@�Ђ悱�ۈ牀�ł͐E�������ŋx�ɂ����������āA�A�Ȃ����藷�s�����肵�ă��t���b�V�������悤�ł��B�����A�吨�̌��C�����ς��Ȏq�ǂ������Ɉ͂܂�Ă��鎞�̎��Ԃ̗���͂ƂĂ������̂ł����A���ɂ͂������ƃ}�C�y�[�X�ɉ߂������Ƃŕۈ�ɂ��V�N�ȋC�����ŗՂ߂�悤�ł��B�x�Ɏ擾�ɂ��Ă��������肪�Ƃ��������܂��B
�@�@��ʂ̕ۈ牀�̃v�[���V�тŐ������̂�����܂����B����ɖ؍ނ�g�ݗ��āA�r�j�[���V�[�g�Ŗh�����Đ������߂�����̃v�[���̂悤�ł��B�v�[���ŏI���̂��ߕۈ�m��������P�����ĕЕt����Ƃ����Ă����Œ��ɋN�������̂ŁA�����̊ԁA�Ď��̖ڂ��r�ꂽ�ԂɋN���Ă��܂����悤�ł��B�����͎q�ǂ��������̂т̂тƗV�ׂ邱�Ƃ��ɂ��ĉ^�c���Ă����ۈ牀�Ȃ̂ŁA�Ђ悱�ۈ牀�Ƃ����j�ɒʂ���Ƃ��낪����A�ɂ܂��������܂��B�킸��4�Ő��U���Ƃ������q����Ɛe�䂳��ɂ͉��Ƃ����O�̂��ƂƎv���܂��B
�@�@�Ђ悱�ۈ牀�ł͎q�ǂ������ɖ������v��������y����ʼn߂����Ă��炢�����B�̂��\���ɓ������Ă����сA���̗͂l�X�Ȃ��ƂɊ������A���ƐS�����Ēq�b�����Ăق����Ɗ���ĕۈ炵�Ă��܂��B�����̍ʂ肠�鐶���̒��ł͗F�����ƌ��܂�����A�������ē]�肵�đ����̉���͂���܂����A�ۈ�m�͉��������Ă��q�ǂ��̖��͎�蔲���Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B���̎��̂̕ɐG�ꂽ�ی�҂���v�[���V�тɑ���s���̐������������܂����B�����N���̎q�ǂ���a���Ă��ĐS�z�ɂȂ�͓̂��R�ł��B�ۈ牀��M�p���Ă��Ȃ��Ƃ����̂Ƃ͈Ⴂ�܂��B�����Ȏv�������t�œ`���ĉ������ĂƂĂ����肪�����Ǝv���܂����B�v�[���V�тɂ��čēx�A���S�Ǘ���O�ꂵ�܂��B�q�ǂ������Ƃ������Ƃ́A�S�Ă̂��ƂȂ��������^���ɂȂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ��Ɖ��߂Ďv���܂��B
�@�@
��8�����i2017�N8��1���j
�@�@
�@�@�ۈ牀�̏��ݒn�ł��鉡�l�ł͔~�J�̎����ɉJ�����Ȃ������ł����A�S���e�n�ő����̔�Q������A��Ђ��ꂽ���ɂ͂ƂĂ��������ĂƂȂ��Ă��܂��B�܂��A���܂łɂȂ��قǂ̍��J�◳���ȂLjُ�C�ۂɌ������Ă���͓̂��{�����ł͂Ȃ��n����̂��������ő�ЊQ���N���Ă���A�Ƃ�������f������������ڂɔ�э���ł��܂��B
�@�@���̒n��ɏZ��ł���ƕ��f����Ă����i�����܂�ɂ�����A�ڂɂ��邱�ƂƂ�������Ă��邽�߂ɁA����炪�f��Ȃǂ̃t�B�N�V�����ł͂Ȃ����ۂɋN���Ă��āA��Ђ��ċꂵ��ł��������������Ƃ���������߂��炫��Ȃ��ł��܂��B
�@�@���R�E�̂��Ƃ������ۗ����Ĉُ�Ȃ̂ł͂Ȃ��A�l�Ԃ����̐��E�ł��A�C�O�̑����̍��Ńe���ɏے�������R�ُ̈�Ȏ����N���Ă��܂��B���{�ł͕��a���@�Ɏ���Đ��V�O�N�]����ɕ�炵�ė��܂������A���ꂩ��̎���͂���Ȏp��������O�ł͂Ȃ��Ȃ��Ă���̂��낤���ƕs�����o���܂��B���̂Ƃ��됭���Ƃ̕s�ˎ��ƌ����邱�Ƃ��p�����Đ������������Ă��܂����A�C�O�ł������̕������傫���ς��A���݂̍�����s�����ł��鎞��ɂȂ��Ă���悤�ł��B����ȏ�ɏ�����͌�łɂ킩�ɗL���ɂȂ������t�ł����u�`�h�v�̊J�����i�݁A�S�Ă̕����R���s���[�^�[�Ōq����ȂǑ������x�ł��낢��Ȏ����ς�낤�Ƃ��Ă��܂��B�߂������Ɏ������̕�炵�Ԃ���ۉ��Ȃ��ς���Ă����̂��낤�Ƃ�������ł��B
�@�@���w�Z�ł��u�p�ꋳ��v�̓����ŋ����Ă�����A���ɂ́u�R���s���[�^�[�v���O���~���O�v�������ł��B���オ�ς�����Ȃ��[�A����ɒǂ��t���Ă��Ȃ��Ȃ��[�A�Ɛ[�����ߑ������������̂���ł��B
�@�@�䕗�����������������悤�ł��B��Q���N����O�ɐg�̉���_�����ď\�����ӂ��ĉĂ̊��Ԃ����C�ɂ��߂������������B�@
��7�����i2017�N7��3���j
�@�@
�@�@�@����́u���䑏���l�i���Q�X�A���ŘA���X�g�b�v�v�A�����́u���r�S���q��������s���t�@�[�X�g�̉�s�c�I�ň��|�I�����v�̃j���[�X�ł�������ł��ˁB
�@�@�@���w�R�N�A�P�S�Ƃ�������l�i�ɂ��Ă͓V�ˊ��m�ƕ]����A�ނ��ǂ�Ȏq�ǂ��ŁA���c�������ǂ̂悤�ɉ߂��������A�ȂNj����[�����グ���Ă��܂��B�w�Z�ł͂ǂ�Ȑ��k�ŁA���Ƒԓx�͂ǂ̂悤���A�ƒ�ł͂ǂ�Ȃ�������ł�����ł������A�킪�q��l�i�̂悤�Ɉ�Ă����Ƃ����e�����납��A�c�����ɋC�ɓ����ėV��ł����Ƃ����������Ⴊ�X����������A��������܂Ŕ̔��\�E�����Ă��邻���ł��B
�@�@�@�l���ꂼ��A�\�l�\�F�ł�����A������������A���������������Ƃ��Ă��A�ނ̂悤�Ɉ���ǂ����́H�H�H�ł���
�@�@�@�e���q�ɂ�������҂▲�͂قق��܂���������܂��B�u�\�Ő_���A�\�܂ōˎq�A��\�߂�������̐l�v�Ƃ����̎����ꂪ����܂����A�U��Ԃ��Ă݂�Ǝ����̎���ɂ����Ă͑����̓V�˂����������Ȃ��A�ƂȂ������ȋC���Ƌ��Ɏv�������܂��B�O�̍��ɂ��łɃA���t�@�x�b�g�𗝉����A�{���X���X�����Ǐo�����`�����A���������T�b�J�[�����ӂŏ����͂i���[�K�[�����I�A�ƃ}�}�F�̊��҂��W�߂Ă����a����A����ׂƂ����킯�łȂ��A���������Ƃ肵�Ă݂�ȂƊy�����߂����Ă������lj��̎����ɂ��K���ꔭ�ō��i���ď���ɂȂ����b�����B�{���ɂ��낢��Ȉ炿���A��������������̂��Ȃ��Ƃ��̔N�ɂȂ�Ƃق̂ڂ̂Ǝv�������܂��B�ܘ_�A�]���ƌ����鐶�����������F�B�����܂����ǁB
�@�@�@�N�ł����Ă��u����l���܂ɕt���A������̐l���v�ł�����A�l�Ɍ����ĂłȂ����炪���������Ƃ������āA�y�����撣��p���F�߂���Ƃ����ł��ˁB�Ђ悱�ۈ牀�̎q�ǂ������ɂ͍D���Ȏ��A��肽�����Ƃ����t������͂Ƌ@���ł�������ȂƎv���܂�
��6�����i2017�N6��1���j
�@�@
�@�@�@�U���ɂȂ�ƁA�u�₪�Ĕ~�J�̒��J�������āA���̓v�[���V�т��n�܂�Ȃ��v�ƕۈ�҂̓C���[�W���Ȃ���ۈ�v��𗧂Ă܂��B�U���͕ʖ��u�������v�ł����A���������̂ł͂Ȃ��u���̌��v�Ƃ����Ӗ�����������A�A��ł́u�c�A�����I����Đ��鎞���ł��邩��v�Ƃ�����������悤�ł��B
�@�@�@��ʓI�ɂU���́u�~�J�E���������E�J�^�c�����E������v���K�{�A�C�e���Ƃ��āA�ۈ��ʂɂ����Γo�ꂵ�܂��B���N�͓��ɁA�c���N���X�ŃJ�^�c�������l�C�҂Łi�N���X�����ɓo�ꂵ�Ă��܂������O�ۈ�ŕ߂܂��܂����B�j�q�ǂ������������Ă����b���Ă���悤�ł��B���Ƃł���������₨�ꂳ�����������Ő}�ӂŒ��ׂ���A�a�̗p�ӂ������肷��l�q���z���ł��Ăقق��܂����v���܂��B�q�ǂ��̋�����S�Ɋ��Y���Ă��������Ă��肪�Ƃ��������܂��B
�@�@�@����ȓ�����̂����₩�ʼn��₩�Ȋւ���y��Ƃ��Ďq�ǂ������̏�ʂ̈��肪�����܂����A�z���͂�A�Ȋw�I�D��S�Ȃǔ�F�m�I�\�͂��O�[���ƐL�тĂ������Ƃ������̕ۈ���H�������Ă��܂��B���ƂȂł͓�����O�ɂȂ������̂���l�X�Ȃh�s�@��̎g�p���A���ł͗c���̊Ԃɂ��Z�����Ė{����������G�ꂽ�肷�邱�ƂȂ��A�X�}�z��r�f�I�ŏ��߂Č�����̌������肷�邱�ƂŁA���������{����m���Ă���l�ȋC�ɂȂ��Ă��܂��܂��B
�@�@�@�Ђ悱�ۈ牀�̎��ӂ͌�����Βn�Ɍb�܂�Ă���A�����Ȏ��R�ɓ��X�G�ꍇ�������o����͍̂K���Ǝv���Ă��܂��B�o�b�^��J�^�c�����A�Z�~�Ȃǂ̂������ʂ̍��������s�X�n�ł͖ڂɂ��邱�Ƃ��o���Ȃ��Ƃ��������̂ł�����B
�@�@�@�g�̉��̏����Ȏ��R�ɂǂ��Ղ�ƐZ����A�����̖ڂ���S�g��ʂ��Ċ����邱�Ƃ��A���͂̂�т肨���Ƃ�ł����Ă��A�����̎����Ɍ����Đ�L�т���m�́A���ł������Ŗ����m�b����ނ̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�@�@�@�O���[�o�����ɑΉ����ď��w�Z�ł��p�ꋳ�炪���������悤�ɂȂ�A�c������Y�Ƃ��������ĉp�ꋳ���Ȃǂ�W�J���Ă��܂��B����܂��܂����Ԃ�������Ǝv���܂��B�p��ɐG��邱�Ƃ͗ǂ����Ƃ��Ƃ͎v���܂����A�l�X�ȑ�l�̎v�f�Ɏq�ǂ��������U���Ȃ�������ȂƈĂ��Ă��܂��B
��5�����i2017�N5��1���j
�@�@
�@�@�@�S���Q�X���i���a�̓��j�ɑ�P�T��Ђ悱�܂���J�Â��܂����B�A�x�͓V��s���̓V�C�\�o�Ă����̂ŁA�C�����݂܂������A�����͐�������Ɛ���n��A�q�ǂ������ƂȂ��C����X�ł݂�ȂƂĂ������\������Ă��܂����ˁB������^�[�t��������Ă����������ی�҂̊F���肪�Ƃ��������܂����B�R���ɑ��������q�ǂ��������قƂ�ǂ��Q�����Ă���āA������ƏƂ�Ȃ���ĉ����э����Ă��܂����B�u���P�̕ǁv�ƌ����܂����A�q�ǂ����e�����̌��ςő�ςȋ�J�̐^���������ɂ���̂��낤�ƁA�ɂ��ɂ������Ί�̐e�q�ɃG�[���𑗂肽���C�����ɂȂ�܂����B
�@�@�@���w�Z�ɓ��w�����Ƃ���A���ی�̋��ꏊ�T���⍧�k��Őe�̏o�Ԃ�������̂ŁA�F����u�ۈ牀�ł͊y�������Ă�����Ă�����ł��ˁv�Ƃ������Ⴂ�܂����A���a�ɐ����������Ƃ��Ắu�y�́~�A�e���q�ǂ��̎��ŋ�J����͓̂��R�I�v�Ǝv���Ă��܂��B�ł��A���̏�Ō����ƁA���̂������ł͊p�������ɂȂ肩�˂Ȃ��̂ŁA�u�����Ƀ`���b�N�v���Ă��܂����E�E�E�B�����ɂ͂��ނƂ���ł͌Z�o�̊w�Z�s���ɘA��čs���Ă��炦�Ȃ����̎q�����������ł��B�������Ɏ肪�|����A��̎q�ɍs���͂��Ȃ��Ƃ�����������̂ł��傤���A�c���q�ǂ������ē��R�ł����ɂ������s�����Ă��炦�Ȃ��Ƃ́u�ʂ����ĉƑ����ĉ����낤�H�c���q�ǂ����Ȃ����d�g�݂��ăA���H�v�Ǝv���܂��B�ނ��A�c���q�ɋ�����Ȃ���A���ƂȂ������������ꂪ����̂����R�ł����B���̏����s�������������̑Ή��łȂ������悭�ĉ����_���Ȃ̂�������ƍl���邱�Ƃ��q��Ăł͑���Ǝv���܂��B
�@�@�@��N�S������S���Łu�q�ǂ��q��Ďx���V���x�v���X�^�[�g����N�o�߂��܂����B�V���x�ł́u���ꂻ�̑��̕ی�҂��q��Ăɂ��Ă̑��`�I�ӔC��L����v���Ƃ���{�F���ɂ��Ă��܂��B�ۈ牀�ɓ���Ȃ��q�ǂ��A�s�҂��Ă���q�ǂ��A�Ǘ������玙���������Ă���e�q�ȂǕ�I�Ɏq�ǂ��̍őP�̗��v��Nj����鐧�x�Ƃ������ł����A���x��������s���Ď��Ԃ������A�Ƃ������ɂȂ�Ȃ��悤�ɁA�s�����J�����Ǘx�炸�A�ƂȂ�Ȃ����߂ɂ͏����ȒP�ʂ̑g�D���灁�Ђ悱�ۈ牀����q�ǂ��ɂƂ��čőP�̗��v�����߂�C�^����Ăčs���܂��傤�B��{�I�ɂ͊e���ƒ�̐ӔC�ɕ����̂ł������{���ɑ�ςō����Ă��鎞�ɂ́A���݂�����������L�������ƁA�ł��A������Ƃ����H�v�ŏ��z������Ƃ���͂�����Ă݂�E�C���K�v�Ȃ̂�������܂���B�u�ǂ����Ă������I�v�Ƃ����ꍇ�ɂ̓N���X�̒S�C�Ȃ艀���܂ł����k���������B
��4�����i2017�N4��1���j
�@�@
�@�@�@�@�i���E�������߂łƂ�
�@�@�@�R�����͂��킩�ꉓ���A���킩��p�[�e�B�[�A�������j������o�āA�i�����ł͐V�����N���X�ƒS�C�ۈ�m�\���ĔN�x���̎�ȍs�����I���邱�Ƃ��o���܂����B�q�ǂ������͈�A�̗����ʂ��āA�c���Ȃ���Ɉ�傫�Ȏq�̒��ԓ��������C�ɂȂ��Ă���悤�ł��B�������j����ł͂Q�R���̐V���������}���āA�V���邩�̎q�ǂ������Ɂu�ނ���łЂ炢�āv���̂��Ċ��}���Ă��炢�܂����B�Ԃ����{�ԂȂ̂ɑ吨�̕ی�҂̑O�œx�����_�Ŕ�I���Ă���܂����B�Q�ȉ̂��I����Ă��܂��܂��̂��������ɂ��Ă���V���邩����A�V�������Ƀ��_�����͂肫���ēn���܂����B
�@�@�@�ۈ�ŏI���ɂ͒Z�k�ۈ�̂����͂����肪�Ƃ��������܂����B�Ђ悱�ۈ牀�ł͔N�x���Ō�̓��܂Ŏq�ǂ������ɂ͓��������ŁA�����Ɠ����悤�ɉ߂����������A���ɑ������Ă��������炮�݂̎q�ǂ��������u���ꏊ���Ȃ����v�������Ƃ̂Ȃ��悤�ɁA�Ƃ����v��������̂ŁA���N�R�P���̗[������ˊэH���̂悤�ɐV�N�x�������s�����Ƃɂ��Ă��܂��B�Z�k�ۈ�ɂ����Ă����������������ŁA�W�����ďo�����̂ő啔���͐V�N�x�d�l�ɂȂ�܂����B���Ȃ��ۈ玺�ł��S�C�ɂ���Ċ��\�������Ȃ�ς��̂ŁA���N�x�͂ǂ�Ȃӂ��ɂȂ�̂��y���݂ɂ��Ă��Ă��������B
�@�@�@�Ђ悱�ۈ牀�͍��N�x�n�����ĂP�T�N�ڂɓ���܂��B�u��\�L�܂ɂ��Ċw�Ɏu���v�Ƃ͘_��ɂ��閼���������ł����P���ɍs�����Q�X�N�x���߂̐E����c�Łu�q�ǂ����悭�݂邱�ƁB�܂��͎q�ǂ�������āA�����Đ�Ԃ����Ɓv�̑����^�ۈ�m�̌��C����������ɂ��Ȃ���_�c���܂����B�E����c�̌�Łu����ς�����Ȃ�������I�I�v�@�Ƃ����Ⴂ�ۈ�m�����̌��t�Ɂu�K��悢�X�^�[�g������v�Ɗ������v�������ł����B���N�x����낵�����肢���܂��B
��3�����i2017�N3��1���j
�@�@
�@�@�@�挎�ɂÂ��ăh�b�W�{�[���Ŋ��������ƁE�E�E�����A���ԏ�ł����炮�݂̎q�ǂ������ƐE���ƂŃh�b�W�{�[�������܂����B�ۈ炩�炿�傱���Ɣ�������ۈ�m�������H�������������ɋ삯����ƁA�q�ǂ������́u��ɏ����[�v�ƁA���u���X�ł����B�ǂ̎q�ǂ��̊�����̎����ɂȂ�ƁA�����������w�Z�ɓ��w����ɂӂ��킵����������Ƃ����\��ɂȂ��ė��Ă��邱�Ƃ����߂Ċ����A�c���ꂽ���Ԃ��킸���ł��邱�Ƃ��₵���������܂����B
�@ �@�u��������̓h�b�W�{�[���ł���������������ł���v�Ƃ͒S�C�̕قł����A�m���Ƀ{�[������ɂ��ĈȑO�́�������͑z���ł��Ȃ��قǂ̓��u�ƋC�����݂��܂����B��l�ЂƂ�̌������ɂ߂Ă̕ۈ�ƁA���ƒ�ł̕ی�҂̐[������₢�����Ă����A�q�ǂ������͌��S�Ȕ��B�Ɛ����������̂ł��ˁB��������̐^���ȕ\������Ȃ���A�ӂƁA�ނ̂�������₨�ꂳ��̊炪�����т܂����B
�@�@�@���̐����A�}�X�R�~�ł͖^�w�Z�@�l���c�t���̋�����e�ɂ��āA�傫�����ꑛ����Ă��܂����A���w�̌��w���O�͎��R�Ƃ͂����A�l�Ԑ��̍������ƂȂ�c�N������������́u�l�Ƃ��Ă���ׂ��p�v�̊�b��̂ɐ��݂��Ă����d�v�ȏ�Ȃ̂ł�����A����̌��_�ɗ����ďn�l���đΏ�����ׂ��ł��B
�@�@�@�Ђ悱�ۈ牀�͗��N�x�n���P�T���N���}���܂��B���̊Ԃɉ���ł̓P���L�̖��傫���}���g���A�V���{���c���[�Ƃ��Ă̕��i���\���ƂȂ�܂����B���̖͌��݂̂Ђ悱�ۈ牀�̑O�g�������Ђ悱�ۈ玺����̕ی�҂̕��ɂ���t�ŋL�O�A�����ꂽ���̂ł��B�ċG�ɂ͎q�ǂ����������O��������؉A�ƂȂ�A�Z�~����������W�܂��Ďq�ǂ��������y���܂��Ă���܂��B�݂�Ȃ��y����ł���ؐ��A�X���`�b�N�͂��낻��K�^�����āA��K�͏C�U������\��ł��B����Ȃ��Ƃ�������o�I�ɂ͂����Ƃ����ԂɎ�������Ă����悤�ł����A���Ԃ͒����Ɍo�߂����Ȃ��ƋC�t������Ă��܂��B
�@�@�@�ʂ����đn���ȗ��A�Ђ悱�ۈ牀�̕ۈ�̎��͌��サ�Ă���̂ł��傤���B���Ԃ̘Q��͖��������̂ł��傤���B�P�T�N�ڂ�ڑO�ɐU��Ԃ�Ȃ���ۈ�����̂��݂A���P���Ă����C���X�ł��B
�@�@�@���̂P�N�̊ԂɁA����⎖�̂Ȃǂł��S�z���������������Ƃ��������Ǝv���܂��B���l�тƋ��ɁA�����������͂����������肪�Ƃ��������܂����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
��2�����i2017�N2��1���j
�@�@
�@�@�@�G���g�����X�̃X���C�h�V���[�ł����ɂȂ������Ǝv���܂����A����A�����炮�݂��ߗוۈ牀�Ƀh�b�W�{�[���̉��������ɏo�|���đS�폟���I�I�ł����B�����͂ǂ��ǂ��ْ����ɂǂ��Ղ�ł������A�A��͑������y�������̗Y���т������āE�E�E�B�I�����s�b�N�̋L�����܂��c���Ă���̂��꒚�O�̃A�X���[�g�̋C���ł��B�q�ǂ������͂����ԑO����u��ɏ����Ă��[�v�Ɛ킢���[�h�ɃM�A�`�F���W���Ă��܂����B�h�b�W�{�[�����͂��ƂȂ̑����炷����قǂ̘J�͂������Ă̑傫�ȍs���Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A�ۈ�̓��퐫�𗐂��Ȃ��Ƃ����z���̂��Ƃł̃~�j�s���ł����A�q�ǂ������ɂƂ��Ă͑傫�ȃ`�������W����萋�����B�����ɐZ���s���̈�̂悤�ł��B�u�{�[���ĂĂ�������I�v�Ƃ����܂��Čւ炵���Ɍ��q�ǂ��̊�͂��炫�炵�ė�������������A���炵��������A�悭�������܂ő傫���Ȃ��Ă��ꂽ�A�Ɗ������܂��B�@
�@�@�@�Ђ悱�ۈ牀�ł͓���̃X�|�[�c�ɗ͂�����Ƃ������A�����A�O�Ŏv�������ɑ̂����āA�����̍D���Ȏ������ėV�Ԃ��Ƃɏd�_��u���Ă��܂��B�������A�����Ȃ��Ƃ���ł̕ۈ�m�����̕ۈ�̂˂炢��z�������Ă̂��Ƃł����A���R�C�܂܂ɉ߂����Ȃ�����A�q�ǂ������́A���ɂ�������h�b�W�{�[���A�T�b�J�[�A�����Ȃ�Ȃǂ݂�Ȃŋ��͂��邱�ƂŊy�������{�����邱�Ƃ�̂Ŋo���Ă���Ă���A�Ƃ������ł��傤���B�u�Ђ悱�̎q�̗͑͂�����v�Ƃ悭�����܂����A����������ł��B
�@�@�@�������O�œ������Ƃ�������O�ɂȂ��Ă��錻��ɂ́A���c����1���̔������߂����ۈ牀�͓��c�����̐����ŏd�v�ȃ|�X�g���߂Ă��܂��B�����A�O�V�т��������ł̗V�т������Ղ�y���݁A�������������ċ��H�̐搶�����S�Â����̋��H�����������H�ׂāA���S���Ă����Q����A�����������ɂ��ĂЂ悱�̎q�ǂ������͈���Ă��܂��B
�@�@�@���C�����ς��ɓ�����̗́A�l���Ȃ��琶������m�́A�������邱�ƂɑO�����ɂȂ��C�́A�l�̋C�����̕�����S�̗́A�������܂��ċ����ď��āA���J��Ԃ��Ȃ��炯�Ȃ��ɐg�ɂ��Ă���̂��Ȃ��Ɗ����Ă��܂��B
��1�����i2017�N1��4���j
�@�@
�@�@�@�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��B�N���N�n�������x�݂������������肪�Ƃ��������܂����B�Ζ��𑱂����Ă����ی�҂̕��ɂ͂��q����̕ۈ�ɂ��đ�ς��������ƂƂ��@�����Ă��܂��B�\����܂���B�ۈ�m�����͂��ꂼ�ꎩ�R�ɉ߂����āA���t���b�V���o���܂����B�V���ȋC�����ň�l�ЂƂ�̎q�ǂ��ƌ��������ĕۈ�ɗ�ނ��Ƃł��Ԃ��������Ǝv���܂��B
�@�@�@���č��N�͓єN�ł����A���x�ł͒��сi�Ђ̂ƁE�Ƃ�j�Ƃ��������ŁA���Ɠт���������g���ɖ������N�Ƃ�������悤�ł��B�т͌{���Ӗ�����̂łЂ悱�ۈ牀�̔N�ł����邩�ȁA�Ȃ�Ă������Ă��܂��B�u�{�v�Ƃ����ƌ��邩��ɃR�b�R�A�R�b�R�����Ȃ��点�킵�Ȃ�������肦�������ގp���v�������ׂ܂����A��N���̐����̎p�␢�E�̏���S���������Ȃ��������ω��ɂ������悤�ɁA���N�͍X�ɂ��킵�Ȃ��o�T�o�T�ƉH���𗧂Ăē�����肻���ȋC�z�ł��B
�@�@�@�S������͑n�݂��ĂP�T�N�ڂ̐ߖڂ̔N�ɂȂ�܂����A�����̊ԑn��10���N�L�O�̉���s�����悤�ȋC�����܂��B�N���������ɂ�A���Ԃ����̂��Ȃ��ƂĂ������Ȃ����Ɗ�����̂��A���邢�͕�����ۈ���߂����̕ω������������Ă���̂��A�����{���ɑ�Ȏ������������茩�ɂ߂āA�Ђ悱�ۈ牀�̕ۈ���������莩�ȕ]�����Ȃ���i�߂Ă����K�v���������Ă��܂��B�q�ǂ������̐g�̉��̕ۈ���͕ۈ�҂̐ӂɕ����Ƃ��낪�傫���̂ł����u�ς��Ă������E�ς��Ă͂����Ȃ����v��ۈ�ҏW�c�̘b�������̒��ŋᖡ���A�ی�҂̊F����̃A�h�o�C�X���������������Ǝv�����ł��B���N����낵�����肢�������܂��B
��12�����i2016�N12��1���j
�@�@
�@�@�@���N�̓~����21���i���j�A�u1�N�ň�Ԓ��Ԃ��Z���������̏o���x�����̓��肪�������v�Ǝv���Ă������ԈႢ�ł����B���̂���11��������12�����߂��ł������Â��Ȃ邻���ł��B�{����4���߂����炾��Â��Ȃ�n�߂�4�����ɂ͂����^���Âł��ˁB���ƂȂ͂����肪�Â��Ȃ��Ă���ƂȂC���킵���Ȃ��Ă���̂ł����A�q�ǂ������͂���Ȃ��Ƃ��\���Ȃ��ňÂ������Q�K�̃f�b�L�łł����͂��Ⴌ�ł��B�Â����ŗV�ԂƂ����͓̂��ʊ�������悤�ł��B�����������k��Œx���Ȃ鎞�ɂ͒��Ԉӎ����q�[�g�A�b�v���Ă����ɗւ������Ă͂肫���Ă��܂��ˁB
�@�@�@�����Ȃ��Ă��܂������A�ǂ̃N���X���ߑO���ɂ��������̌����𐧔e���ĉ���Ă��܂��B���ꂼ��̌����Ɋy���ރ|�C���g������A�����V��Ȃ��Ă������ɂ�����̂��������猩���ėV�ѓ���ɂ��Ă��܂��V�˂����������Ă���̂ł�����A2���Ԃ�����������V��ŋA���Ă���Ȃ�A���H�̃T���v���P�[�X�������āu�����I�����̓u���卪�����i���Ԃ��ȁ[�j�v�A�u������[�I�J���[�����v�Ƃ�낱�Ԏq�ǂ������͂ƂĂ����������A���Ă��ł��B�܂��Ɂu�V�т�����Ƃ�ꂯ�ށ@�Y�ꂹ��Ƃ₤�܂ꂯ��@�V�Ԏq�ǂ��̐������@�킪�g���������������v�ł��B
�@�@�@�ŋ߁A�o�|������̌����Ő܂ꂽ�S�p�C�v��Ƃ������B�ȂǑ傯���Ɍq����댯�Ȕp�ނ₲�݂��U�����Ă��邱�Ƃ��ڗ����܂��B�C��������A�y�؎������ɘA�����ď������Ă�����Ă��܂����A�����ɂ���Ă͊Ǘ����s���Ƃǂ��Ă��Ȃ�������A�q�ǂ��������̂т̂тƑ�_�ɗV�ׂ�L�����Ȃ�������A�Q�[�g�{�[���ȂǂŐ�L����Ă��Ďg���Ȃ�������Ǝq�ǂ��������O�V�тő̗́A�ؗ͂����悤�ɂ������R�����Ɗ����܂��B�c�����̎q�ǂ��̉^���\�͌���ɂ͓��ʂȃX�|�[�c�ł͂Ȃ�������̗V�тŕ����A����A���ԁA������A����Ȃǂ̊�{������\���Ɍo�����邱�Ƃ���ƌ����Ă��܂��B�ۈ牀�ň�q�ǂ��A�ƒ�ň�q�ǂ��A�݂�Ȃ��Ƒ��ƈꏏ�ɋC�y�Ɋy���߂�����g�߂ɏ\���ɐ��������Ƃ����ł��ˁB
�@�@�@���N���c�菭�Ȃ��Ȃ�܂����B���N�����S�ł���ۈ牀�Ɍ������ė�݂܂��B�����͂��肪�Ƃ��������܂����B
��11�����i2016�N11��1���j
�@�@
�@�@�^�������ق�ȂǂP�O�����ʂ�s�����I���܂����B�ǂ�����V�C����Ȃ̂ŋC�����ވ���ŁA�u�v���ʂ�ɂȂ�Ȃ����Ƃ����邳�v�Ƃ����C��������A�ł������y���߂Ďq�ǂ�������ی�҂̕��X�̏Ί炪���������Ăق��Ƃ��Ă��܂��B�^����ɂ͑吨�̕ی�҂̂����͂����������Ă��肪�Ƃ��������܂����B����ς�s���́u�݂�Ȃŗ͂����킹�đn��グ��v�Ƃ����̂���햡�̈�ł�����܂��ˁB�܂��A�A���P�[�g�̉��S�S�ƒ납�炢���������肪�Ƃ��������܂����B�l�X�Ȃ��ӌ��₲�v�]������܂������E���ԂŌ������āA���P���ׂ��Ƃ���͉��P���Ȃ��痈�N�x�ւƌq���Ă����܂��B�������Ȃ���A���ɐV���������������ƒ�ɑ��Ă̎��O����������Ȃ������̂�������܂��A�J�Â̓����ȂǏ������ύX�ł��Ȃ��Ƃ��������A�Ђ悱�ۈ牀�̍s���ɂ��Ă̍l������j�A����ї��N�x�Ȍ�ɕύX���邱�ƂȂǍ��k��ł��b�������Ǝv���܂��B
�@�@�P�P���͗��N�x�̕ۈ珊���p�\�����n�܂�܂��B���x���ς���ĊԂ��Ȃ����߂��A�u�ۈ珊�����p�ē��v�������Ԃ�{�����[���������Ă��܂��B�����\���ɐ旧�ۈ珊���w�⊵�炵�ۈ�A���H��̕��S���ɂ��ĂȂǐ̂͂���Ȃɏڂ����L�ڂ���Ȃ������������A�u�͂��߂ɂ��m�F���Ă��������������Ɓi�d�v�j�v�Ƃ��ċL�ڂ���Ă��܂��B�@
�@�@���l�s�ł͗l�X�ȕۈ�{�݂��ł��Ă��܂����A��������������ɂȂ��Đe�̊��҂����ۈ���e�ƕۈ珊�̕ۈ痝�O�Ƃ̃~�X�}�b�`����ی�҂ƕۈ珊�Ԃł̃g���u�������������߂��Ǝv���܂��B
�@�@�Ђ悱�ۈ牀�ł������̂悤�Ɍ��w�҂��������܂����A�G���g�����X�̂s�u���j�^�[�ɕی�҂����͂��ă^�[�t��������Ă���Ƃ����Ȃ܂�ɉ���łǂ�ɂȂ��Ă����ʂ𗬂��Č��Ă��������Ă��܂��B���ӂɂ͂��낢��ȕۈ牀������܂����A�Ђ悱�ۈ牀�ł́u�q�ǂ��̗V�тɂ͓y�Ɛ��Ƃ����l���������Ȃ��v�Ƃ��Ă��邱�Ƃ�ی�҂Ƃ̋������d�����Ă��邱�Ƃ����w�҂ɂ͂�����Ɛ������ĕۈ���e�̏������Ă��܂��B�q�ǂ��������ǂ�܂݂�ɂȂ��ėV�ԗl�q�ɖڂ��L���L��������l������A�����ȂƂ����\��̐l������A���ƒ�ł̎q��Ẳ��l�ς��l�X�Ȃ��Ƃ����������Ă��܂��B
�@�@�u����āv�Ƃ������t������܂��B���������ی�҂ƕۈ�҂����͂������Ďq�ǂ�����������������������Ă鎞�ɁA�q�ǂ������͐S����ۈ�҂�M�����Ĉ��S���Ă̂т̂тƈ���Ă����̂ł��傤�B
��10�����i2016�N10��1���j
�@�@
�@�@�J�͗l�ɍʂ��Ă��邤���ɁA���̊Ԃɂ��Z�~�̖������������Ȃ��Ȃ�܂����B���Ƃ����Đ����ɒ��̉��������Ƃ������܂ɂ͂��܂��Ȃ炸�A���Ƃ��s���S�R�ẲĂ̏I���ł����B9�����͋ߗZ�̉^��������\�肳��Ă��܂������A���߂���������グ�Ă���q�ǂ��������吨�ł����B�V��ɍ��E�����s���͎�Â��鑤���Q�����鑤���{���ɑ�ςł��ˁB
�@�@�Ђ悱�ۈ牀�̉^����͖��N�̈�̓��ł����A1964�N�̓����I�����s�b�N���s��ꂽ������1��̑̈�̓��ƂȂ��������ł��B���̍��͔�r�I�J�����Ȃ��̂ő̈�̓��Ƃ����悤�ł����A�ߔN�͉��g���ɂ��܂��܂����������������������̂ŗv���ӂł��ˁB�Ƃɂ����������ꂳ��ȂljƑ��̐l������A�F�����A�ۈ牀�̐搶�����݂�Ȃ��W�܂��ĂȂ��y�������ɑ̂����Ă����ʂ͕��a�łقق��܂����Ǝv���܂��B�c���ɂȂ�Ə������A�������ʼn����܂𗬂���������܂����A����Ȃ��ƈ������������̂Ȃ������̗ƂɂȂ�Ȃ��Ɩ��N�q�ǂ������̎p���狳�����Ă��܂��B���V�C���x�����Ă݂�Ȃʼn^������y���߂�Ƃ����ł��ˁB
�@�@���N�s���Ă������ق�_������N�ŏI���ɂȂ����̂ŁA���N�͒n��̕��̌�D�ӂō��]�˒��̔������肵�Ĉ��ق�����邱�ƂɂȂ�܂����B���܂ł̂悤�Ȃ��ٓ��������ă}�C�N���o�X�ōs���āA�A��Ɏl�G�̐X�����Ɋ���ėV�ԁA�Ƃ����̂Ƃ͈������ł����A���̑���A�Ă̊Ԃ̓g�}�g��Ȃ��A�I�N����A���Ď��n���Ė��키�Ƃ����̌����ł��܂����B�ۈ�m���F�A�������Ƃ̌o�����Ȃ��҂���ł����A�����������n�̊�т𖡂킦�܂����B�����Ǘ����Ă�����Ɂu�Q�l����ǂ�ŕ����Ȃ��Ƃ��߂���B���͂���ȂɊȒP�ł͂Ȃ���v�Ɛh���̂����t�����������܂����B
��9�����i2016�N9��1���j
�@�@
�@�@�������̑䕗�Ɍ�����ꂽ�W���ł����B���������̉ċx�݂���J�ɂ�����ꂽ���ƒ�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�W�����߂ɓs�}����̂j�ۈ牀�ōs��ꂽ���J�ۈ�ɉ����ƕۈ�m�Q�����Q�����܂����B�����ۈ玺�̈�Ƃ��ďd�����Ă���A���N�A���ɂ��ۈ��A���H���Ă���ۈ牀�ŁA�S�����猩�w�҂������K��Ăs�u��ۈ�֘A�̏����ɂ��������グ���Ă���A�m��l���m��ۈ牀�ł��B�������x���K�₵�Ă��܂����A���̓s�x�V���Ɏ肪�������i���������Ă��鎖�ɋ��Q���Ă��܂��B�Ђ悱�ۈ牀����͕����Ă��P�T���قǂȂ̂ɁA�S���̕ʐ��E�̎�ł����B�Ђ悱�ۈ牀�ł͂��ƂȂ������̐E���ɒǂ��Ă��銴�������A����̂Ȃ��悤�ɂƈ��S�ۈ�ɌX�������ł������ŁA�q�ǂ��������肽�����Ƃ��v��������肫�邱�ƂŁu�l�Ԃ炵���������Ă����q�ǂ��v�A���ƂȂ͐Â��Ɍ����A�Ƃ������̕ۈ牀�̕ۈ痝�O�͂܂Ԃ���������܂����B
�@�@������Ƃ�������ł��傫�ȃg���u���ɂȂ�������ł́A����������Ȃ��悤�ɂƂ��ƂȂ����肵�Ĉ��S���S�D��ɑ��肪���ł��B���ƂȂ̎�̂Ђ�͈̔͂̒��ł̖`������������Ȃ��ۈ�́A�{���Ƃ��đ傫��痂����炿�������Ă���q�ǂ������̐S�Ƒ̂ɂƂ��Ă͞g�ɂȂ��Ă���̂ł��傤�B�ŋ߂͂���ȕ����ɋ^��������ƂȂ������q�ǂ������̖`���S������悤�ɂƁA�e�n�̌����Ŗ�V�т����R�ɂ�����̃v���C�p�[�N���J�Â��Ă��܂��B��肽�����Ƃ��Ƃ��Ƃ��肫���ĉ���������Ƃ��Ă��A�ӔC�͎����ɂ���Ɣ[���ł������A��肽�����Ƃ��\���ɂ�錠���Ƌ��ɁA�������Ȃ����Ƃ��݂�Ȃ̗��v�̂��߂ɂ͂���Ƃ����`�����ʂ������o�����g�ɂ��Ă����̂ł��傤�B
�@�@�����Ō��߂čs������q�ǂ��͎��Ƃ��Ă��ƂȂ̎v���Ƃ͈قȂ��������ɐi��ł��܂��č��邱�Ƃ�����܂��B������ƂȂ̌����������݂̂ɂ��Ă��܂��q�╷�������̂悷����q�͂��ƂȂɂƂ��Ă͈����₷���ǂ��q�Ȃ̂ł��傤����l�ЂƂ�ʓI�Ȑl�i�̐l�ԂƂ��Ă̈炿�͂ǂ��Ȃ낤�Ǝv���Ă��܂��܂��B���ƂȂ��猩��Ηǂ����Ƃ��������Ƃ��A���܂�Ă��点�������Z�N�̎q�ǂ����猩��ƑS������Č����Ă���̂�������܂���ˁB
�@�Ђ悱�ۈ牀�ł��ǂ�ɂȂ��ĉ���ŗV�ѕ����Ă���q�ǂ������̕\��͎��M�ɖ����ċP���Ă��܂��B�Z�~��߂܂��ėF�����Ɗ���ĉ����b�������Ă���p�͂ƂĂ��قق��܂������͓I�ł��B�[���ɗV�т����Ė��������q�ǂ������͕ۈ�m�̌��t�ɂ����Ȃ��Ɏ����X�����Ƃ肪�ł��܂��B���ƂȖڐ��Ŏw�����o������łȂ��A�q�ǂ��̎v�������ݎ��Ȃ��疞���ł���V�т̊��𐮂��Ă��������ł��B�@�@�@
��8�����i2016�N8��1���j
�@�@
�@�@���A�V�����⒓�ԏ�̂킫�ɋ�����œ��X�Ƃ����p�Ńq�}�������炢�Ă��܂��B�����{��k�Ђ̕����x���ɂƕ����Łu�Ђ܂��v���W�F�N�g�v������������A�����̏ے��Ƃ��ăq�}�����̉Ԃ��炩�����A�u�ӂ����܁v�����[���Ɗo���Ă������Ǝ킪�z���đS���ɍL�܂�܂����B��l�̕ی�҂̕�����u�Ђ悱�ۈ牀�ł��ǂ����v�Ǝ�������������̂łT���̏I���Ɏ���܂��܂����B���ԏ�͔S�y������̌��z�c�y�������̂ʼn���Ɉڂ��ēD�c�q�Â���ɗL�����p���邱�Ƃɂ��āA���|�p�̓y�����ւ��Ă������܂��܂����B�����������������Ă��������Ȃ̂ɁA�����ɑo�t���萶���A�����������͂ł���ƐL�тđ�ւ̉Ԃ��炩���Ă���܂����B�q�ǂ��������C�ɓ����Ă���悤�ŎU���̐܂ɂ������茩�Ă��܂��B�u���Ȃ����������Ă���v�Ƃ����̂��Ђ܂��̉Ԃ��Ƃ̈�ɂ���悤�ł����A�^�Ă̏�M�I�ȑ��z���������ԂƂ��ăC���p�N�g�������ł��ˁB�킪��ꂽ��q�ǂ������ɔz���ė��N���ƒ�ł��炩���Ă������������Ǝv���Ă��܂��B
�@�@�܂��A�P�X�l���̑��������D����Ƃ����Ռ��I�Ȏ������N���Ă��܂��܂����B�V���̂P�ʂ߂đ傫��������Ă��銈�������āA���܂�̂ނ����ɋp���Č�������������Ă��܂��v���ł����B�������A�f��⏬���ł͂Ȃ��`�������邱�Ƃ̂ł��Ȃ������ł��B�u�Ȃ�����Ȃ��Ƃ��N�����̂��H�v���𖾂��邽�߂ɂ��ꂩ��w���o���҂�_�Ȉ�A�x�@�W�҂��������Ԃ������Č����Ă����̂ł��傤�B��ςȂ��Ƃł��B�ł��A�����Ƃ͖����̂Ƃ���Ő����Ă���Ǝv���Ă��鎄����������̐[�w��T���Ă������Ƃ����߂��Ă���̂�������܂���B�@
�@�@���̓x�̐��S�Ȏ����̊j�S�ƂȂ��Q�҂⍂��҂ɑ���₽���܂Ȃ���������������������Ȃ����߂ɂ́A�L���L�����������̒��ŁA�C���C���������o���玩�R�ɂȂ��āu�������F��������Ɂi�s�}�Ђ悱�ۈ牀�ۈ�ڕW�j�v����邵����l�ЂƂ肪�S�����Ă������ƁA����̐����̒��Ŏ��������l���������Đ����Ă��鎖�ɋC�t�����Ƃ��A����������ۈ�̒��Ŏ��H���Ă��������Ǝv���̂ł��B�ۈ�ōŏd�v�ۑ�ƂȂ�u���ȍm�芴�v����Ă邱�Ƃ͎q�ǂ��ɂ͂������ł������X���C���̑�l�ɂƂ��Ă���Ȃ��ƂƎv���܂��B�@�@
�@�@
�@�@
�@�@
��7�����i2016�N7��1���j
�@�@
�@�@�~�J�̍��ɔ������炭�A�W�T�C�́A�F�Ƃ�ǂ�Ō��h�����ǂ��O����������Ă����̂��Ǝv������A���{�×��̉ԂŌÂ��͖��t�W�̒��ɉr�܂�Ă��邻���ł��B�U���̐�X�ł��ꂢ�ɍ炢���A�W�T�C�͎q�ǂ������ɂ���ۂ������c��̂ł��傤�B�u���߁E�����ނ�E���������v�͂��̎����̕ۈ�ɂ͕K���o�ꂵ�܂��ˁB�ŋ߂͕i�킪���ǂ���ĈȑO��茩���ꂽ�A�W�T�C�Ƃ͂܂�ŕʕ��̂悤�ȁA�������u�n�c�̉ԉv�E�u�_���X�p�[�e�B�[�v�E�u�čՂ�v�E�u���؋��v�ȂǂƋC���������O�̉Ԃ��X���ɕ���ł��܂��B����A�G���g�����X�ɐ�Ԃ������Ă������Ƃ���A�u��\���ꂢ�I�Ȃ�Ă������ԁH�v�Ƃ����˂��q�����āA���ꂵ���Ȃ�܂����B���C�����ς��ɃG�l���M�[��̒����甭�U����q�ǂ������ɂ��A���ꂢ�ɍ炭�Ԃ��y����ł��炢�����ł��ˁB
�@�@�V���͂��悢��v�[���V�т��n��܂��B�X���܂ł̂Q�����Ԃ͂قږ����̂悤�Ƀv�[���ɓ���܂��̂ŁA���q����̌��N�Ǘ�����낵�����肢���܂��B��N�ʂ�A�G���g�����X�̋L����ɘA���[�Ƌ��ɓ������~�[��p�ӂ��܂��̂ŖY�ꂸ�ɋL�����Ă��������B���N�܂ł͖��L���҂ɂ͌ʂɓd�b�Ŋm�F���Ă��܂��������Ɏ�Ԏ���Ă��܂����B�v�[���ۈ�͎q�ǂ��̈��S�m�ۂ̂��߂ɓ��ɕۈ�m�̌���肪�d�v�ł��̂ʼn˓d�̂��߂Ɉ�l�������邱�Ƃ͕s���v�ɂȂ���܂��B�q�ǂ����p�Ӗ��[�Ńv�[���ɓ��肽���Ă����������Ă��Ă��A���̋L�����Ȃ��ꍇ�͈��S���A�ۈ�m�̔��f�Ő��V�т����ɂ��܂��̂ŁA���Y��ɂȂ�Ȃ��悤�ɂ��ꂮ�����낵�����肢�������܂��B
�@�@���N�A�v�[���V�т������Ղ�Ɗy���ޒ��ŁA�q�ǂ������͉j����Ƃ��j���Ȃ��Ƃ������ƈȏ�ɁA��N�܂ł̎��������z����A�F�����Ƌ��͂��Đ��V�т̊y�����i����A�����Ɍ������ă`�������W����Ȃǎq�ǂ��̔��B�ɂƂ��ĉ����ウ�������̌������Ă��܂��B�q�ǂ����u�������݂̎��͏o���Ȃ������̂ɏo����悤�ɂȂ�����v�ƌւ炵���Ɍ������̕\��͂ق�ڂꂷ��قNjP���Ă��܂��B
�@�@������Ɖ��ł��o���錫���q�ɂ������A���������̗ǂ��A�f���ȗD�����q�Ɉ�Ă����ƒN�����e�͊肤���̂ł����A�ʂ����ĔN������ł����A���܂�Ă��������U�N�ł��B���ɂ͕ۈ璆�ɍ�����ԂɂȂ�A�ۈ�m�ł�������グ�Ƃ�����ʂ�����A���̕ۈ�m�ƃo�g���^�b�`���ăN�[���_�E������̂�҂Ȃǂ��Ă��܂����A�q�ǂ��̂���̂܂܂̎p������Ȃ���A���̎����̎��Ɏq�ǂ����{���ɋ��߂Ă�����̂��������Âɍl���đΉ����邱�Ƃ��q�ǂ��̍ő�̔��B�ۏ�ɂȂ�ƍl���܂��B�l���ɉ��\�N�Ƃ����������d�˂��͂��̂��ƂȂ����������ƌ��n�����Ƃ��āA�S�Ẵ��[�������A��Ђ̃~�X�◎���x���Ȃ�������Ɖ��ł����Ȃ��āA���a�ł݂�ȂɗD�����A�����̂��Ƃ��l�̗��v��D�悵�A�H�ו��̍D���������Ȃ����ł����ӂ��ĐH�ׂ���l�E�E�E�E�E�E�Ȃ�āA���Ȃ��ł���ˁB
�@�@�q�ǂ������Ɖ߂������X�́A�ǂ��ɂ��������ɂ��h���}�e�B�b�N�ł��B������t�ɐ����Ă���q�ǂ������ɃG�[���𑗂�A���S���ĐS���₩�ɉ߂�����悤�ɁA���n�ȕۈ�҂̏W�܂�ł͂���܂����A�݂�ȂŒm�b���o�������ă`�[���v���[�̒�͂��������Ȃ���A�s�}�Ђ悱�ۈ牀�̕ۈ�����݂��ĂĂ��������Ǝv���Ă��܂��B
�@�@�~�J��������Ό���������������Ă��܂��B�P�Ɍ��N�A�Q�Ɍ��N�A���ɋx�{���Ȃ��珋���Ă��y���݂܂��傤�B
��6�����i2016�N6��2���j
�@�@
�@�@�s�m���̐����������p�^�f���^�T�����ɂ���Ď����オ���Ĉȗ��A�ߋ��ɋN���������Ƃ����̓��l�̎�����V�����Ƃ���ł͉��l�s���Ȃǂ��܂��܂Ɂu�����Ƌ��v�Ɋւ����肪��肴������ē��₩�ł��B
�@�@�@�u�n���̍�����������v�A�u����ɂ̌����K����v�Ƃ����̎��͂����肪��������̂���u���̐�ڂ����̐�ځv�A�u���Ɛo�͐ς���قlj����v�Ȃǔے�I�Ɏg������̂Ȃǂ����Ɋւ��Ă͑����̂��Ƃ킴������܂��B�@�@�@
�@�@�������ɂ������Ȃ���ΐ����o���Ȃ��̂ł�����A�����͑�ł����i�����Ȏq�ǂ������ł����A���܂܂��ƂȂǂł����ɑ��đ傫�ȊS�����p������قǂł��j�A�R�c�R�c�Ɛ������Ă����ʐl�ɂ��Ă݂�A�u���ł���ȂɃZ�R�C���܂ł��Ă������ق����́H�v�Ǝv���̂ł����A���Ⴂ�̂���������悤�ɂȂ�Ɛl�Ԃ͕ς��̂ł��傤���B�ł��A���⎩���̂̃g�b�v�ɗ��悤�Ȑl�͌����Ă���ȂЂƂł����Ăق����Ȃ��Ǝv���܂����A�u���K�g�ɂ����v�Ƃ��u���̐�ڂ����̐�ځv�Ƃ������܂���ˁB�Ƃɂ����u���������v�Ȑl�ł����Ăق����ł��B
�@�@����ŁA�ۈ珊�����ҋ@������肩��͂��܂�A�ۈ�m�̏������P�ɂ��đ傫����肴������Ă��܂����A�x���Ɏ����銴������܂��B��̈ȏ�O�A���݂�y�A�Ō�t�A��������œ����҂ɑ��ĂRK�ƌ����Ă��܂������A�������J�����̒��ł��܂��߂̓����Ă���l�����͑吨���܂��B�ۈ�m�ƂāA�l�l�̑厖�Ȃ��q�����吨�A�����������Ԃ��a���肷��̂ł�����ǂ�Ȃɂ����_�I�A���̓I�ɔ�J���邩�͑z������ɓ�Ȃ����Ƃł��B�@
�@�@�Q�V�N�x���A�ۈ�m�ɑ��ċ����ɏ������P�����Z�Ƃ������ڂ̉��Z�������܂����B�ł́u�T���~�̃A�b�v���I�v�Ƃ�����������悤�ł����A����ő��ł��摗��ɂȂ�A�����͂ǂ���z����̂ł��傤���H
�@�@�@��ɐl�Q���Ԃ牺�����Ď�������n�ł͂Ȃ��̂ł�����A���������ǂ��Ȃ�Εۈ�m�̂Ȃ�肪������ƍl����̂͒Z���I�ł��B�q�ǂ������킢���Ǝv���A���a�ň��S�ł��鎞�Ԃ��q�ǂ������Ɖ߂��������Ƃ�����簂ȗ��z������ĕۈ�̓���I�̂ł��B�����ۈ�m���ǂ̂悤�ɐS�����߂ē����A�q�ǂ���������낤�Ƃ��Ă���̂��A���������ł͐l�̐S�͖�������Ȃ��ƒm���Ăق����Ǝv���܂��B�ۈ�m�����͕ۈ�Ƃ����d���ɂ��ĎЉ�I�ɂ����Ɛ[���������ė~�����A�]�����ė~�����Ɗ���Ă���̂ł��B�@�@�@�@
��5�����i2016�N5��2���j
�@�@
�@�@�V�N�x�S���̏I���ɂЂ悱�܂���s���܂����B���̎����ɊJ�Â���˂炢�̈�ɁA���������Ă̐V��N���ɗV�тɗ��Ă��炤��������܂��B�������̂悤�ɉ߂������Ђ悱�ۈ牀����A�S���K�͂⎞�Ԃ̗���̈Ⴄ���w�Z�ɍs���āA�͂��߂͕����������璣����Ă����q��A�ْ����Čł��Ȃ��Ă����q�ȂLj�l�ЂƂ蔽���͂������܂����A�T���a�Ƃ������t������悤�ɂP�������炢�o�Ƃ��낻���ꂪ�o�n�߂���A�o�Z���a�����肷��q���o�n�߂܂��B����Ȏ����ɂ�����ƌÑ��ɗ�������Ă�����Č����ꂽ�ۈ玺�₨������A�搶�����ɉ���āA�����ς���Ă��Ȃ��A�����ۈ牀�͂����ɂ���ƁA���S���Ă��炢�����̂ł��B�U�N�Ԃ��A�������P���̑唼���߂������q�ǂ������ɂƂ��āA�ۈ牀���v���o�̒��Ő�߂銄���̑傫�����Ƃ��Ђƌ��Ԃ�ɉ�����q�ǂ������̕\��犴���܂����B�q�ǂ������͌������Ɂu�܂�����ˁ[�v�ƌ����ċA���čs���܂����B��������������Ă��ꂽ�搶������ꏊ���ς�炸�ɍ݂�Ƃ������S���͉����ɂ��ウ�������̂ł��B���Q�����̂��ƂȂ̐��E�͂Ƃ������������������ł����A���߂ĕۈ牀�͉��������Ă����̎q�ǂ��������������肳���Ȃ��悤�Ɋ撣��Ȃ���A�Ǝv�������Ƃł����B
�@�@�Ђ悱�܂蓖���̒��A�吨�̂���������������f�b�L�A���ԏ�̃^�[�t��������ĉ������܂����B���[�o�[�̏�⍂���r���ɂ̂��ė͂̂����Ƃ����Ă��������{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B���ꂩ�率�O���������Ȃ��Ă��܂��̂ŁA����V�т�v�[���V�т̋C�����肪��N���A�o���Ė{���Ƀz�b�Ƃ��Ă��܂��B���i�̗D�����\��̂���������Ƃ͂܂��Ⴄ���������ċ�����������̎p�ɐE���ꓯ�̓��̓n�[�g�}�[�N�ɂȂ��Ă��܂����B
��4�����i2016�N4��1���j
�@�@
�@�@�����A�i�����߂łƂ��������܂��B�q�ǂ������͍������y���݂ɑ҂��Ă��܂����B�P�N���X�オ�������Ƃ����ꂵ���ăn�C�e���V�����ł��B�o�^�o�^�ƍQ���������߂���������̂R�P���B�����炮�݂͂��悢��Ђ悱�ۈ牀�ʼn߂����Ō�̂P���ł����B�ۈ牀�̊O���≀�ɓ����u���肪�Ƃ��̋C���������߂āv���|�����Ă���܂����B�������Ƃ͂��|����@���|��������q�ǂ������͂��Ă��ł����A�ڂ̉��قǂ̖Z�����̒��ŕۈ�ŏI���܂Ŏw�����Ă���S�C�ۈ�m�ɂ͐g���Ȃ��瓪��������v�������܂����B���܂ǂ��͂��ƒ�Łu�l�Ɋ��ӂ��邱�ƁA�����đ̂ƐS�������Ă���킵�Ă������Ɓv���A������@����Ȃ��̂��Ȃ��Ɗ����鎞�����܂łɂ�������܂������A��́A�ۈ牀�ł͎q�ǂ������Ɏێq��K�ł�������A����łȂ��u�S����̂��肪�Ƃ��v��`���Ă���ł��傤���B�q�ǂ��������v�킸�u���肪�Ƃ��v�Ƃ������́A���ƂȂ��C���[�W����悤�ȑ傻�ꂽ���Ƃ���ʂȎ��ł͂Ȃ�j�A����̒��Ŏq�ǂ�������̗͂ŗV�т���Ŗ������ꂽ����A�D��S�ɓI�m�ȉ�ꂽ���ł��B�����炱���A�q�ǂ����{���I�Ɏ����Ă���f���Ȋ��ӂ̋C�����������o���ɂ͊��ݒ肪��Ȃ̂ł��B���ׂȎ��ɂ��ꂵ����L�����������q�ǂ��͍K���Ȏ��Ԃ��߂����Ă���̂��Ǝv���܂��B
�@�@����͕ی�҂̊F����ɂP�U�F�R�O���}���̂��肢�����܂������A�N�x���ł����������ɂ�������炸�A�قƂ�ǂ̕������͂��ĉ��������̂ō����Ȃ����₩�ɐV�N�x�����Ɏ��|���邱�Ƃ��o���܂����B���肪�Ƃ��������܂����B
�@�@�M���M���܂ŕۈ玺�̖͗l�ւ���A���O�V�[���̌��������Ȃ��̂́A�q�ǂ������ɍŌ�܂œ������ŗ��������ĉ߂����������Ƃ̊肢����ł����A�q�ǂ������͕ۈ�m�̑z���������ďI���y�����ɉ߂����܂����B�����č����ł��B
�@�@�ŋ߁A���N�O�ɑ��������q�ǂ��������悭�V�тɗ��܂��B�����Ă����炮�݂̎q�ǂ������ɐ�y�Ƃ��āu�ۈ牀�ł�������V��ł����Ȃ�B�����v���o�����Ȃ�v�ƃA�h�o�C�X�����Ă���p�͂قق��܂����ł��B
�@�@�l�Ƃ��Đ��܂�Ă܂��܂��c���o���̏��Ȃ��q�ǂ������ɂƂ��āA���ƒ�ƕۈ牀�ł̐������قƂ�ǂȂ̂ł�����A�ۈ�҂͂��ƂȂƂ��Ďq�ǂ��ւ̐ӔC�E�q�ǂ��������K���ł��葱���邱�Ƃւ̓w�͂��������莩�o���Ă��������Ǝv���܂��B�q�ǂ����������ǂ����Ԃ��߂������߂ɁA�O�����Ȃ��ӌ������҂����Ă��܂��B���N�x����낵�����肢���܂��B
��3�����i2016�N3��1���j
�@�@
�@�@����͂S�N�ɂP�x�̂Q���Q�X���ł����B�Q�X�����܂�̕��̒a�����͂S�N���Ƃɂ�������Ă��܂��A�s���葱���I�ɂ͂Q���Q�W�����u�݂Ȃ��a�����v�Ƃ��邻���ł��B�����Ƃ��@���I�ɂ͒N�����N��͑O���̌ߌ�P�Q���ɉ����ĂP�N�オ�邱�ƂɂȂ�܂��B�N��v�Z�ɂ��Ă͕��G�ł킩��ɂ����̂ŁA��o���ނ̑��������A���w���T�������̎����ɂ̓~�X�̂Ȃ��悤�ɂƓ���Y�܂��Ƃ���ł��B�Q���͂P�A�Q�����Ȃ������łƂĂ����Ԃ���������Ă�����������A�����s���Ɠ����s�����T���āu�Ƃ��Ƃ��R���ɂȂ��Ă��܂����v�Ɗ����Ă��܂��B
�@�@����̂킭�킭�X�e�[�W�͍��܂ł�肳��Ɏq�ǂ��̑��ɗ����čs�������������Ƃɏd�_��u���Ď��{���܂����B�����̔ώG����q�ǂ��������ӗ~�I�Ɏ��g��ł��銈�����q���Ă������ƍl���Ă̂��Ƃł������A�ۈ�҂̗��ꂩ�炷��Ƃ����ȏ�Ɏq�ǂ������͕��i�̎��������������ƕ\�����Ă����悤�Ɏv���܂��B�u�F�����ƈꏏ�ɉ̂��v���߂ɂ́A�c���Ȃ�̋C�z��₪���A�W������S���K�v�ł��B�F�������C�ɂ����Ȃ���݂�Ȃ̑O�ʼn̂��p�ɂ̓N���X���̐����ƈ�l�ЂƂ�̎q�ǂ��̂���̂܂܂̎p�������܂����B�F����͂ǂ�������ꂽ���Ƃł��傤���B
�@�@���N�A�N�x���ɂȂ�ƒʋΓr��̂����炱����œ��H�H�������Ă��āA��ʏa�������N�����Ă��܂��B���}���̕ی�҂ɂ��A�u���H������ł��Ēx�ꂽ�v�Ƃ���ĂĂ�����������炵�ĒǓˎ��̂ȂNjN�����Ȃ��łق����ȂƋC������ł��B�@�@�ۈ牀�ł��������Ă����q�ǂ������A�މ����Ă����q�ǂ������A�V���ɓ������Ă���q�ǂ������A�܂��A���̎q�����芪�����ƂȂ���������g��ő��X�����Ȃ肪���ȂR���ł����A�������V�N�x�Ɍq������X�ł���A�q�ǂ������ɂƂ��Ă͕ς��Ȃ������̕ۈ牀�ł̐����ł��B���ƂȂ����͐S���Ďq�ǂ��̓��퐫������Ȃ��ł������Ǝv���܂��B�q�ǂ����O�[���Ɖ��L�т₩�ɊJ�����čs����͕��a�ŗ�������������ɑ��Ȃ�Ȃ��Ə�X�����Ă��܂��B
�@�@���N�x���ۈ�^�c�ɂ����������������肪�Ƃ��������܂����B�c��1�J�����C���ɂ߂��ɂ������܂��B
��2�����i2016�N2��1���j
�@�@
�@�@��T���A��X�T���ƂQ�T�ɂ킽���đ��\��ɖ|�M���ꂽ�ς�����܂����B�L�^�I���g�ʼn����哇�ɂP�P�T�N�Ԃ�̍~�Ⴞ�����ł��B���R�u��v�Ƃ������̂��������ƁA�G�ꂽ���Ƃ̂Ȃ��l���吨���邱�Ƃł��傤�B�q�ǂ��������ǂ�Ȕ������������A�����[���ł��ˁB�Ђ悱�̎q�ǂ������͍~���S�҂��ɂ��Ă��܂������ۈ�҂����͎q�ǂ������ɐ\����Ȃ��Ǝv���Ȃ�����A������ƃz�b�Ƃ��Ă��܂��܂����B�Ⴊ�~������d�Ԃ��~�܂��Ă��܂����o����ρE�E�E�Q�N�O�o�X���S�ʉ^�x�Ŏs��������R���Ԃ����ďo�����L��������̂ŁA���̊E�G�ł̋␢�E�͂��育��Ȃ̂ł��B�i����ۈ�m�͂���܂ł̐l���łP�Ԑh���o�����ƌ����Ă��܂����I�j�q�ǂ������ɂ́u���R���y�������v�ƌ����Ă���̂ɔ߂������ȁA���Ƃ��ǂ��閈���A���}�����Ȃ������ł��B�Q���͔@���i�ߍX���E�����ďd�˒�����j�ƌĂԂ����ł�����{���Ɋ����ł��B
�@�@�P���ɂ͗c�������s�҂ŒD����ߎS�Ȏ�������������܂����B�ۈ牀�ɒʂ��Ă���q�ǂ��������̂ł����A���Ƃ���肫��Ȃ������ł��B�c���q�ǂ�����ؓ��ɂ́A���x�����䂪�͂�����Ƃ��ė��āA�ˑR�킪�܂܂ɂȂ�����A�e�̌������Ƃ��Ȉ����q�ɂȂ����肷��ƁA���ƂȂ̑�����͎v���鎞��������܂��B�Ԃ����ł��Ɩ鋃�����Ђǂ���ΐe�͂ւƂւƂɂȂ�܂��B��ʓI�ɂ͔��B�̐ߖڂł��炭�҂����ɂ���ȗ������܂邱�Ƃ��قƂ�ǂȂ̂ł����A�Q���ɂ��鎞�͖{���ɑ�ςł��ˁB�ۈ牀�ł͕ی�ғ��m�Ōo����`����������A������ׂ肵����ŋC���]���o����̂ł����A�Ǘ������ƒ���ł͈玙�s����q�ǂ��ɑ�������������ɑ����ɂȂ��Ă����Ƃ����A�������邻���ł��B�������N���邽�тɑg�D�ԂŐӔC�̉����t���������J��L�����Ă��܂����A���̂������ɂ��]���ƂȂ�q�ǂ����o�邩������Ȃ��Ƃ������Ƃ��A�q�ǂ��Ɋւ�邨�ƂȂ͊̂ɖ����Ă����Ȃ�������܂���B
��1�����i2016�N1��4���j
�@�@
�@�@�����܂��Ă��߂łƂ��������܂�
�@�@���₩�ȓV�C�Ɍb�܂�ĂQ�O�P�U�N�i�����Q�W�N�j���n��܂����B�N���N�n�ɂ͒����x�݂������������肪�Ƃ��������܂����B��N�͂Ђ悱�ۈ牀�̒��ƊO�A�܂����E���Ŋ�������Ƃ�ڂ����ނ������ߎS�Ȃ��Ƃ����X�ɋN���܂������A���N�͂ǂ��Ȃ��Ă����ł��傤���B���N�̊��x�́u���\�v�i�Ђ̂�����j�A�����ɓ��Ă͂߂�Ɓu���v�Ȃ̂ŁA�\�N���܂�̐l�͐肢�I�ɂ͖��邭�����œ��̉�]���������ʖO�����ۂ��Ƃ��������Ƃ��E�E�E�E�B�����邩�ǂ����͕s���ł����A�ǂȂ������N�����ɁA���N�ɉ߂��������ł��ˁB
�@�@���Ƀ��j�Z�t���V���A�ً}����̗v�������苦�͂��Ăт����܂����B�����ʂ�ً̋}���œ��ˊ����|�����s���̊����������Ƃ͎v���܂����A���l�̕ی�҂̕��ƐE������^���ĂQ�Q�C�X�U�X�~����t���鎖���ł��܂����B�������������𑱂��Ă������Ǝv���܂��̂ŁA���q����ɕ���̈Ӗ���`���Ă��������čX�Ȃ邲���͂����肢���܂��B
�@�@���̂Ƃ�����{�ł͎q�ǂ��̕n����s�҂����f�B�A�ɑ������グ���Ă��܂��B�ꌩ���a�ƖL�����ɐZ���Ă���悤�ȉ䂪���ł����A���Ԃ͐e�̎��Ƃ⎾�a�Ȃljƒ���@�\�s�S�ɂ��闎�Ƃ��������鏊�ɂ���Ƃ������Ƃł��ˁB
�@�@����A���[���b�p�ł̓���͗��j�┭���̌����͍��ɂ���đS���قȂ�ɂ���q�ǂ��������瓖����O�̐����⎞�ɂ͑����̖���D���Ă��鎖��������܂��B�����̐g�̉��ɂ���q�ǂ������ɁA��ɂӂ��킵�����𐮂����X�a�Ɉ��S���ĐS�g�Ƃ��ɖ�������Ĉ���Ăق����Ƃ͒N�������]�ނƂ���ł����A���ۂɎ����̖ڂɌ����Ȃ��͂邩�����̍��̎q�ǂ������̍K���ɂ��Ă͑z���͂⋤���͂̏������K�v�ł��ˁB�����n����ŁA�����̊����Y���ƂȂ�A���̂������ۏႳ��Ȃ��̒��Ŏq�ǂ������͖������ǂ̂悤�Ɍ}���悤�Ƃ��Ă���̂ł��傤�B�����Ƃ������t�����m��Ȃ��q�ǂ������������Ƃ������邱�Ƃł��傤�B
�@�@�Ђ悱�ۈ牀�̎q�ǂ������͉Ƒ���F�B�Ƃ��̉Ƒ��A�ۈ�m�����Ɏ���Ȃ���̂т̂тƋ����Ȃ�����Ă��܂����A����͌����ē�����O�ł͂Ȃ��̂��Ƃ������ƁA�����Đ��E�ɂ͔ߎS�ȋ����ɂ���q�ǂ��������吨����Ƃ������Ƃ�c���Ȃ�ɒm���Ăق����Ǝv���܂��B�܂��A���̂��Ƃ�`���Ă������Ƃ��ۈ�̐ӔC�ł���Ɗ����Ă��܂��B
��12�����i2015�N12��1���j
�@�@
�@�@�n���E�B���̓��₩�ȑ��������܂肩���A���̓N���X�}�X���킪���낻��n��Ƃ������~�̂킭�킭�����C���𐁂�������낵������������܂����B�p���œ��������e���������N���A�킸���Ȏ��Ԃ�130�����̖����D��ꐢ�E�����[���߂��݂Ƌ��|�ɂ��̂̂����A�����ɂ̓e���̎�d�҂Ƃ݂Ȃ����l���̐����悪���������Ƃ����A�����Ƃ͎v�������Ȃ���ގ��̎��������E�̂�����Ƃ���Ŕ������Ă��܂��B�u�ڂɂ͖ځA���ɂ͎��v�Ƃ����̘A���Ɓu���̗אl��������v�Ƃ����אl���̋��������ɂ�����������܂����A�ǂ�����@���Ƃ̊ւ��̐[���������ƔF�����Ă��܂����B�����������܂������{�͏@���푈���Ȃ��̂ŁA���E�̂�����Ƃ���Ŗu������@���̂��������{���I�ɗ������ɂ����̂ł��傤�B�e���͘_�O�ł����A���ƍ��̑Η��͍X�ɗl�X�Ȍ��������ݍ����ĕ��G���������Ȃ̂ł��ˁB
�@�@���݂������݂�����āA�F�ߍ������Ǝ�e���鎖�̏o���Ȃ��p�͎������̎���ɂ����܂�Ƃ���܂��B�q�ǂ������̌��܂͂͂��ߎ�⑫���o�ĂЂ��������肩�݂�����Ɠ��₩�ł����A���炭����ƃN�[���_�E�����Ă��݂������Ȃ������悤�ɒ����肵�܂��B����ɂ��ƂȂ�������Ȃ���������Ȃ�A���R�ȋC�����Łu���߂�ˁv��������ꍇ�������悤�ł��B��l���m�A���ƍ����q�ǂ������Ɋw�ׂ�ƕ��a�ɂȂ��̂ɂƎv���܂��B
�@�@�ۈ璆�ɋN�����������͖��x�u���̕��v�ɋL�ڂ��Ď������ɕ��鎖�ɂȂ��Ă��܂��B���e�͏��a�̏A���̔����̏A�ی�҂ւ̘A���A�o�߂ȂǂƋ��Ɂu���㓯���悤�Ȏ��̂������Ȃ����߂ɂ͂ǂ�������悢���v���l���A���̓��̕ۈ��U��Ԃ邫�������ɂ��Ă��܂��B�����[���i�H�j�̂͑�̌��܂̏ꍇ�́A���A����̎q�ǂ��̑g���킹�����܂��Ă��邱�Ƃł��B�ۈ�m�͉�������Ă͍���̂Ō��܂����y�A�[�ɂ͌����J�ɂ��Ă��Ă��A�Ȃ��������ɂ��݂����߂Â��Ă����̂������ł��B�ȑO�A���܂��ĕۈ�m�������ł������j�̎q�����������w�Z�ł����悵�ł������ł��āA�Ђ悱�̍s���̂Ƃ��ɂ݂͂�Ȃŗ�₩���i�H�j�ɗ��Ă����̂͂��ꂵ������ł��B
��11�����i2015�N11��1���j
�@�@
�@�@���̂Ƃ���A�ۈ牀�̏��Ƀw���R�v�^�[��������Ă��đ��X������������܂��B�U������A���Ă��������������u����Ƀw���R�v�^�[�������ς��������v�ƕ��Ă���܂����A�s�X�n�ɒė����鎖�͉̂ߋ��ɉ��x������̂ŁA�q�ǂ������̎U����ɒė�������|���ȂƎv���Ă��܂��܂��B�����A���V�����ʂ��ɂ��킹�Ă���}���V�����̍Y�H���U���ɂ��Ă̕w���Ȃ̂ł��傤���A���R�ЊQ��厖�̂Ȃǂ̔�펖�Ԃ̂悤�ŕs���ȗ������Ȃ��C���ɂȂ�܂��B
�@�@���Y�}���V�����̏Z���ɂƂ��ēˑR�~���Ă킢���Г�ɁA���q�����M���ɍ���̐����⑹�Q�⏞�Ȃljۑ肪�R�ς��Ă��܂��B����̎����Ƃ͒��ړI�ȊW�̂Ȃ��҂ɂƂ��Ă��Z���͐l���̒��ł��傫�ȃE�G�C�g���߂���ł�����A�����҂̕��X�̋�Y���@����ƏՌ��Ɠ{��̊���������������܂���B
�@�@�����ł́����S���̃f�[�^�s���A�O���ł͎Ԃ̔r�K�X�s���Ɩ����̂悤�Ɂu�s���v�̕����������̊ς�����܂��B
�@�@�u�V�ԉ����i�e�����E�J�C�J�C�j�a�ɂ��ĘR�炳���v�i�V�q�j�Ƃ����̎�������A�Ӗ��́u�V�̒���Ԃ͍L���Ĉꌩ�ڂ��e���悤�����A���l��Ԃ̖ڂ���R�炷���Ƃ͂Ȃ��B�������s���ΕK���߂����V���������ނ�v�Ƃ������Ƃ������ł��i�̎����Ƃ킴���T�j�B�O���ɂ������悤�Ȍ���������A�Y�����Ă��K���o�����Ɛ̂���݂�Ȃ��m���Ă���̂ɁA�������Ƃ肸�ɌJ��Ԃ��̂͐l�Ԃ̐��Ȃ̂ł��傤�B
�@�@���X�̎q�ǂ������Ƃ̕�炵�̒��ŁA���ėǂ����A���Ĉ������Ȃǂ��낢��Ȃ��Ƃ����N���܂��B�ǂ������̔��f��͂ЂƂ��܂��܂ł����A�݂�Ȃ��S�n�悭�K���ȋC�����ɂȂ�邱�Ƃ͂ǂ�ǂ�o�����Ă�����āA���ꂵ���C�����݂�Ȃŕ����������Ăق����Ǝv���܂��B�����C����ςݏd�˂邱�ƂŁA�l�ɖ��f�ɂȂ邱�Ƃ�l�̌����邱�ƂɋC�t����悤�Ɉ�Ǝv���܂��B
�@�@�H����̂ƂĂ��S�n�悢������A�����炮�݂̎q�ǂ������͗V�����̗����t�͂������Ă��܂����B�ق����ŗ����t���W�߂�q�A����Ƃ�ɓ����q�A���ݑ܂̌����L���ė����t�����₷���悤�ɋC�z�肷��q�A�ǂ̎q�̊���^���ňꐶ�������d�����Ă��܂�����B
��10�����i2015�N10��1���j
�@�@
�@�@�^����A���ق艓���Ɗy���������҂��Ă���P�O���ł����A���N�͓V��s���ŗ��K���܂܂Ȃ�ʊԂɑ̈�̓����^��������}���܂��B�ۈ�m�����ɂ͏��X���Ԃ�����Ȃ�����������̂́A�q�ǂ������͔N����ɒ�����ė��K�ɗՂ�ł��܂��B���Ƃ��ƁA�q�ǂ����������B���サ�āu�����邽�߂̉^����v�Ɏd�グ�邱�Ƃɂ˂炢�������Ă��Ȃ��̂Ŏq�ǂ������������I�ɗ��K�ɗ�ޗl�q���C�y�Ɍ�����Ă��܂��B����ł��c���N���X�ł͂��C���o���Đ^���ɋZ�ɗ����������p������A��N�Ȃ���^����q�ǂ��̔��B�̐ߖڂƂ��đ傫�ȍ�p�ƂȂ��Ă���Ǝv�킳��܂��B
�@�@�X���͂��������̑呛���̖��A���ۖ@�Ă��������܂����B�u������{�̕��a���ǂ̂悤�ɂȂ�̂��C������ł��v�Ȃǂƌ�����قǐ[���l���������Ė������炵�Ă���킯�ł͂Ȃ��A�c��̐���ɂ͉������������ł���u�m���|���v�Ȃ̂ł����A�ۈ牀�Ŏq�ǂ����������т�H�ׂ��A�D�V�т������A���݂��ꂽ�ȂǂƂ�������I�ȉc�݂��{���͐�����@���ȂǂƖ��ڂȂ�����肪����̂��Ɗ����邱�Ƃ�����܂��B
�@�@���N����q�ǂ��E�q��Ďx���V���x�����{����܂�������ϕ��G�ȃV�X�e���Ŗ������ۈ猻����������Ă��܂��B�傫�ȖړI�̂P�ł������ҋ@���������ɂ͌��т����A���N�x�͑������̑ҋ@���������܂��悤�ł��B�V���ɕۈ珊�����܂��A�ҋ@�����������邢�����������̒��ŁA�ۈ珊�{���̎����̕����Ƃ����傫�Ȏg�������X�ɏ����̘J���͊m�ې���Ƃ����т��ĕی�҂̗����D��ɂ��肩�����Ă���̂������ł��B
�@�@�P�O���ɓ���Ɨ��N�x�����̂��߂ɑ吨�̌��w�҂�����̂őΉ��ɒǂ���̂ł����A�Ђ悱�ۈ牀�̕ۈ�̓��F����������Ɠ`���čs�������Ǝv���܂��B�@
��9�����i2015�N9��1���j
�@�@
�@�@�V��s���̉Ă��I����ĂR���ɂȂ�܂����B�\��ł͍��T���V��͂������悤�ŁA�~�J���߂������ł��ˁB���̂Ƃ���v�[���ɓ���Ȃ������̂łV���̃v�[�����܂��̑O�ɂ͑�V�т��������Ȃ��Ɗ���Ă��܂��B�q�ǂ������͂Ƃ����ƉJ�ł��낤������ł��낤���ό����݁A���C��ł��B
�@�@�Q�K�f�b�L�̍�̍����������E�⋭���܂����B�S�_�A�u�����R�A�̂ڂ�j�A���[�v�l�b�g�Ȃǎq�ǂ��������f�b�L�ł��̂����Ă̂т̂тƗV��łق����Ǝv������ŁA������̔N��̎q�ǂ������̂Q�K����̓]���Ƃ������X�N��h�~���邽�߂ł��B�ނ��A�q�ǂ������ɑ��Ắu�댯�Ȃ��Ƃ͎���̔��f�Ŕ�����v�ƌ������o��{���Ăق����Ɗ肢�܂����A�ۈ�̒��œ`���čs���ׂ��d�v�ۑ�ł���Ƃ͎v���Ă��܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
���ɐV�z�����A�ӏ����Â炵�Đv�����̂Ŏ��鏊�ɔ��ς��d���������[�o�[��ݒu�����Ă��܂������A�����{��k�Ђ̌o�����瓪�㗎�����ƂȂ肦��\�z����ۈ�ɕs�v�ȕ��͓P�������S����Nj������Ƃ𑱂��čs�����ŁA�Q�K�f�b�L�̃��[�o�[�����O���܂������A�S���͖{�̂ƈ�̉����Ă��Ċ��Ȃ̂ŗL�����p���ėl�X�ȗV���ݒu���܂����B�@
�@�@�L�������Ɠ����Ƃ͍s���܂��A����ł��q�ǂ������͊��ŗV��ł���Ă��܂��B�j�̎q�����̍D���ȗV�тɐ킢������������܂����A�N��オ��ɂ�ėL��]��G�l���M�[�������̗V��Ń`�������W������Z������Ǝ��������z����o���ɍ��߂Ăق����Ƃ����肢�ł�����܂��B
�@�@�ŋߗc���q�ǂ��������]���ɂȂ鎖���⎖�̂������������Ă��܂��B�}�X�R�~�ł͂��낢��ɋ]���҂̉Ƒ��̂��ƂȂǎ�肴������Ă��܂����A�����֖��Ɗ�]����������������c����������ɐs�������Ƃ̂ł��Ȃ��قǂ̔ߎS���ł��ׂĂ�D��ꂽ���Ƃ͖{���ɒɂ܂����A�Ђ悱�ۈ牀�Ɍq����q�ǂ������͉��������Ă������⎖�̂̊������܂�邱�Ƃ��Ȃ��悤�ɂƉ��O�ۈ�݂̍���A���S������x�m�F���Ă��܂��B�܂��A�ۈ璆�Ɏq�ǂ������̘b�����ɂ���̂ł����A�q�ǂ������ŊO�ɏo��������A�����ԗ���Ԃ��Ă���Ȃǂ���悤�ł��B�̂قnj�ߏ��̐l�ԊW���e���ł͂Ȃ��Ȃ��Ă�������́A�댯�������ς��Ȃ̂ł͂Ȃ����Ɗ뜜���܂��B
�@�@�ɂ��Ǝq�ǂ��̎����͂قƂ�ǂ��[�邩�����ɔ������Ă���悤�ł��B�q�ǂ����������܂��ɂ͂��ꂼ��ƒ�ɂ��낢��Ȏ�������Ă̂��Ƃ��Ǝv���Ɠ����ɁA�ƒ�݂̍�����q�ǂ��ɂƂ��ĕ��a�I�łȂ��Ȃ��Ă���w�i�͌o�ϗD��̍��݂̍���Ɩ����ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B
�@�@�e������ƌ����Ďq�ǂ��̌��������S�ɂł��鎞�ԓI�̗͓I�]�T�͂Ȃ��A���Ƃ����ĕۈ牀���ڂ����ς��Ƃ����ɂł͈�̎q�ǂ��������ǂ���������邩�A�u�����̐g�͎����Ŏ��v�Ƌ��炷��̂������̂��A�l���ǂ���ł��B
�@�@
��8�����i2015�N8��3���j
�@�@
�@�@�Ă̈��C�x���g�u�Ȃ܂�v���I�����܂����B�䕗�̂��ߓV��̗\�����������A�e���g����Ȃǎ���߂Ă̎��{�ł������傫�ȕs�s���Ȃ��A�q�ǂ������̓Q�[���₭���т��ȂǑ�͂��Ⴌ�ł����B�ی�҂̕�����u�`���[�y�b�g�����������v�Ƃ̊��z�����������܂������A�J���[��o�[�x�L���[�̖��͂������ł������H�F�B�̉Ƒ��Ƃ����荬�����ă��C���C�ƐH�ׂ邱�Ƃ͎q�ǂ��ɂƂ��āA�傫�Ȋy���݂ł��ˁB���O�����A�����̔C�����S�Ȃǂ����͂��肪�Ƃ��������܂����B�ۈ牀�̎��ӂł͖��T���ǂ����ł��Ղ肪�s���Ă���̂ł��Ƒ��ʼnċC�����y����ł��������B
�@�@�ҏ��������ĘA���A�����w�X���b�O���������Ă���̂ŕۈ�͂����ς�v�[���V�сA�����V�тł����e�N���X�Ƃ��N��ɉ������o���G�e�B�[�ɕx�V�т�����Ă��Ďq�ǂ����m�ł���肵�H�v���Ȃ��犈���ɗV��ł��܂��B�����Ղ�V��͋��H���S�Â����̋��H��H�ׂĒ��悭�N�[���[�̂����������ł������薰���Ă��܂��B���Ƃ̐���z�c�ɐ����|����Ȃ��悤�ɁA�x�����_�ł̐��V�т����T���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ⓑ���ċx�݂����ė]�����w���̘b�����тɁA�̂т̂тƕۈ牀�ʼn߂����q�ǂ������͌b�܂�Ă���Ǝv���܂��B�M���ǂ���N�̔{�Ƃ����f�[�^������悤�ł����A���ƂȂł��������̏����͎q�ǂ��ɂƂ��Ă͍X�Ɍ������̂ŁA���C�����ς��ɗV��ł͂��܂����A�����Ƀ����n�������ċx�{���邱�Ƃ̑�����S���Ă��������Ǝv���܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@
��7�����i2015�N7��1���j
�@�@
�@�@������グ�ĉ_�̗l�q���C�ɂ����邱�Ƃ̑��������U���ł������A�����炮�݂̂����܂�ۈ�E�������ɏI���邱�Ƃ��o���܂����B�Z���Ԃ̂����ɂR������ٓ�������Ă����������肪�Ƃ��������܂����B���t�A�A�w���T���������炮�݂͎��ӂ̒n��⎩�R��m��Ƃ����ړI�ł������͂���܂����Œ����Ԃ̉��O�ۈ�̋@������̂ŁA��������X�̂��ٓ��Â����낵�����˂������܂��B�����A�U���ɏo�����Ă���̂ŁA�q�ǂ������͌��r�łP���Ԓ��x�̋������������Ėڂ����ς��V��ł��A����͂����Ƀ��Z�b�g���Ă��܂��B�ŋ߁A���̕ۈ牀�Ƃ̌𗬂̋@���������܂����A�D��S�����ȂЂ悱�̎q�ǂ������̗͑͂ƗV�ԋC�i�H�j�����ɂ����Ղ�Ȃ悤�ł��B
�@�@�ҋ@����ŕۈ牀��肪�}�s�b�`�Ői�߂��Ă��܂��B���낪�Ȃ��A�r���̒��ȂǕۈ牀�ɂ͕s�����ȂƂ������������܂����A�D�V�т͂��������Ȃ��A���O���ɂ͓����点�����Ȃ��A�����ł̂�������⑁������ɖ��͂�������ȂǁA���ƂȂ̉��l�ς����R�ő��l�Ȓ��ł��������`�Ԃ̕ۈ牀���p���Đl�C�̂���ۈ牀�ɂȂ�̂�������܂���B
�@�@���S�ۏ�֘A�@�ɂ��Đ��{�^�E��}�A�w�ҁE�����Ҏn�ߑ����̈�ʎs�����_������킷���ԂƂȂ��Ă��܂��B���{�̐�ォ�猻�݂ɂ����ĂV�O�N�ɂ킽�鎞�Ԃ̌o�߂̒��Ő�l�ɂ���Ēz����A��������Ă������a��`��v�z�A�����̎��R�Ȑ����ƈӎ��́A���̐�ǂ��Ȃ��Ă����̂ł��傤�B
�@�@�q�ǂ�����𑗌}���鎞�̕ی�҂̊F����̗l�q����A�c���q�ǂ�����ĂȂ��瓭�������邱�Ƃ��ǂ�Ȃɑ�ςȂ��Ƃ��ƁA���@�����Ă��܂��B�����������������̂�������܂��A��ςȂ��Ƃ͂��܂�o���Ă��܂���B��ɉ�c��������ɂ͗[�H���J���[�ɂ��Ȃ��������Ƃ������Ɋo���Ă��܂��B�J���[�����ȃC���[�W�̐H�ו��ɂȂ��Ă��܂��Ă͍��邩��A�Ƃ����̂��A�P���ȓ��]�̎�����̗��R�ł����B�V�v�w���тƂȂ������ł͕��C�Ń��g���g�J���[�ł����I�@
�@�@�X�g���X�̑����E��A��̂�����q�ǂ������A�ƍQ�������������Ƀz�b�Ƃ���Ԃ��Ȃ��̂������Ǝv���܂����A�ЂƂ��ѐ푈�̎���ɂȂ��Ă��܂��Ȃ�A����Ȃ��Ƃ��S�đ�ȕ̎��ԂƂ��Ă̎v���o�ɂȂ�̂��낤�ȂƎv���܂��B����قǂɐ푈�͕|���A�ߎS�ȑ̌��Ȃ̂��낤�A�q�ǂ���������ɑ��肽���Ȃ��Ƌ����v���܂��B
��6�����i2015�N6��1���j
�@�@
�@�@�T���X���i�y�j�ɍ��]�ˏ��h�o���������E���h�c���̎w���̂��ƁA�e�q�h�ЌP���Ɖ����������P�������{���܂����B���n�E�X�E�����Ί����h�Ԏ���E���h�������Ȃǎq�ǂ���������ԓ��e�������Ȃ���A��P���Ԃ����ĂQ�Q�ƒ�̎Q���ґS�����̌����܂����B�q�ǂ��̈��������s������A�����`���[���ł`�d�c���K�⌸�Ђɂ��Ă̂��b���f���܂����B��n�k�̔�Q�z�肪�������������ꂽ�܁A���h�������M�����Ęb���ĉ�����A�I���\�莞�����啝�ɐL�тĂ��܂��܂����B���N�A�����悤�Ɏ��{���Ă���̂Ń}���l�����͔ۂ߂܂��A����ł��A���P�[�g�Ɂu����̎��{���K�v�v�Ƃ��ĉ���������قƂ�ǂł��̂ŁA���e���������Ȃ��獡����p�����Ă����܂��B�A���P�[�g���܂���o����Ă��Ȃ����͂��ЁA�����Ȃ��ӌ����܂��悤���肢���܂��B�ۈ牀�͗l�X�Ȃ��ƒ낪�W�����ł��̂ŁA�����邲�ӌ����l�X�ň�ɂ܂Ƃ܂�Ȃ��ł����o����Ƃ��납�甽�f���Ă����܂��B
�@�@�����������i�Ǖ����������܂����B�ŋ߁A��ԎR������A�����R�ȂljΎR�����������ɂȂ�n�k�̕s�����������Ă��܂����A�n�k�������{�̒��ł��Ƃ�킯�u�n�k�̑��v�ƌ������s���Ŏ�s�����n�k�����̍ۂ̉��l�s�̔�Q�͉��ĉЂȂǂŒf�g�c���ƌ����Ă��܂��B�ۈ牀�̎q�ǂ������͍ЊQ���ɂ͎�����l�ł͂ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��ЊQ��҂ł����A����A�ۈ牀�J�����ԓ��ɑ�k�Ђ����������ꍇ�ɂ́A�E���͑S�͂�s�����Ďq�ǂ����������܂����A���Ƒ��̐g���ɍŌ�̈�l�������n���܂ł͎q�ǂ����������S�Ɉ��S���ĉ߂������ƂɑS�ӔC���܂��B���̂��߂ɂ��ی�҂݂̂Ȃ���̂��m�b���肽���Ǝv�����ł��B
��5�����i2015�N5��1���j
�@�@
�@�@�����̏��a�̓��A��P�R��Ђ悱�܂���s���܂����B�������萰��ĐS�n�悢���A�݉����₲�Ƒ����吨�W�܂�܂����B�Q�U�N�x�̑��������݂ȗ��Ă���āA�q�ǂ��������肩���ꂳ������ĉ�����Řb�ɉԂ��炢�Ă���l�q�ɖZ��������Ǎs�������邱�Ƃ̈Ӌ`�����߂Ċ����܂����B���肨������R�[�i�[��A�C�����r�[�Y�A���[���[�ނ�Ȃǂ������ł������A����͓��������قǂقǂ��������Ƃ������Ă��A����ő������ėV�ԏ��w���̎p�ɁA���i�͂�����Ƒ�l�т��l�q�������Ȃ�����܂��܂����C�ȂƂ��낪��������ȂƂق̂ڂ̂����C���ɂȂ�ƂƂ��ɁA�������ĉ��N�������Ă���̂Ɋo���Ă��Ă���đ����^��ł����q���������邩��ɂ́u���܂ł��ۈ牀���q�ǂ������̐S�̂ӂ邳�Ƃł��葱���Ȃ�����v�Ǝv���܂����B
�@�@�܂��A�������^�[�t��������ĉ�����������������A�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B��N�x���őމ������q�ǂ��̂�������������ԏ��ŋ삯���ĉ�����労���ł����B���̕��X�̂������ł��ׂẲ������������O���������邱�ƂɂȂ�Ƃ������Ƃ��F����ɒm���Ă��Ă������������Ǝv���܂��B
�@�@���N�x����V���x�ɂȂ�A���q���͒��X�Ɛi��ł���悤�ł�������ǂ̂悤�ɉ^�c���Ă������Y�ނƂ���ł͂���܂����A����ȋC������|���Ă����̂͂����q�ǂ������̏Ί�ł��B�q��Ďx���Ƃ������t���p�ɂɎg��������A����ς�q�ǂ������̍K�����P�ɍl���ĕۈ牀�𑱂��Ȃ�����I�Ǝv����łȉ����ł��B
��4�����i2015�N4��1���j
�@�@
�@�@�����E�i�����߂łƂ��������܂�
�@�@�t���̓��ɑ�12�����j����s���A22�l�̎q�ǂ��������������܂����B�����Ƃ͈Ⴄ�����ŋْ������ʎ����̎q�ǂ������͂ЂƂ܂��傫���݂��āA�����h�Z����w�����p���ڂɕ����Ԃ悤�ł����B�c��1�T�ԂƂȂ������X�A4���ɂ͏��w���ɂȂ�q�ǂ��������A�ۈ牀�ł̎c���ꂽ���Ԃ��ɉ߂����Ă���l�q���قق��܂������Ă��܂����B
�@�@���A�ۈ牀���̗V�����͂��Ԃ��̔����Ԃ����J�ł��B�H�ɂ͐Ԃ������q�ǂ������̂��܂܂��Ƃɂ����Ղ�o�ꂵ�܂��B�C�𗚂��ĕ����n�߂邱�납�疈���A���O�ɏo�����Ă͑�R�̂��݂₰�������A���Ă���q�ǂ������ł����A�c���ɂȂ��ď������������A�|�тŒT���V�тł����a�s���̐X�A��ʂ̐�쌴�ł���V�т��y���ތ��o�������A���ォ��̌����炵�����Ă��Ȑ�a�x�m�����ȂǁA�ߗ��ɂ͎������Ȃ��Ђ悱�ۈ牀�ł��B�����ł̗V�т��\���Ɋy����ł��܂����A���̌b�܂ꂽ���������Ǝg�������ĐS�Ƒ̂��J�����ėV�ѕ����Ȃ�������������Ȃ��I
�@�q�ǂ��E�q��Ďx���V���x���n��܂����B���낢��Ȏ葱���̗����^�c��E�⏕�����ς��܂��̂ŕی�҂̕��ɂ������Ƃ���͏������m�点���Ă����܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�V���x�ɂ��Ă̌����ƕ��s���č��Ĉȗ��A���l�����ɑ����̎��Ԃ������Ă��܂����B�ȑO�Ђ悱�ۈ牀�œ����Ă����E���ɍďA�E��Őf������A����̋��l�ē��͂������L���̒n���A�C���^�[�l�b�g���l�T�C�g�A�V���܂荞�ݍL���A�����̍L��f���Ȃǂ��낢�뎎���܂������A�������l�łǂ��ɂ��E�����W�܂��ĐV���ȋC���ŐV�N�x�̕ۈ炪�n�߂��邱�ƂɂȂ�A�Ђƈ��S���Ă���Ƃ���ł��B
�@�@�ی�҂Ƃ��Ă͊猩�m��̕ۈ�m�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��₵�����A�V���E���ɑ���s���ȂǑ��X����Ƃ͎v���܂����A�q�ǂ������̕ۈ�ɂ��Ă͎��̒ቺ���Ȃ��悤�ɁA�ۈ�҂݂�Ȃő��͂������Ċ撣��܂��B�u�ۈ�̓`�[���v���[�I�v�Ƃ����S���Ă��܂������A�ۈ�m����ʂɌ�サ�����N�x�����A���ɂ��̂��Ƃ��X���[�K���Ɍf���čs���܂��B�����ĉ��������̂Ђ悱�ۈ牀�`�[���ɑ吨�̕ی�҂݂̂Ȃ��Q�悵�Ă�������A�|�����̖����ł��B
��3�����i2015�N3��2���j
�@�@
�@�@���N�x�Ō�̌��ɂȂ�܂����B��N�����ɂȂ�Ɗ����邱�Ƃł����A�����炮�݂̎q�ǂ������͂����Ɏ����āA�����̐߂����щz������܂��B�q�ǂ��Ȃ���ɒ��N�ʂ����ۈ牀�A�������C�Ȃ�������킹�Ă����F������ۈ�m�����Ƃ̕ʂꂪ�߂Â��Ă��邱�Ƃ��A��l�ȏ�ɃV���A�X�Ɏ~�߂Ă���̂ł��傤�B�ɂ��ɂ��Ί�łӂ����Ȃ���ł����A�ˑR�u������ɂȂ��Ă��肪�Ƃ��������܂��v�Ƃ�����̏��̎q�Ɍ����āA�т����肵�܂����B���̊Ԃɂ��A����Ȍ��t��������悤�ɂȂ��Ă����̂ł��ˁB
�@�@���s�ŋN�������w�P�N�̏��N�E�l�����̕ɁA���̐����A�݂̂����肪�d�ꂵ���f���C������悤�ȋC�������Ă��܂��B��N�܂ŏ��w���������c���q�ǂ��̎��͂��Ƃ��s���̕a�Ƃ��Ă��h�����Ȃ̂ɁA�܂��Ă�\�s�̗g��ɖ���D����Ƃ͕M��ɐs�����������ߎS�ł��B�Ȃ�����Ȗڂɍ���Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂��A�����ĉ��Q�҂͂ǂ̂悤�Ȑ��������Ȃ̂��B�ƍߐS���w�҂�_�Ȉオ���ꂩ�玖���̊j�S��T���Ă����̂ł��傤���A��Q�҂ƔN��̂����ĕς��Ȃ��q�ǂ������Ɠ��X�ڂ��Ă���ۈ�҂ɂƂ��Ă͑��l���ł͂���܂���B�F�����Ɗւ���āA���������ɂ͂��Ⴎ�p�⎩�Ȏ咣�̂Ԃ��荇�����炯����Ɏ���o���Ă���p�ȂǁA�q�ǂ����m�̑f�̂܂܂�ڂɂ��Ă���ۈ�҂ɂƂ��ẮA�q�ǂ�����ɂ͂��̂悤�ȂȂ܂Ȃ܂����ւ��������Ղ�ƌo�����ė~�����B�����苃�����肵�Ȃ���l�ԂƂ������݂Ɣ��Ŋ�������Ăق����Ɗ肢�܂��B�C���^�[�l�b�g��Q�[���̗L�Q��������ċv�����ł����A���z��Ԃɂӂ�ӂ�ƕY�������ɑ��݂��Ȃ��l�ԂłȂ��A���������Ό����o�āA�ɂ��ċ������A����Ȃ��Ή������̂��l�Ԃł��鎖��m���Ăق����Ɗ肢�܂��B�q�ǂ������̈�l�Ƃ��Ă��̂悤�Ȕƍ߂̔�Q�ҁE���Q�҂ɂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ɛ؎��ɂȂ�܂��B�@�@
�@�@�����̉��C�Ȃ������ŁA�S�Ă̎q�ǂ��������Ɏ��M�������Ĉ��S���Ă̂т̂тƉ߂����邱�ƁA�����ɗF�����������Ɠ����悤�ɑ�Ȃ̂��ƋC�Â��A�ւ���[�߂čs�����Ƃ�������ۈ�̍ł��厖�ȖڕW�Ƃ��Čf�������v���܂��B
�@�@���ɂ����ĐV���x�ɂ��ۈ炪�n�܂镽��27�N�x�́A�Ђ悱�ۈ牀�ɂƂ��Ă��V���ȏo���ɂȂ�N�x�ł��B�ʂ����Ďq�ǂ������̍őP�̗��v��S�E�����������悤�ƐS���Ă��邩�B���������q�ǂ��̍őP�̗��v�Ƃ͉��Ȃ̂��B���܂ł�12�N�Ԃ̕ۈ���H�͂ǂ��������̂��B������Ǝ��ȕ]�������Ă����Ȃ���Ǝv���Ă��܂��B�ی�҂͂ǂ������Ă����邩�A����z�z�����d�v������������ǂ݁A���ӌ�����K���ł��B1�N�ԁA�����������͂��肪�Ƃ��������܂����B�@
��2�����i2015�N2��2���j
�@�@
�@�@����ς�~��܂����ˁA�Ⴊ�B��N�Q���̑��قǂł͂Ȃ��ɂ����ɕs����Ȏ҂ɂƂ��Ăْ͋�����~�̎��ۂ̂P�ł��B�炿�炿�畑���~��������߂������グ�Ȃ���u�Ⴉ���E�����E�]�|�v�Ɣے�I�Ȍ��t���肪�]���ɕ�����ł��܂��܂��B
�@�@�q�ǂ������͂Ƃ����ƒ������͂��Ⴌ�ŁA�����炳��͑����A����������Č��o�������ɏo�����čs���܂����B���������ǂ��̍��ɂ͐Ⴊ�~��Ƃ킭�킭�������̂������̂ɁA��������Ɋ�����悤�ɂȂ��Ă��܂����̂��ȁA�Ǝv���܂����A���ƂȂ��݂�ȁA�����Ȃ̂ł͂Ȃ��A�������ƃX�L�[��X�m�{�[���v�������ׂ�l�A���N�N�E���U�N����������������̂ł��傤�ˁB�@
�@�@�����͐ߕ��Ƃ݂�Ȃ̂킭�킭�X�e�[�W������܂��B�ߕ��ł͎q�ǂ������͋S�Ɍ������ē��i�q�ǂ������̐��앨�j�𓊂����A�ގ�����Ƃ�����d�������邱�ƂɂȂ�܂��B���ɂ����낵���`���̋S��ł����������q�ǂ������́i�|���̂��܂�ł܂��Ă��܂�����A�������Ⴍ���Ă���q������ق�ł����j���������ɂ���Ɏ��M�����āA���H�̏ăC���V����ۂ����肷��قǂł��B�ق�킩�������Ƃ���łȂ��A���ɂ͂قǂقǂ̕|���̌����y�����̂������ȂƎv���A���N�s���Ă��܂��B
�@�@�킭�킭�X�e�[�W�ł݂͂�Ȃŗ͂����킹�ďo���������������邱�ƁA�l�Ɍ��Ă��炤���Ƃ��o�������܂��B�ۈ牀�ʼn߂����������ɁA�q�ǂ������������̗͂ŗF�B�Ɗւ�肠���Ȃ���m�����Ă��邻�̎q�炵���⎩�䂪�A���C�Ȃ��\���A�d���A�F�����Ƃ̂����ɕ\��Ă���ƕۈ�m�͋C�Â��܂��B
�@�@���낢��s���ۈ牀�ł̍s���ł͎q�ǂ��������y�߂邱�ƁA�ꐶ�����ɂȂ�邱�Ƃ��ŗD��ɂ��Ă��܂����A�ی�҂̕��ɂ́A��Ƃ��ăe���r���j�^�[��ʐ^�ŗl�q���������������悤�ɂ��Ă��܂��B���Ƒ��c�R�̎��₨���C�ɓ����Ă��鎞�Ȃǎq�ǂ�����ɕۈ牀�ł̏o�����ȂǕ����Ă݂Ă��������B�q�ǂ�����̐����Ԃ�ɋ�������邱�Ƃ����ڂł���B
��1�����i2015�N1��5���j
�@�@
�@�����܂��Ă��߂łƂ��������܂�
�@�@�@�����N���N�n�̋x�������I���A�V�����N�̕ۈ炪�n��܂����B�F����̂��ƒ�ł͂ǂ̂悤�ɉ߂�����܂������B�A�J�̂��ƒ�����X���������ƂƎv���܂����ۈ牀�ł͒����x�݂������������肪�Ƃ��������܂����B���͔N���Ɉꔑ�ő����ɍs���A�A��ɍ]�̓��Ɋ���Ă��܂����B�Ă̒�A�x�݂ɓ������Ƃ���A���������̒��s�ǂɂȂ�[��~�}�f�Â���f����ȂǕs���ޗ��͂���܂������A�ǂ��ɂ��s�����Z�[�u���Ė��⑧�q�̉Ƒ��S���A�����P�O���ōs�����Ƃ��o���܂����B
�@�@�@���͔��N�O����u�݂�Ȃʼn���ɍs���I�v���Ƃ��y���݂ɂ��Ă����̂ōs���Ă悩�����ł��B�Ƒ������낤���ƁA�݂�Ȃł�����������H�ׂ邱�ƁA�킢�킢�����Ȃ��炨�������ނ��ƁA�e���r�ł����ԑg�����ăQ���Q�������ƁA����Ȃ��Ƃ̂P�P����͂�N���N�n�̓��ʂ̓��ȂȂ��A�S�������b�N�X���Ă���Ȃ��Ƃ��Â��v���܂����B�ۈ�m�������A�Ȃ��āA���t���b�V�����܂����B�܂����C�ɗ�݂܂��B
�@�@�@���āA�Q�O�P�T�N�͊��x�Ō����Ɩ��N�i�r�N�j�ł����A�r�͌Q����Ȃ��čs�����邽�߁A�Ƒ��̈��ׂ╽�a�������炷���N���ƌ����邻���ł��B�m���ɗr�͉��₩�ȕ��e�œ������ł͎q�ǂ������ɐl�C�̂��铮���ł��ˁB���N�͂S�����炢�悢��q�ǂ��q��ĐV���x�̓������n�܂�܂�܂����A���{�̕ۈ琧�x���n�܂��Ĉȗ��̑傫�ȕϊ��ł��̂ŁA�^�c�̗v�ƂȂ�^�c��̐������@��l���̕ύX�ȂǑ卬�����\�z����܂��B
�@
�@�@�@���������ł����Ђ悱�ۈ牀�ł��A�ȑO���m�点�����Ƃ���A�R�����łP�O�l�̐E�����ސE�A�ȂǍ��܂łɌo���������Ƃ̂Ȃ������Ɍ��������܂��B�����_�ł͎q�ǂ������̕ۈ炪���Ȃ��邱�Ƃ̂Ȃ��悤�ɐE���̗p��ۈ玺���A������𐮂��邱�ƂɑS�͂𓊓����Ă��܂��B�ۈ�͐l�����ł����A�������l�̗͈ȏ�ɐE���W�c�̒�͂����̂������Ǝv���܂��̂ŁA��͂�E�����m���ۈ�ɂ��Č�荇���A���ߍ������Ƃ���Ǝv���Ă��܂��B�@
�@
�@�@�@���������Γs�}�Ђ悱�ۈ牀�����ꌴ�ŊJ�����������r�N�������̂Ŋ��x���ꏄ�����̂ł��ˁB�S�@��]�A�����܂��I�@�@
��12�����i2014�N12��1���j
�@�@
�@�@�@��T����蒷�J�������Ă��܂����A������Ƃ�������ԂɂЂ���č���A����̏��a�L�O�����ɍg�t�����ɍs���܂����B�����ɂ�����ɐǂ���Ɖ_�ɉ������ꂽ�悤�ɏ����Ă��܂��܂������A�L��ȕ~�n�ɋ�ǂ̗t�̉��F�ƍg�t�̐ԁA��Ύ��̗��o�����X�悭�f���Ă��ꂢ�ł����B����萶�܂�ĊԂ��Ȃ��悤�ȓ������ꂽ�Ƒ��A��������K��Ă��āA���Z�����₨�o�����Ǝv����q�ǂ���������ǂ̗t�̉J���~�点����A�L���ł̏�𑖂�܂������A�Ƃق̂ڂ̂Ƃ������i�ł����B���T�͂��悢��~���R�����Ƃ��E�E�E�B�{�i�I�Ɋ����Ȃ�O�ɁA�Ԃ�����܂ꂽ���Ƃʼn����Ɖ䖝���������邱�Ƃ̑�����̎q�����ɂ��y�����ЂƂƂ����A�Ǝv���Ă̂��Ƃ��e�̕��X�̕\��ɂ��₩�ŁA�Ȃ�����ȉƑ��A������ăz�b�Ƃ��܂����B�ł��A�����ƕ����͂���Ȃ�������������d���ɒǂ��Ďq�ǂ������Ɂu�����I�����I�v�ƘA�����Ă���낤�ȁB�q�ǂ������͕ۈ牀�ł̒����ԕۈ�ŕ����A�������ł͂������߂����Ԃ��Ȃ������Ȃ낤�ȂƁA�q��Ă��Ȃ��瓭�����Ƃ��@���ɑ�ςȂ��Ƃ��Ǝv����y���Ă��܂��܂����B
�@�@�@�O�c�@���U�A���I���A����ő��Ő摗��ƁA�܂��N���ɗ��čQ���������Ȃ��Ă��܂����B���N�x�S���A����ő��ł����z���Ă��悢��q�ǂ��q��ĐV���x���X�^�[�g����Ɠ`�����Ă��܂������A���̐�ǂ̂悤�ɂȂ�̂��A�Ŏ����s�����钆�A��Â�����ǂ��Ȃ��Ă����낤�ƕs���ɂȂ�܂��B
�@�@�@�s�}�Ђ悱�ۈ牀�̉^�c�ɂ����āA�����Ƃ��Ă͂����邱�Ƃ̔��f���悸�u�q�ǂ��ɂƂ��Ăǂ��Ȃ̂��v�Ƃ������_�𒆐S�ɐ����ė��܂����B�ڂ̑O�̎q�ǂ������S���ĉ߂�����ۈ牀�Ɍ������Ă��������Ǝv���Ȃ���R�O�N���ۈ�𑱂��ė��܂������A�ʂ����čŋ߂̎q�ǂ�����芪�������̌������ɁA�u�q�ǂ��D��v�Ƃ����ۈ�̐��������Ƃ�����Ƌ�������Ă��܂��̂ł͂Ȃ����Ɗ뜜���Ă��܂��B
�@�@�@�l�͏\�l�\�F�A�݂ȑ�Ɏv���A��肽���Ǝv�����͈̂Ⴂ�܂����A�����x���ł������⍑�����̈Ⴂ�Ɉ˂�̂ł��傤���A�q�ǂ����n�߂Ƃ��Ďア�l�X�Ɍ��������̊z�����ɂ���Ă����Ԃ�Ⴄ�悤�ł��B���{�͖{���Ɏq�ǂ��������ȍ��̕�ƍl���Ă���̂��ƁA�ŋ߂̕ۈ珊���߂��鍬�������ɒ��ʂ��Ċ����Ă��܂��B
��11�����i2014�N11��1���j
�@�@
�@�@�@�^����E���ق�ƏH�̍s�����o�������q�ǂ������́A�܂��]�C���y����ŗV��ł��܂��B�^����ł͗��K�̎��ɂ͂Ȃ��Ȃ������Ȃ��^���ȕ\��ŁA�u�������Ђ悱�̎q�����͖{�Ԃɋ����I�v�Ɖ��߂Ďv���܂����B���K�̒��ł݂͂�Ȃƈꏏ�ɂ��Ȃ��Ă͂����Ȃ��A�o���Ȃ��Ă͂����Ȃ��A�Ƃ������Ƃ���Ȃ菬�Ȃ�X�g���X�ɂȂ��Ă���̂ł��傤�B�c���Ȃ���ɗւ̒�����͂ݏo���Ă݂���A�ۈ�m�̎w���ɏ]�����Ƃ��Ȃ������肷�邱�ƂŁA�����̗������Ȃ��S����\�����悤�Ƃ��Ă���̂�������܂���B�ۈ�̐U��Ԃ�̒��Łu�����̌��v�Ƃ������t�������Ό����܂����A�q�ǂ��ƂāA���͂���J�߂��F�߂��闧�h�Ȏp�ɂȂ肽���Ƃ����肢�ƁA�f�̂܂܁A����̂܂܂ɐU���������Ƃ����C�����̂͂��܂ŗh��Ȃ���߂����Ă���悤�Ɋ����܂��B���ł����킯�Ȃ��q�ǂ��̕\�ʓI�Ȏp����ɂ��ƂȂ��C���Ƃ���̂ł͂Ȃ��A�������Ȃ��獡�������ɐ����Ă���p�Ƃ��Ă��ƂȂ��������Ȃ�����Y���ւ��Ƃ��ɁA�������ǖʂ��ꂽ�肷��̂��Ǝ��⎩�����Ȃ���q�ǂ������Ɛڂ��Ă��܂��B
�@�@�@���l�s�͑ҋ@���������Ɍ����ĕۈ珊����������V�݂��Ă��邱�Ƃ���A�ۈ�m�s�����[���ƂȂ��Ă��܂��B�Ђ悱�ۈ牀�ł��挎���m�点�����悤�ɁA27�N�x�Ɍ����ĕۈ�m�̋��l���s���Ă��܂����A���낢��Ȕ}�̂𗘗p���ĕ�W���Ă��菙�X�Ɍ��w�҂����Ă��܂��B�ߗׂ�2�������V�����J�����܂����A�ۈ珊�ɂ��ۈ���@�͗l�X�ł��̂ŁA�V���E������킸�A�\���Ɏ��O���w���Ď����̂������ۈ炩�ǂ����������ė~�����Ɗ肢�܂��B
�@�@�@�ۈ�Ƃ����d���͉��s�����[���A�w�Ԃ��Ƃ���������ŁA���U�̎d���Ƃ��Ă̈Ӌ`������Ƃ������ƁA�Ђ悱�ۈ牀�̎q�ǂ������͌��C�����ς��ŁA�ꏏ�ɉ߂������Ԃ͊y�����A�ۈ�m�ɂƂ��Ă͊w�т̕�ɂł���A���C�̌��ƂȂ��Ă��邱�Ƃ�`�������Ǝv���܂��B���N�S������̕ۈ�͕ی�҂̊F����Ǝq�ǂ������ɕs���̖����悤�ɁA�\���ɏ��������������Ǝv���Ă��܂��B
��10�����i2014�N10��1���j
�@�@
�@�@�@�厩�R�̋��Ђ�ڂ̓�����ɂ���ЊQ���܂��N���܂����B�ؑ]�E��ԎR�̕��ŋ]���ɂȂ�ꂽ���X�A�܂��A�ˑR�̕s�K�ɐS�g�Ƃ��敾����Ă��邲�Ƒ��̕��X�ɂ͂Ȃ����߂̌��t��������܂���B�̂���u����܁v�Ɛe���܂�A���w�ł������炩�ɉS���Ă���������ނ����Ƃ������ƁB����Ȋw�����Ă��\�m�͓���Ƃ������Ƃł�����A�l�Ԃ̗͂̋y�Ȃ��Ƃ��낪�����ɑ������B�吨�̎q�ǂ���C����Ă��鎄�����́A����̕�炵�ŏo���邩����A�댯����������낪���Ă����Ȃ��Ă͂ƁA���߂Ďv���܂��B
�@�@�@�P�O���ɓ���A�����Q�V�N�x�̕ۈ珊�����\�����z�z���J�n���܂��B���N�x�͎q�ǂ��E�q��Ďx���V���x�����悢��n�܂�܂����A�ۈ珊�^�c�̓����҂ł��鎄�����ɂ��\���ȗ������o���Ă���Ƃ͌����Ȃ����ŁA�ی�҂ɂ��s��������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���l�s�ɂ��ӌ��\�������ł͓s�}�Ђ悱�ۈ牀�͏]���ʂ�̎��������@�Q�S���P���ɂ��ۈ珊�Ƃ��ĉ^�c����Ɖ��܂����B�c�t���A�ۈ牀�A�F�O�ۈ�{�݂Ȃǂ��ׂĂ̎q�ǂ��Ɋւ��{�݂̑傫�ȓ]���ɑΖʂ���N�ɂȂ�킯�ł����A��������ɕs���傳���邱�ƂȂ��A���m�ȏ������W���Ȃ���A���܂ŃR�c�R�c�Ɖc�ݔ|���Ă����u�������̕ۈ�v�Ɏ��M�������ė�ÂɑΏ����Ă��������Ǝv���܂��B
��9�����i2014�N9��1���j
�@�@
�@�@�@���������āA�������ǂ̂悤�Ɍ��N�ɉ߂��������傫�ȉۑ�ł���Ă��I���܂����B��T�ȗ��A�C����������A��̉��i���������Ă���悤�ł��B���ƒ�̐H���ۈ珊�̋��H�ł͐H�ނ̒��B�ɋC�����ނƂ���ł��ˁB
�@�@�@�����A9��1���͍��Ō��߂Ă���h�Ђ̓��ł��B�������A�e�n�ōs���Ă���h�ЌP���̗l�q��TV�ŗ�����Ă��܂����A�ŋ߂ł͍L���ŋN�����L��̓y������Ɣ�Q�̏��L���ɐV�����Ƃ���ł��B�傫�ȍЊQ�����ۂɋN����ƕK���A���ЈȑO����N���Ă������ׂȒ���ɂ��Ă̏��肴������܂����A���l�s���ɂ��e�n�ɂ���y������댯���ȂǁA�������l�����d���D�悳���ׂ��ł�����Ή�����Ƃ��Ăق����Ǝv���܂��B
�@�@�@�ۈ牀�̎��ӂɂ͏����Ȏ��R����������A�q�ǂ������ɂƂ��Ă͑����̔���������̕��ڂȂ̂ł����A���̕��A�ۈ�҂����͎��R�̕|���ɂ��݊��ł��Ă͂Ȃ�Ȃ��ƐS���Ă��܂��B�Ђ悱�ۈ牀�ł͓�����O�ɂȂ��Ă��āA����̂��Ƃł͂���܂����A�������R�̂��ƂƂ��čs���Ă��鉀�O�U���ł́A�}�Ζʂɖʂ�������ʂ�Ȃ��ȂǑ�J�̌�͖ړI�n�ɏ\�����ӂ�������A���A�����̏��𐳊m�ɃL���b�`���ē`����Ȃǎ��O��������Ǝv���܂��B
�@�@�@��_�E�W�H��k�Ђ̌�ɁA��Ў҂̑̌�����u���Ёv�Ƃ����T�O�����܂�܂����B�u�h�Ёv����Q���o���Ȃ����Ƃ�ڎw�������I�ȑ傫�Ȏ��g�݂ł���̂ɑ��āA���܂�ɑ傫�Ȏ��R�ЊQ�ɑ��Ă͌���ꂽ�\�Z�⎑���ł͑Ή�������Ȃ��̂ŁA���펞�̔�Q�����炷���߂̎��g�݂��l�����d�ɂȂ���Ƃ����o�����琶�ꂽ�T�O�������ł��B�Ђ悱�ۈ牀�ł͏��h���ɂ��h�ЌP���̂��тɁu���Ѝs���̃X�X���v�Ƃ��������q�����������Ă��܂����A�����ɂ͓����{��k�Ђ̋��P����@�܂��́A�n�k���N����O�ɂ��Ȃ�������Ȃ����Ƃ�m��A�������������肵�Ă������ƁB�A���ɁA���ۂɒn�k���N�������̑Ώ����@��m���Ă������ƁB�B�����āA�n�k���N������̑Ή���m��A�K�ɍs�����邱�Ƃ��u���Ёv�ɒ�������ƌ����Ă��܂��B�ۈ牀�ł͎Y�x��������57���ڂ̓������疞7�߂��c���܂�130�l�قǂ̎q�ǂ����W�܂��Ă���̂ł�����A���Б�ɂ��čČ������Ă����܂��B���C�Â��̂��Ƃ�����܂�����w�E���ĉ������B
��7�����i2014�N7��1���j
�@�@
�@�@�@�u�o�ϋ��͊J���@�\�iOECD�j�����ׂ�����n��̒��ŁA���{�̒��w�Z�̋Ζ����Ԃ��ł������Ƃ������ʂ��o���B�N���u�����̌ږ��������A�������ނ���������ƁA���Ƃ̑��̎d�������Ȃ��Ȃ��B���k�ɂƂ��Ē��w�Z�̂R�N�Ԃ͏u���Ԃɉ߂��邪�A���X�Ƒ���o�����t�̖����ɂ͏I��肪�Ȃ��B���{�̐搶�͖Z�����B��X���̕������������K���A�������ɐ搶�������B�����O���Ǝv���Ă����B�����āA���ɂ͂��Ƃ܂����������B��l�ɂȂ��ĐU��Ԃ�A�p��������肾�B�M�S�ȋ��t�Ƃ̉Ă��Ȃ���A�����w�Ҏ��c�ЕF�͒a�����Ȃ�������������Ȃ��B�Ђ����������č炭��躉�(ɳ��ݶ���)�ɊX�p�ŏo��A�䂪�t�̉����v���B�v�i�U���Q�V���@���o�V���@�t�H�����p�@�j
�@�@�@��肾�����Z�����ċx�݂̊ԁA�M�S�ȋ��t���獪�C�悭�����Ă�����������w�Ҏ��c�ЕF�̎q�ǂ��̍��̃G�s�\�[�h���Љ�Ă̋L�q�ł����A�x�݂��S����ꂸ�A�Ђ����瓭�����w���t���Ƒ��Ɏ��҂Ƃ��Ă͑S�������Ɏv���܂��B
�@�@�@�ŋ߁A�}�X�R�~�ɋ��t��x�@���Ȃǂ̕s�ˎ����Ƃ肠�����邱�Ƃ������Ă���A�s�M�������Ă����ۂł����A�����̎��Ԃ�����ĐE���ɒ����ɁA�����M�S�Ɏ��g�ސl���������͐g�߂ɑ吨���Ă��܂����A�����łȂ���Γ��{�̎q�ǂ������̏����͑�ϔߊϓI���ƌ��킴������܂���B�������A����������ĂƔ�r���ėƌ����钆�A�E���̐��s���x���čs���̂͒n��ł���A�q�ǂ������̐e�ł���͎̂����ł���A�Η��ł͂Ȃ����������߂���̂ł��傤�B
�@�@�@���Ƃ܂�ۈ�ł̂����炮�݂̎q�ǂ������͍L���V�я�Ŏv�������V��A�e�Ɨ���Ĉ�l�Ŕ��܂�Ƃ��������̌��̒��ŁA�ЂƂ�ЂƂ肪���낢��Ȍ��������Ă��邱�ƁA���ꂩ��̐����ɐL�т�����R�~���Ă��邱�Ƃ����߂Ď����Ă���܂����B�����āA�q�ǂ������̎�����ގ��ԂƋ�C�ɂ���āA�q�ǂ������̈炿�͂����l�ɂ��ό����݂Ȃ̂��Ȃƍ��X�Ȃ���w���Ă��炢�܂����B���Z�������A�q�ǂ������Ƃ̎��Ԃ�����ĉ��������S�l�̂���������ɂ͖{���Ɋ��ӂł��B���ꂩ�����낵�����肢���܂��B
��5�����i2014�N5��1���j
�@�@
�@�@�@���肬��ɓV�x�����ĂP�Q��ڂ̂Ђ悱�܂���s�����Ƃ��ł��܂����B�e���g��^�[�t����ɂ͑吨�̂����������₨�Ƃ�����Ɋ��Ă��������đ叕����ł����B�܂��A������������͏��߂Ẵt���[�E�}�[�P�b�g���J���Ă�������A��ɂ��킢�ł����ˁB�n��̎q�ǂ��������吨���Ă���Ď�t�̋L���W�v�ł͑S�̂ł��ǂ��Q�T�P���A���Ƃȁ@�P�T�Q���̎Q���ł����B�����d���ɂ��Z�����ɂ�������炸�A�����ⓖ���̂����͂��肪�Ƃ��������܂����B�@
�@�@�@�����������͗F�����Ƃ̍ĊJ�Ɋ��������ȗl�q�ł������A���Ζʂ̏��w���̒��ɂ͕ۈ�m���֎q������ړ����Ă���Ɛi��Ŏ�`���Ă����q�������肵�Ďv�������Ȃ��ِ���𗬂��ł��܂����B������Ƃ����C�����̎����悤�ƐϋɓI�ȐU�镑�������l�̎菕���ƂȂ����o���͔ނ�ɂƂ��đ傫�ȍ��Y�ɂȂ�Ɗ����܂����B
�@�@�@�s���̂��тɕی�҂̕��ɂ́u�Q���Ƌ��́v�̂��肢�����Ă��܂����A�킸��킵�������Ă����������������Ǝv���܂��B�u�ۈ痿���Ă���̂������`���K�v�͂Ȃ��v�A�u�ۈ珊�̋Ɩ�������ۈ�m���S�Ă��ׂ��v�Ƃ����l���������邱�Ƃ͏��m���Ă��܂����A����ł������Ė��x�A���͂̂��肢�����Ă��܂��B�Ȃ��Ȃ�A�s�}�Ђ悱�ۈ牀�ł͕ۈ�̍������Ƃ��āu�ی�҂Ƌ��Ɏq�ǂ�����Ă�v���Ƃ��ɂ��Ă���̂ŁA���X�̕ۈ�ɂ��Ă��s���ɂ����Ă��ی�҂̕��X�ɐϋɓI�ɎQ�悵�Ă��������A����̂܂܂̎q�ǂ��̗l�q��ۈ�̏�Ԃ��������������āA�����Ȃ��ӌ����������������̂ł��B�����N���X�̕�q�ʉ���������A�ł��B
�@�@�@���{�ɂ����Đ����c�܂�Ă����ۈ�͕����I�ɂ��Ȃɂ������Ă��Ȃ��������̒��ŁA�S����ۈ�҂����̐g�����悤�ȓw�͂Ǝq�ǂ������ւ̎v���Ŗa����Ă����ƁA�����Ŗڂɂ��܂��B�ۈ玺�₨������A�G�{�ȂǕn�������ŏ����ł��q�ǂ����������a�ɁA�L���Ɉ�悤�ɂƐ�y�̕ۈ�҂����͊X���ɗ����đi������A�s���ɓ�����������Ɛ��������Ɠ��������āA�����̐��E�Ɍւ��ۈ�̎v�z��z�������Ă��������ł��B
�@�@�@�O�H�j�b�|���ƌ�����قǕ����I�ɖL���ɂȂ����ƌ����Ȃ���A�����s�҂�玙�������������Ă��錻���e���q�ǂ��Ɖ߂������Ƃ���ɂł�������A���m�ɗ���Ȃ��������Ƃ���������s���Ɋ�������Ȃ������͈�̂ǂ�����h�����Ă���̂��낤�Ǝv���Ɠ����ɕۈ珊�̒S���ׂ��ӔC�͏d���Ȃ��Ɗ����Ă��܂��B�@�@�@
��4�����i2014�N4��1���j
�@�@
�@�@�@�t�����ē��������|�J�|�J�ƐS�n�悭�Ȃ�ƃG���g�����X�̂��߂������҂��Ă܂����Ƃ���A����ʁ[���ƐL���Ă���������Ă��܂��B�~�̊ԁA�ł��k�̒��Ɏ葫�������߂Ă����Ƃ��Ă���l�́A�����̒����瓪���o���Ă��鎩���Ƃ҂����肩�Ԃ��āA�e�ߊ��������Ă��܂����B���̊J�Ԃ�������鍠�͎q�ǂ����������R�Ək���܂��Ă����葫���v�������蓮�����đ��肽���~���ɋ����悤�ŁA�O�V�т���߂��Ă��鐺����i�ƒe��ł��܂��B�q�ǂ����q�ǂ��炵�����Ԃ��߂����āA���ƂȂ��q�ǂ������̌��C�Ȋ������������āA���͂��킯�Ă��炦��ۈ珊�͒n��ɂȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ����������Ȃ��Ǝv���܂��B
�@�@�@���̒��͂��낢��Ȏ������������Ďq��Ē��̐e��s���ɂ����Ă��܂��B����A�V���܂荞�ݍL���̒��Ɂu�q�ǂ��̌����T�[�r�X�v�Ƃ����̂�����܂����B���N�O�ɂ͓�����Ђ��u����҂̌����T�[�r�X�v�̃`���V�����Ă����Ȃ��Ǝv���Ȃ��猩�Ă݂�ƁA�w�Z��m�̍s���A��ɉw�̉��D��ʂ�Ƃ��ɃJ�[�h�����������Ƃɂ���ĕی�҂̌g�ѓd�b��p�\�R���ɒʒm�����d�g�݂ŁA�q�ǂ����ǂ��ɂ��邩�����c���o���邱�Ƃœ����e�̈��S��ۏႵ�A�j�[�Y�ɂ҂�����ƓK������V�X�e���ł���Ƃ�������������ł����B�e�͈��S��������Ȃ�����ǁA���w�Z���w�N�Ƃ��Ȃ�A���X�����ŕs���R�Ɋ�����q�����邾�낤�Ȃ��Ƃ��v���܂��B���������w1�N���̂���A�e�ɖق��ēs�o�X�ɏ���Ĉ�l�ʼn����܂ōs�������̖`���S�ɖ������킭�킭�����C���͍��ł��N���Ɋo���Ă��܂��B�̂��ƂĂ���������������c���Ǝv������Ԃ̂����肳�S�z���ē����̏����^��������10�~�ʂ�����Ď�����ʂւ̃o�X�ɏ悹�Ă��ꂽ���ƁA�e�ɂ͓{��ꂽ���Ȃ��̂Ŗق��Ă������ƂȂǃZ�s�A�F�̎v���o�ł��B
�@�@�@���{��������Љ�ƌ����ċv�����ł����A��N���}���Ă����C�Ȓc��V�j�A�͂��ꂱ���吨����̂ł�����q�ǂ�������������҂ƌ�������X�̈��S���S�̕邵�ɍv���ł��邱�ƁA�Љ�I�]���̘g�g�݂��ł���Ƃ������ȂƎv���܂��B�Ђ悱�ۈ牀�ł����������A���ꂳ��A���o����ƔN��w�ɕ����o�Ă��܂����B�̗́A�C�͂Ƃ��܂��܂��[��������ׂ��w�߂����Ǝv���Ă��܂��B
�@�@�@���N�x���܂��q�ǂ�������^�ɂ��Ă��ǂ��ۈ牀�ɂ��Ă��������Ǝv���܂��B��낵�����肢�������܂��B
�@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@�@
 �g�b�v�y�[�W�֍s��
�g�b�v�y�[�W�֍s��
�@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@